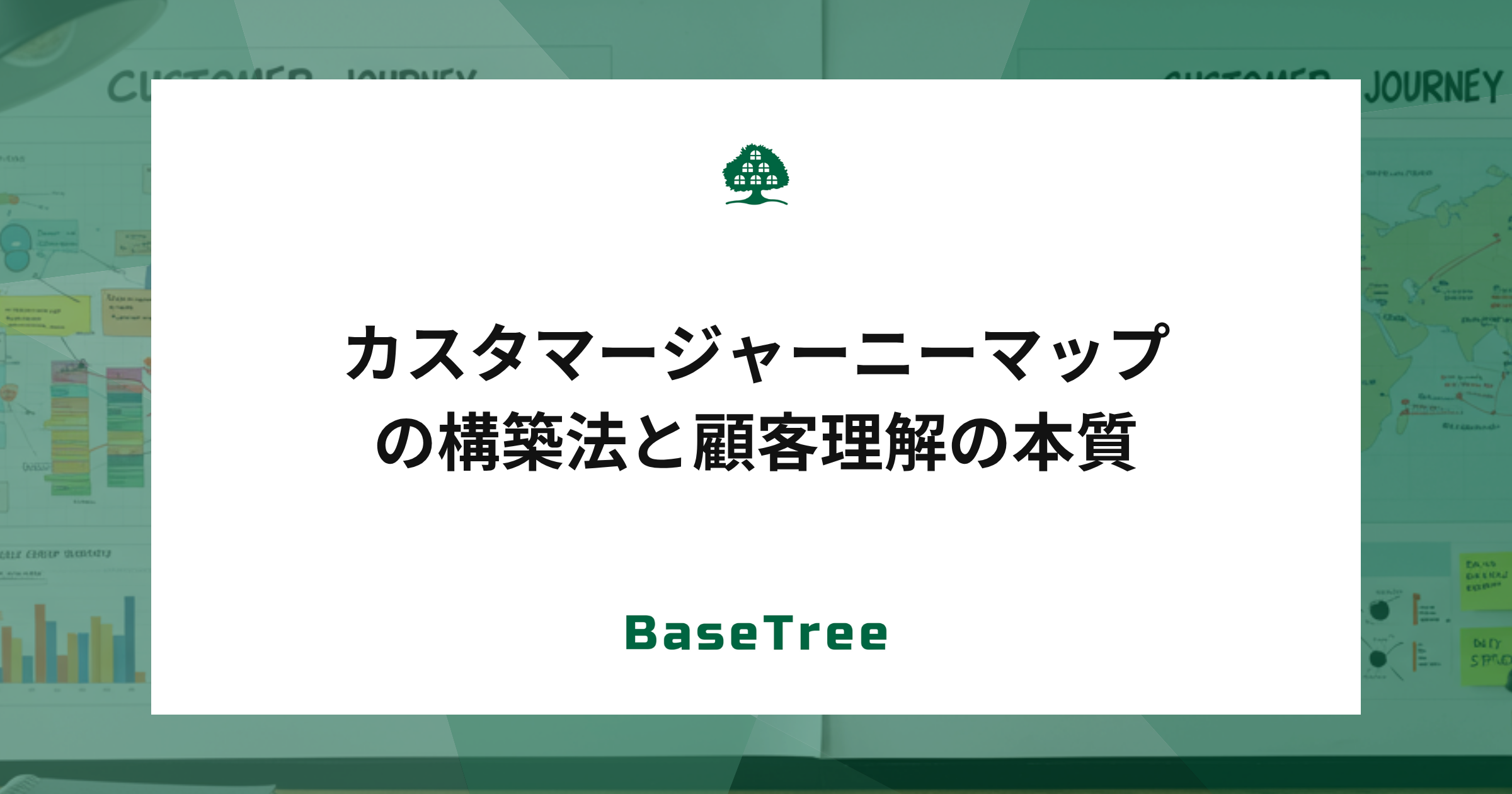カスタマージャーニーマップとは?経営資源としての本質、Webサイト制作における意義
カスタマージャーニーマップは顧客が商品やサービスを認知してから購入・利用に至るまでの道のりを可視化したものです。
単なる「顧客のロードマップ」ではなく、組織の成長を支える重要な経営資源になり得ます。
私がWEBディレクターとして10年間、様々なクライアントのサイト制作に携わる中で気づいたのは、多くの企業が「自社の視点」で情報発信をしているという事実。
顧客がどのような体験をし、何を感じているのかを把握できていない企業が驚くほど多いのです。
カスタマージャーニーマップの本質は「顧客視点での体験の見える化」にあります。
顧客が何を考え、どう感じ、どう行動するのか。
その一連のプロセスを可視化することで組織全体が顧客視点を共有できるようになります。
では、なぜこのカスタマージャーニーマップが単なるマーケティングツールではなく「経営資源」になるのでしょうか?
その理由と構築法について、実践的な視点からお伝えします。
Webサイト制作におけるカスタマージャーニーマップの意義

Webサイト制作においてカスタマージャーニーを考慮することの意義は計り知れません。なぜなら、サイトはただの情報発信ツールではなく、顧客との重要な接点(タッチポイント)だからです。
顧客は様々な段階でWebサイトを訪れます。商品やサービスを初めて知る「認知段階」、詳しい情報を集める「検討段階」、購入を決断する「購買段階」、そして購入後の「利用段階」。それぞれの段階で顧客が求める情報は異なります。
カスタマージャーニーの基本的な段階
一般的なカスタマージャーニーは、以下のような段階で構成されています。
- 認知段階:顧客が自分の課題や欲求に気づき、解決策を探し始める段階
- 検討段階:複数の選択肢を比較検討する段階
- 決定段階:特定の商品やサービスを選び、購入を決断する段階
- 利用段階:実際に商品やサービスを利用する段階
- 推奨段階:満足した顧客が他者に推奨する段階
これらの各段階において、顧客は異なる疑問や不安、期待を持っています。Webサイトがこれらの心理状態に適切に応えられるかどうかが、成約率を左右するのです。
例えば、認知段階の顧客には「なぜこの商品・サービスが必要なのか」という基本的な情報が重要です。一方、検討段階の顧客には競合との違いや具体的な導入事例が求められます。決定段階では料金や申込方法といった実務的な情報が必要になるでしょう。
カスタマージャーニーを理解することで、これらの段階ごとに適切な情報を適切なタイミングで提供できるWebサイトを設計することが可能になります。
Webサイト制作において見落とされがちなカスタマージャーニーの重要性
多くの企業がWebサイト制作を「デザイン」や「機能」の問題として捉えています。確かに見た目の良さや使いやすさは重要です。しかし、本当に効果的なWebサイトを作るためには、もっと根本的な視点が必要なのです。
それが「カスタマージャーニー」という考え方です。カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの一連の流れのこと。この顧客の「旅」を理解し、Webサイトに反映させることが、真に成果を生み出すサイト制作の鍵となります。
10年間WEBディレクターとして様々なクライアントのサイト制作に携わってきた経験から言えるのは、見た目や機能だけを重視したWebサイトは、いくら美しくても成果につながらないということ。顧客がどのような思考や感情の変化を経て購買に至るのかを理解し、それに沿った情報設計をすることが、本当の意味で「使える」Webサイトを作る秘訣なのです。
なぜ多くの企業サイトは成果に結びつかないのか
「ホームページを作ったけど問い合わせが来ない」「サイトはあるけど営業ツールとして機能していない」こんな悩みを抱える企業は少なくありません。その原因は一体どこにあるのでしょうか。
多くの場合、Webサイトが成果に結びつかない根本的な理由は「自社視点での情報設計」にあります。自分たちが伝えたいことを中心に構成されたサイトは、残念ながら顧客の求める情報とズレていることが多いのです。
例えば、企業が「自社の歴史」や「技術力の高さ」を前面に押し出したとしても、初めてサイトを訪れた顧客が知りたいのは「この会社は自分の課題を解決してくれるのか?」という点です。顧客の関心事と企業の発信内容がズレていれば、どれだけ洗練されたデザインのサイトでも成果には結びつきません。
自社都合の情報設計が引き起こす問題
自社視点でのWebサイト制作がもたらす具体的な問題点を見てみましょう。
まず挙げられるのが「顧客が求める情報が見つけにくい」という状態です。企業側の組織構造や商品カテゴリーに基づいたメニュー構成は、顧客にとって直感的ではないことが多いのです。
次に「情報の優先順位が顧客ニーズと合っていない」という問題。企業が重要だと考える情報と、顧客が知りたい情報には大きなギャップがあります。例えば、企業は自社の強みや特徴を伝えたいと考えますが、顧客が最初に知りたいのは「具体的にどんなサービスを提供しているのか」「いくらかかるのか」といった基本情報かもしれません。
さらに「顧客の購買段階に合わせた情報提供ができていない」点も大きな問題です。初めて訪れた人と、すでにサービスを比較検討している人では、必要とする情報が異なります。それぞれの段階に応じた情報を適切に提供できていないサイトは、成約率の向上に繋がりません。
これらの問題を解決するためには、顧客視点に立ち返り、カスタマージャーニーを理解することが不可欠です。
なぜカスタマージャーニーマップは「経営資源」になるのか?

カスタマージャーニーマップが単なる「付箋を貼っただけの紙」から「経営資源」へと変わるポイントは、組織全体での活用にあります。
私がBaseTreeを創業した理由の一つは、多くの企業で「情報が分断されている」という課題を目の当たりにしたからです。営業部門が持つ顧客理解と、製造やサービス提供部門が持つ顧客理解が異なり、さらに経営層が持つ理想像と顧客の実態も乖離しています。
カスタマージャーニーマップが経営資源として機能する理由は、以下の4つです。
- 組織の共通言語になる:部門間のコミュニケーションギャップを埋め、顧客理解を統一
- 意思決定の基準になる:「顧客にとって価値があるか」という判断軸を提供
- リソース配分の指針になる:顧客体験の重要ポイントに投資を集中できる
- 組織の成長指標になる:顧客体験の改善度合いを測定する基準点になる
特に重要なのは「共通言語」としての側面です。
カスタマージャーニーマップ作成を通じて、営業、マーケティング、製品開発、カスタマーサポートなど、あらゆる部門が同じ顧客像と体験プロセスを共有することで共通認識が生まれ、組織としての一貫性や各部門の目的や役割が鮮明になります。
カスタマージャーニーマップの基本構造と作り方

効果的なカスタマージャーニーマップを構築するには基本的な構造を理解することが重要です。
一般的なカスタマージャーニーマップは、横軸に時間軸(顧客の行動プロセス)、縦軸に顧客の行動・感情・タッチポイントなどの要素で構成されます。
基本的なカスタマージャーニーマップは以下の5ステップで作成します。
1. ペルソナ設定:誰(ペルソナ)の旅を描くのか
まずは、ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を明確にします。
年齢や性別だけでなく、役職・職務、性格・考え方、趣味嗜好など、顧客の行動に影響を与える要素を具体的に設定します。
BtoB企業の場合は特に役職や立場による意思決定プロセスの違いが大きいため、「マーケティング部長」「情報システム部の担当者」など、具体的な役職や立場を設定することが重要です。
2. フェーズ設定:旅のステップを定義する
次に顧客の行動プロセスをフェーズに分けて設定します。
一般的なフェーズとしては以下のようなものがあります。
- 認知フェーズ:商品やサービスの存在を知る
- 興味関心フェーズ:詳細を調べ始める
- 検討フェーズ:他社と比較検討する
- 購入・契約フェーズ:実際に購入・契約する
- 利用フェーズ:商品・サービスを使用する
- 推奨フェーズ:他者に推薦する
これらのフェーズは業種や商材によって異なります。
例えばパッケージ化されたソフトウェアを販売する場合は「トライアル」「初期設定」「活用」「更新」などのフェーズ設定になるでしょう。
3. 顧客行動の洗い出し:どんな行動をするのか
各フェーズで顧客がどのような行動をとるのかを具体的に洗い出します。
「Google検索する」「口コミサイトを見る」「友人に相談する」「店舗を訪問する」など、できるだけ具体的に記述します。
この行動の洗い出しにはアクセス解析データ、顧客インタビュー、営業担当者からのヒアリングなど複数の情報源を活用することが大切です。
実際の顧客の声を反映させることで精度が高くリアルな顧客行動に近いカスタマージャーニーマップになります。
4. 感情と思考の洗い出し:何を感じ、考えているのか
顧客の行動だけでなく各ステップでの感情や思考も重要です。
「不安を感じている」「選択肢が多すぎて混乱している」「安心感を得た」など感情の起伏を記録します。
ここで大切なのは、ポジティブな感情だけでなくネガティブな感情も正直に記録すること。
問題点を隠さずに可視化することで改善すべきポイントが明確になります。
5. タッチポイントの整理:どこで接点を持つのか
顧客が企業と接触する「タッチポイント」を整理します。
Webサイト、SNS、メール、電話、店舗、営業担当者などあらゆる接点を洗い出しマップ上に配置します。
デジタルとリアルの両方のタッチポイントを網羅することで、オムニチャネル時代の顧客体験を総合的に把握できます。
オムニチャネルとは実店舗、オンラインショップ、SNSなど、企業が顧客と接するあらゆるチャネル(接点や経路)を連携し、顧客がどのチャネルを利用しても一貫した体験を提供できるようにすることです。
経営資源として活用するためのカスタマージャーニーマップ構築法
次に、カスタマージャーニーマップを「作って終わり」にせず、真の経営資源として活用するための構築法をお伝えします。
1. 経営課題と紐づける
カスタマージャーニーマップを作る際はまず経営課題と紐づけることが重要です。
「売上向上」「顧客満足度向上」「解約率低減」など、解決したい経営課題を明確にしてから取り組みましょう。

例えば「新規顧客獲得コストが高い」という課題がある場合、認知・興味関心フェーズに焦点を当てたマップを作成し、効率的なマーケティング施策を検討します。
「解約率が高い」という課題なら利用フェーズに重点を置いたマップを作成します。
2. 複数部門を巻き込んだワークショップ形式で作成する
カスタマージャーニーマップはマーケティング部門や営業部門だけで作るものではありません。製品開発、カスタマーサポート、経営層など、顧客に関わるすべての部門を巻き込んだワークショップ形式で作成することで多角的な視点を取り入れることができます。
各部門が持つ顧客情報を持ち寄り「この段階で顧客は何を考えているのか」「なぜこの行動をとるのか」を議論することで、より深い顧客理解が生まれます。
3. 定量データと定性データを組み合わせる
精度の高いカスタマージャーニーマップを作るには定量データと定性データの両方を活用することが大切です。
- 定量データ
アクセス解析、コンバージョン率、顧客満足度調査など - 定性データ
顧客インタビュー、営業担当者の声、SNSでの顧客の声など
例えば「Webサイトの特定ページでの離脱率が高い」という定量データと、「情報が多すぎて何を見ればいいかわからない」という顧客の声を組み合わせることで、具体的な改善策が見えてきます。
4. 現状と理想のギャップを可視化する
「現状のカスタマージャーニー」と「理想のカスタマージャーニー」の2つを作成し、そのギャップを可視化すると課題がより浮き彫りになります。
現状と理想のギャップが、具体的な改善施策につながります。

例えば「現状では問い合わせから見積もりまで平均5日かかっている」のに対し、「理想は24時間以内」というギャップがあるとします。
このギャップを埋めるためには、見積もりプロセスの自動化やテンプレート化、その前に価格の均一化や組織としての料金テーブル制定から着手すべきかもしれません。
顧客の何を解消するために、何をするのか。
場当たり的ではなく目的を明確にすることが、時間短縮や成果率向上に直結します。
5. KPIと紐づけて継続的に改善する
カスタマージャーニーマップを経営資源として活用するために、具体的なKPIと紐づけることが不可欠です。
各フェーズやタッチポイントごとに測定可能な指標を設定し、定期的に測定・改善するサイクルを回します。
例えば「認知フェーズ」なら「ブランド認知度」「Webサイト訪問数」、「検討フェーズ」なら「資料請求数」「デモ申込数」などの指標を設定し、定期的に測定します。
カスタマージャーニーマップを経営資源として活用する実践例
カスタマージャーニーマップを経営資源として活用する具体例をご紹介します。
実践例1:顧客の声を製品開発に活かす
あるSaas企業がカスタマージャーニーマップを活用して、顧客の「痛点」を製品開発に反映させます。
カスタマージャーニーマップの作成によって、顧客が「初期設定」フェーズで混乱や不満を持っていることが可視化できたとします。
初期設定時の「わからない」「迷う」というネガティブ感情に着目し、ステップバイステップのチュートリアル動画の追加や、設定ウィザード(画面上に表示させる操作説明)の改善、初期設定サポートや、導入1ヶ月のフォローアップメールを提供プロセスに組み込むなどが改善施策として考えられます。
どの取り組みが効果を発揮したのか?は、初期設定の完了率やソフトウェアの解約率低減をKPI(目標数値)とすることで定量的に計測できます。
また、改善施策を行う前と後の両方で顧客へのインタビューを実施しておくと、「使いやすさ」「見やすさ」といった定性的な計測や効果検証が可能です。
実践例2:オムニチャネル戦略を強化する
ある小売業でオンラインとオフラインの顧客体験を統合するために、カスタマージャーニーマップを活用したとします。
オンラインで商品を検索し、実店舗で確認して購入するという行動パターンが可視化できたので、チャネル間の連携を強化します。

具体的にはオンラインで「在庫あり」と表示された商品が実店舗で見つからないというネガティブ体験に注目し、在庫管理システムのリアルタイム連携や、店舗スタッフへのタブレット配布による在庫確認の迅速化を改善施策として定めます。
この取り組みが功を奏したかは、「オンラインで見て店舗で買う」顧客の満足度が向上や平均購入単価増をKPIに設定します。
例えばオンラインショップや当該商品のアクセス数と実店舗での販売数の相関や、来店者の購入率、購入者の平均単価などをKPIとします。
実践例3:営業プロセスを改善した製造業
ある製造業でBtoBの営業プロセスを改善するためにカスタマージャーニーマップを活用したとします。
特に「情報収集」から「見積もり依頼」までの検討フェーズに着目し、顧客の不安や疑問を可視化しました。
具体的には「価格がわからない」「導入事例が少なく不安」という顧客の声に対応し、Webサイトに価格シミュレーターや詳細な導入事例を追加。また、営業資料も顧客の検討フェーズに合わせて再構成します。
問い合わせから受注までの期間や工数をKPIに設定したり、営業資料を送付した顧客の契約数や契約率を追うことで、顧客の不安や疑問を解消できる取り組みだったのかが計測できます。
カスタマージャーニーマップを組織に定着させる4つのポイント

カスタマージャーニーマップを一過性のワークショップで終わらせず、組織に定着させるための4つのポイントをご紹介します。
1. 経営層のコミットメントを得る
カスタマージャーニーマップを経営資源として活用するには経営層の理解とコミットメントが不可欠です。
経営課題との紐づけを明確にし具体的な成果指標を設定することで、経営層の支持を得やすくなります。
BaseTreeでは、クライアント企業の経営層に対してカスタマージャーニーマップと経営指標の関連性を明確に示すことで、全社的な取り組みにつなげています。
数値化できる効果を示すことが経営層の理解を得るポイントです。
2. 担当者・責任者を明確にする
カスタマージャーニーマップを継続的に活用するには、「カスタマージャーニーマネージャー」のような担当者や責任者を設置することが効果的です。
この担当者が中心となってマップの更新や改善施策の進捗管理を行います。
担当者はマーケティング部門だけでなく顧客接点を持つ様々な部門から選出することで、全社的な視点を持ったマップ運用が可能になります。
3. 定期的な更新と改善のサイクルを確立する
カスタマージャーニーマップは「生きた資料」として定期的に更新することが重要です。
市場環境の変化、新サービスの投入、顧客行動の変化などに合わせて、四半期や半期ごとにマップを見直し、改善施策を検討します。
更新のタイミングは事業計画の見直しや予算策定のタイミングと合わせることで、経営計画との連動性を高めることができます。
4. デジタルツールを活用して共有・更新を容易にする
カスタマージャーニーマップを紙やホワイトボードだけで管理するのではなく、デジタルツールを活用することで共有や更新が容易になります。
デジタルツールを使えばリモートワーク環境でも全社で最新のマップを共有できます。
BaseTreeではNotionを活用してカスタマージャーニーマップを管理し、関連する施策や担当者、進捗状況も一元管理しています。
情報の一元化がマップの活用度を高めるポイントです。
カスタマージャーニーを活かしたWebサイト制作の具体例
カスタマージャーニーを理解することで、Webサイト制作はどのように変わるのでしょうか。
カスタマージャーニーを効果的にWebサイト設計で活かすための具体例を列挙してみます。

あるBtoB企業のWebサイトリニューアルを例に考えてみます。
従来のサイトは会社概要や事業内容が中心で、顧客視点での情報設計がなされていませんでした。
カスタマージャーニーを分析した結果、以下のような改善を行うことにしました。
認知段階の顧客への対応
認知段階の顧客は、まだ自社サービスについて詳しく知りません。
顧客が最初に知りたいのは「この会社は自分の課題を解決できるのか」という点です。
この段階の顧客に対してトップページで明確に「どんな課題を解決できるか」を示し、業界や課題別の入り口を設けます。
顧客はプロではないため、専門用語を極力避け、初めて訪れた人でも理解しやすい言葉で説明することを心がけることにしました。
さらに「よくある課題」のセクションを設け、顧客が自分の状況と照らし合わせやすいようにします。
課題を先んじて提示することで「この会社は自分の課題を理解している」という安心感を持っていただける可能性を高めます。
検討段階の顧客への対応
検討段階の顧客はすでに課題解決の必要性を認識し、複数の選択肢を比較しています。
この段階では「なぜ他社ではなく自社を選ぶべきか」という差別化ポイントが重要です。
競合との明確な違いを示すページや、具体的な導入事例・成功事例のセクションを充実させることにしました。
特に事例は業種や課題別で検索できるようにし、自社の状況に近い事例を見つけやすくします。
よくある質問(FAQ)ページでは検討段階の顧客が持ちやすい疑問(「他社サービスとの違いは?」「導入にかかる期間は?」など)に焦点を当てて再構成します。
決定段階の顧客への対応
決定段階の顧客はすでに購入を前向きに検討しており、具体的な条件や手続きを確認したいと考えています。
料金プランのページを詳細かつ透明性を持って設計し、「隠れたコスト(追加費用や不明瞭な見積項目)」がないことを明確にします。
申込みフォームへの導線を分かりやすくし、複数のステップに分けることで心理的なハードルを下げることにしました。
さらに導入までの流れを図解で示したページを新設し、契約までどのような手順で進むのか?契約後に何をどんなステップで履行してくれるのか?を記載し、顧客の不安を取り除く工夫をします。
これらの「顧客の不安や疑問解消のための地道な改善」の結果が、Webサイトからの問い合わせ数増加や、成約率向上に繋がります。
カスタマージャーニーを理解することで顧客の心理把握に努め、心理に寄り添うために何をどこにどうやって配置するのか?掲載するのか?がWebサイト設計であり、Webサイト運用です。
カスタマージャーニーを中心に据えたWebサイトは事業の情報資産になる
Webサイトは単なる情報発信ツールではなく、顧客との重要な接点であり企業の貴重な「情報資産」となり得るものです。
カスタマージャーニーを中心に据えたWebサイト設計により、その資産価値を最大化できます。
営業・採用・教育に活用できる情報基盤の構築
カスタマージャーニーに基づいたWebサイトは営業活動の強力な武器となります。
顧客の段階に応じた情報が適切に整理されているため、営業担当者は顧客の状況に合わせて必要なページを案内できます。
例えば、初期接触の顧客には課題解決の概要ページを、検討段階の顧客には事例や比較ページを、決定段階の顧客には具体的な導入手順や料金ページを案内するといった具合です。
また、採用活動においても、求職者のジャーニーを考慮したコンテンツ設計が効果的です。
「なぜこの会社で働くべきか」「どんな仕事をするのか」「どんなキャリアパスがあるのか」など、求職者の疑問に段階的に答えるサイト構造が、質の高い応募者の獲得につながります。
さらに、社内教育のツールとしても活用できます。
新入社員や異動してきた社員が、自社の商品・サービスや価値観を理解するための情報源として、適切に構造化されたWebサイトは非常に有効です。
情報の一元管理と継続的な改善サイクル
カスタマージャーニーを中心に据えたWebサイトでは、情報が体系的に整理されているためコンテンツの一元管理が容易になります。
情報の重複や矛盾を防ぎ、常に最新かつ一貫性のある情報提供が可能になります。
また、サイトのアクセス解析と顧客フィードバックを継続的に収集・分析することで、カスタマージャーニーの理解をさらに深め、サイトを常に進化させることができます。
例えば特定のページで離脱率が高い場合、そのページが顧客の求めるものに応えられていない可能性があります。
顧客の声を集め、ジャーニーマップを更新し、コンテンツを改善するというサイクルを回すことで、サイトの効果を継続的に高めていくことができるのです。
組織全体での顧客理解の共有
カスタマージャーニーマップを基にしたWebサイト設計は、組織全体で顧客理解を共有する基盤にもなります。
マーケティング部門だけでなく、営業、カスタマーサポート、商品開発など、あらゆる部門が同じ顧客像と顧客の旅を理解することで、一貫した顧客体験を提供できるようになります。
特に組織が大きくなるほど重要です。
店舗間や部門間の連携が難しくなる中で、Webサイトが「顧客理解の共通言語」として機能することで、組織全体の顧客中心主義を促進することができます。
カスタマージャーニーを中心に据えたWebサイトは、単なる情報発信ツールを超えて企業の重要な情報資産となり、事業全体の成長を支える基盤となるのです。
カスタマージャーニーを活かしたWebサイト制作の実践ステップ
ここまでカスタマージャーニーの重要性と活用方法について説明してきましたが、実際にどのようにWebサイト制作に取り入れていけばよいのでしょうか。
具体的な実践ステップを見ていきましょう。

ステップ1:顧客理解のための情報収集
まずは顧客を深く理解するための情報収集から始めましょう。
- 顧客インタビュー:実際の顧客に直接話を聞くことで、生の声を集めることができます。特に「なぜその商品・サービスを選んだのか」「検討過程でどんな情報を探したか」といった点を掘り下げましょう。
- アンケート調査:より多くの顧客から定量的なデータを集めるのに有効です。
- サイトアクセス解析:現在のサイトがある場合は、どのページが多く見られているか、どこで離脱が多いかなどのデータを分析します。
- 問い合わせ内容の分析:顧客からの質問や問い合わせを分析することで、情報ニーズを把握できます。
- 競合サイトの分析:競合がどのように顧客ジャーニーに対応しているかを調査します。
収集した情報を基にペルソナとカスタマージャーニーマップを作成します。
ステップ2:情報設計とサイトマップの作成
カスタマージャーニーマップを基にサイトの情報設計を行います。
- 顧客の段階に応じたコンテンツ分類:認知、検討、決定など、各段階に必要なコンテンツをグループ化します。
- 直感的なナビゲーション設計:顧客が求める情報に素早くたどり着けるメニュー構造を設計します。
- 検索行動を考慮したページ構成:顧客がどのような検索キーワードでサイトにたどり着くかを考慮し、それに対応するページを設計します。
- コンバージョンポイントの戦略的配置:各段階に適したコンバージョンポイント(問い合わせフォーム、資料ダウンロードなど)を配置します。
顧客の思考段階と情報動線を整理してサイトマップを作成し、全体の構造を明確にします。
ステップ3:ワイヤーフレームとプロトタイプの作成
サイトマップを基に、各ページのワイヤーフレーム(骨組み)を作成します。
- 情報の優先順位付け:各ページで最も重要な情報を目立つ位置に配置します。
- 顧客の疑問に答える構成:各段階で顧客が持ちやすい疑問に答える情報を適切に配置します。
- 次のステップへの誘導:顧客のジャーニーを進めるための自然な導線を設計します。
- モバイル対応の考慮:スマートフォンでの閲覧体験も同様に設計します。
ワイヤーフレームを基にクリック可能なプロトタイプを作成し、実際の顧客に使ってもらってフィードバックを得ることも有効です。
ステップ4:コンテンツ制作とデザイン
ワイヤーフレームを基に実際のコンテンツを制作します。
- 顧客の言葉を使う:業界用語や専門用語ではなく、顧客が実際に使う言葉でコンテンツを作成します。
- 段階に応じたトーンと詳細度:認知段階では概要を、検討段階では詳細を、といったように段階に応じた情報の詳細度を調整します。
- 視覚的要素の効果的活用:文字だけでなく、画像、図解、動画などを適切に活用して理解を促進します。
- 信頼性を高める要素:顧客の不安を取り除くための証拠(実績、事例、お客様の声など)を適切に配置します。
デザインは自社の「カッコイイ」や「キレイ」優先ではなく、顧客の感情や期待に合わせたビジュアルイメージを選択することが重要です。
ステップ5:テストと改善
Webサイトが完成したら実際の顧客にテストしてもらい、フィードバックを基に改善します。
- ユーザビリティテスト:実際の顧客に特定のタスクを行ってもらい、使いやすさを評価します。
- A/Bテスト:特定の要素(見出し、ボタンの色、配置など)の異なるバージョンを比較し、より効果的な方を選びます。
- アクセス解析:サイト公開後も継続的にデータを分析し、改善点を見つけます。
- 顧客フィードバック:問い合わせや感想を集め、サイトの改善に活かします。
反響情報を収集・整理するステップを通じて、カスタマージャーニーに基づいた効果的なWebサイトを構築し継続的に改善していくことができます。
カスタマージャーニーマップ構築の注意点と失敗しないための4つのコツ
最後に、カスタマージャーニーマップを構築する際の注意点と失敗しないための4つのコツをお伝えします。

1. 理想と現実を混同しない
カスタマージャーニーマップを作る際によくある失敗は「理想の顧客行動」と「現実の顧客行動」を混同してしまうことです。
まずは現状を正確に把握することが重要です。
特にネガティブな顧客体験や不満点は目を背けてしまいがちだったり、そもそも内部では気づきづらいこともあります。
顧客からのフィードバックや自社が提供している情報や体験を客観的に捉え、包み隠さず可視化することで、真に価値のある改善点が見えてきます。
「こうあってほしい」という願望ではなく「実際はこうなっている」という現実から始めましょう。
2. 過度に複雑化しない
カスタマージャーニーマップは詳細であればあるほど良いというものではありません。
あまりに複雑すぎると全体像が見えにくくなり、活用されなくなってしまいます。
まずは主要なフェーズとタッチポイントに絞ったシンプルなマップから始め、必要に応じて詳細化していくアプローチが効果的です。
全体像を把握するための「マクロマップ」と、特定のフェーズを詳細に分析する「ミクロマップ」を使い分けるのも一つの方法です。
3. 仮説に頼りすぎない
カスタマージャーニーマップは社内の仮説だけで作成すると、実際の顧客行動とかけ離れたものになりがちです。
可能な限り実際の顧客データや顧客の声に基づいて作成することが重要です。
顧客インタビュー、アンケート調査、行動ログ分析、SNSでの声の収集など、多様な方法で顧客の実態を把握しましょう。
特に「なぜそう思ったのか」「なぜその行動をとったのか」という理由や背景を深堀りすることが重要です。
どうでしょう?カスタマージャーニーマップの重要性が伝わりましたか?
4. 施策と紐づけないと「絵に描いた餅」になる
カスタマージャーニーマップを作っただけで満足してしまい、具体的な施策に落とし込まないケースが非常に多いです。
マップは「気づき」を得るためのツールであり、作成が最終目的ではありません。
マップから見えてきた課題や機会を具体的な施策に落とし込み、実行・検証するサイクルを回すことが重要です。
各タッチポイントでの改善施策を明確にし、優先順位をつけて実行していきましょう。
カスタマージャーニーマップを次のレベルに引き上げる発展的な4つの手法
基本的なカスタマージャーニーマップを作成した後、さらに効果を高めるための発展的な手法をご紹介します。

1. マルチペルソナ・マルチシナリオ対応
実際の現場では単一のペルソナや単一の購買プロセスだけでは捉えきれないことが多いです。
複数のペルソナや、異なる購買シナリオに対応したマップを作成することで、より包括的な顧客理解が進みます。
例えばBtoB企業であれば「最終決裁者」「実務担当者」「影響力を持つステークホルダー」など、役割の異なるペルソナごとにマップを作成することで、それぞれに最適なアプローチが見えてきます。
2. デジタルとリアルの統合
現代の顧客行動はデジタルチャネルとリアルチャネルを行き来するのが一般的です。
オンラインで情報収集し、実店舗で確認して、再びオンラインで購入するといった複雑な行動パターンを可視化することが重要です。
チャネル間の連携や情報の一貫性を確保するためにオムニチャネル対応のカスタマージャーニーマップを作成することで、繋がりを持った一貫性ある顧客体験を設計できます。
3. 感情曲線の活用
顧客の感情の起伏を「感情曲線」として可視化することで注力すべきポイントが明確になります。
ポジティブな感情のピークをさらに高める施策や、ネガティブな感情を改善する施策を優先的に検討しましょう。
特に重要なのは最終接点での感情です。
最後に良い印象で終われば、それまでの小さな不満は相対的に軽減されることが心理学的にも証明されています。
最終接点での顧客体験を特に重視しましょう。
4. Journey Map Ops(ジャーニーマップ・オペレーション)の導入
カスタマージャーニーマップを一度作って終わりにするのではなく、継続的に運用・改善するための「Journey Map Ops」という考え方があります。
これはカスタマージャーニーマップを中心に据えた業務オペレーションの仕組みを構築することです。
具体的には、カスタマージャーニーマネージャーの設置、定期的なマップの更新プロセス、KPIモニタリング、改善施策の実行管理など、マップを「生きた経営資源」として活用するための体制づくりが含まれます。
カスタマージャーニーマップを経営資源に変える実践ステップ
カスタマージャーニーマップは単なるマーケティングツールではなく、組織全体で活用できる重要な経営資源です。
顧客視点での体験可視化や組織の共通言語として機能し、一貫性のある顧客体験の提供と継続的な改善が可能に。
本記事で触れた「カスタマージャーニーマップを経営資源として活用するための実践ステップ」をおさらいします。
- 経営課題と紐づける:解決したい経営課題を明確にし、マップの目的を設定する
- 全社を巻き込む:部門横断のワークショップでマップを作成し、共通理解を形成する
- データに基づく:定量・定性データを組み合わせ、実態を反映したマップを作成する
- ギャップを可視化する:現状と理想のギャップから、具体的な改善施策を導き出す
- KPIと紐づける:測定可能な指標を設定し、改善効果を可視化する
- 定期的に更新する:市場環境や顧客行動の変化に合わせて、マップを更新する
- デジタルツールを活用する:共有・更新を容易にするツールを導入する
BaseTreeではWebサイト制作やマーケティング支援においてカスタマージャーニーマップを中心に据えています。
「カスタマージャーニーマップはもう古い、使えない」という意見もありますが、特にこれからWebマーケティングやWebサイトに注力される企業や担当者にとってカスタマージャーニーマップは、施策の優先順位やチームで目的意識を共有できる効果的なツールです。
カスタマージャーニーマップがなければ、とりあえずSEO・Web広告、とりあえずデザイン性の高いサイトにリニューアル、とりあえずカッコイイ営業資料…など、「顧客」が置き去りのまま施策が錯綜し、成果につながらず、「マーケティングは不要」という結論に陥り、個々人の・各部門で分断された組織に戻っていってしまいます。
カスタマージャーニーマップを経営資源として活用することで、顧客体験の向上だけでなく組織内の共通理解の形成、効率的なリソース配分、継続的な改善サイクルの確立など、多くのメリットが得られます。
ぜひ、自社の事業・商品・顧客に合わせたカスタマージャーニーマップを構築し、経営資源として活用してみてください。
顧客視点で価値を整理し、成果を生み出す経営資源としてのWebサイト制作についてもっと詳しく知りたい方は、BaseTreeのWebサイト制作サービスをぜひご覧ください。
理念・構造・価値を言語と設計で伝えるWebサイト制作で、あなたの企業の価値を最大化するお手伝いをします。