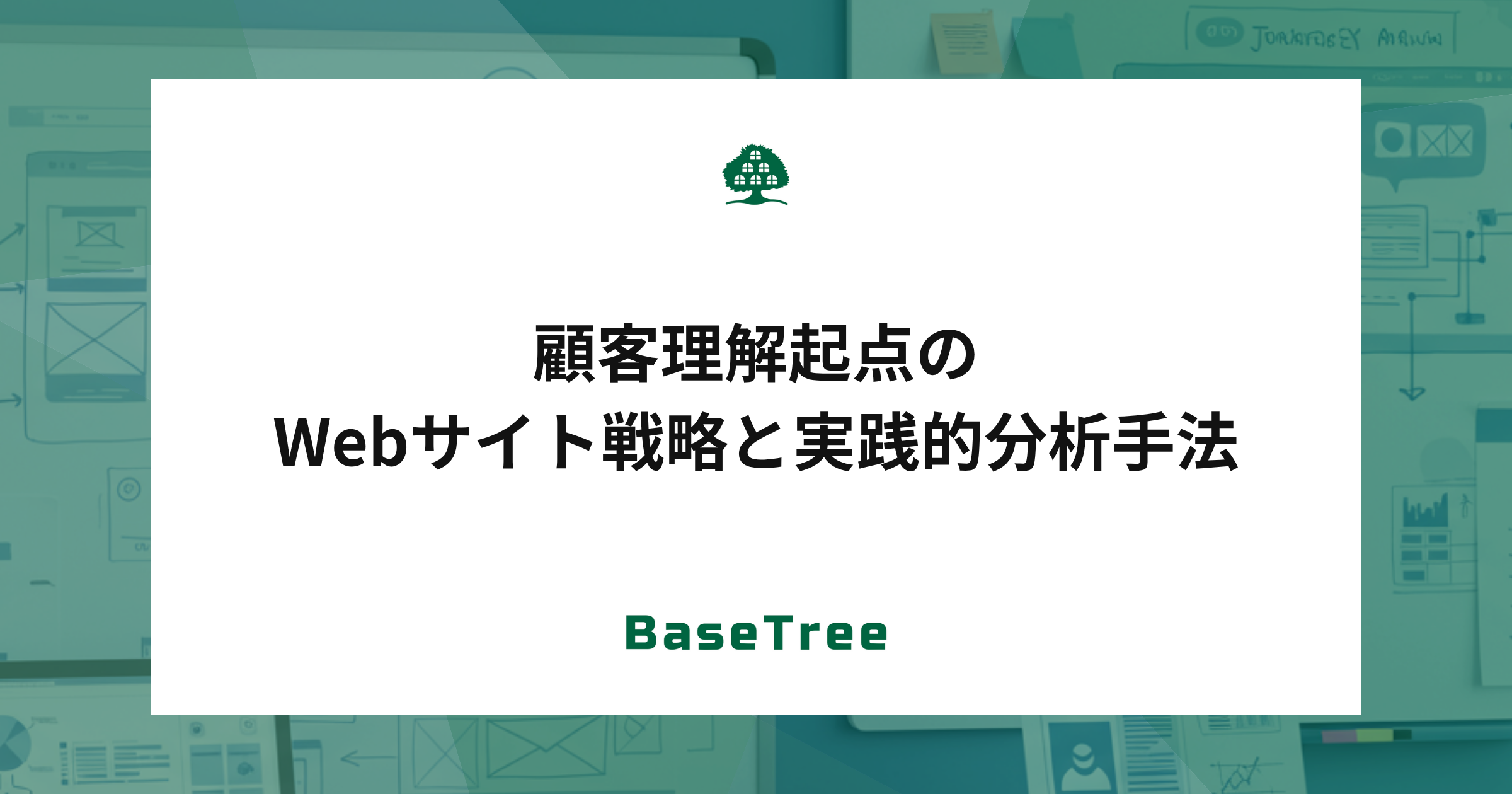Webサイト戦略における顧客理解の本質
Webサイトは単なる情報発信ツールではありません。
顧客との対話の場であり、組織の価値を伝える重要な接点です。
多くの企業が「ちゃんとしたホームページを作りたい」「事業やサービスを正しく伝えたい」と願いながらも、実際には自社の都合だけで設計されたWebサイトを運用し、期待した成果を得られていないという現実があります。
なぜこのような状況が生まれるのでしょうか?
その根本原因は「顧客理解の欠如」にあります。
顧客が何を求め、どのように情報を探し、どんな体験を期待しているのか。
この理解なしにはどれだけ美しいデザインや高機能なサイトを構築しても、本当の意味での成果には結びつきません。
顧客理解を深めることは単に「誰に向けて話しているか」を知るだけではありません。
顧客の行動パターン、意思決定プロセス、潜在的なニーズや不満、そして彼らが抱える本質的な課題を把握することです。
顧客理解が不足したWebサイトの典型的な4つの問題点
顧客視点での情報設計ができていないWebサイトには、いくつかの共通した特徴があります。これらの問題点を認識することが、改善への第一歩となります。

問題点1:自社都合の情報設計
最も多く見られる問題は「伝えたいこと」が優先され、「知りたいこと」が後回しにされている点。
例えば会社の歴史や理念を語る前に、顧客が求めているのは「この会社は自分の問題を解決できるのか?」という答えです。
自社の都合で情報を配置するとユーザーは読んでも読んでも必要な情報にたどり着けず、離脱率が高まります。
これは単なるデザインの問題ではなく「誰のためのWebサイトか」という根本的な視点の問題です。
マーケティングや営業目的において誰のためのWebサイトかの答えは明白で、「ユーザーのためのWebサイト」です。
問題点2:価値の表現不足
多くの企業サイトでは自社の強みや特長が顧客にとって理解しやすい形で提示されていません。
専門用語や抽象的な表現が多用され「なぜこの会社を選ぶべきか」が伝わりにくくなっています。
例えば「高品質なサービスを提供します」という抽象的な表現よりも、「24時間以内の回答保証で、あなたの緊急の問い合わせにも対応します」という具体的な価値提案の方が、顧客が理解しやすく、どのような対応をしてもらえるのかが明確です。
よくある「安心」「信頼」「安全」「高品質」「プロ」「専門家」の装飾は、何にかかってくるのか?なぜそう言えるのか?
言い切れる根拠や具体性の提示こそ顧客が求めているものであり、貴社の強みや特徴が初めて顧客にとってのメリットになるのです。
問題点3:情報の構造設計の欠如
情報量はあるものの優先順位や関連性が整理されていないため、目的の情報にたどり着きにくいサイトも少なくありません。
ユーザーは自分の求める情報を探すために何度もクリックをしたくありません。
自分にとって有益な情報を、すぐに、簡単に、わかりやすく取得したいのです。
これは「情報の海に溺れる」状態を生み出し、せっかくの価値ある情報も点在していたり、一貫性がないことで閲覧されなくなり、結果的に「あるけど見つからない」になってしまいます。
問題点4:技術的な最適化不足
SEO、ページ速度、モバイル対応などの技術的対策が不十分で、そもそも顧客に発見・閲覧されにくい状態にあるサイトも多く見られます。
どれだけ内容が素晴らしくても、検索エンジンで上位表示されなければ、その価値は限定的なものになってしまいます。
タイトルやディスクリプション、見出し構成など「そんな基本的な対策は意味がない」という意見もありますが、それはすでにオンライン上で名が売れている強者の方便です。
今まで注力して来なかった、業種やサービス名で検索してもヒットしない、地域名を入れても出てこないなど、オンライン上で「弱者」なのであれば、まずは基本的なところはきっちり抑える。
それが弱者でもすぐにできる対策です。
顧客理解を深めるための実践的な4つの分析手法
具体的にどのようにして顧客理解を深め、Webサイト戦略に活かしていくのか、実践的な分析手法をいくつかご紹介します。

分析手法1:ペルソナの再定義と意思決定プロセスの明文化
ペルソナとは製品やサービスの典型的なユーザー像を具体化したものです。
多くの企業では「30代男性、会社員」といった表面的な属性だけでペルソナを定義してしまい、本当の意味での顧客理解には至っていません。
効果的なペルソナ設計では、背景・行動・動機といった深層的な要素を可視化することが重要です。例えば、「なぜその人は自社のサービスを必要としているのか」「どのような状況で検討を始めるのか」「決断を左右する要因は何か」といった点まで掘り下げることで、より具体的な顧客像が見えてきます。
実際の顧客データや営業担当者からのフィードバックを基に、リアルな顧客像を構築することで、「この人に対して、どんな情報をどう伝えるべきか」という具体的な指針が得られます。
分析手法2:カスタマージャーニーの構築
カスタマージャーニーとは顧客が商品やサービスを知ってから購入し、利用するまでの一連の体験プロセスを可視化したものです。
「気づき→検討→選定→導入→利用→推奨」といった段階ごとに、顧客の行動、感情、接点、課題を整理します。
例えば「検討段階」では、顧客は複数の選択肢を比較検討しています。
この段階で顧客が求めているのは「なぜこの会社を選ぶべきか」という明確な理由です。
ここでWebサイトに求められるのは競合との差別化ポイントを分かりやすく示すこと。
各段階で顧客が必要とする情報は異なります。
カスタマージャーニーを構築することで「どの段階の顧客に、どんな情報を、どのように提供すべきか」が明確になり、Webサイトの情報設計に直接活かすことができます。
▶︎関連:カスタマージャーニーマップの構築法と顧客理解の本質
分析手法3:競合サイトの情報構造・言語の調査
業界上位・地域競合などを対象に、ページ構成、表現、導線設計の傾向を比較することも有効です。
ただし単にマネても意味はありません。
なぜなら競合のサイトに書かれている内容は、競合の商品・強み・特徴・地域性・ルーツ・提供体制などに起因しているから、いわば「競合だから」書けることであったり、またはすでに名が通っていて説明不要なので割愛しているからです。
見るべきは「どんな論理展開なのか」「なぜそのような構成になっているのか」「どのような顧客ニーズに応えようとしているのか」「何を根拠や証拠として主張しているのか」を分析することが重要です。
競合サイト分析では、以下の点に注目すると良いでしょう。
- トップページで最も強調されている情報は何か
- どのような言葉で価値を表現しているか
- 顧客の不安や疑問にどう対応しているか
- CTAの配置と表現はどうなっているか
競合サイト分析を通じて、業界の標準的なアプローチを理解するとともに、差別化ポイントを見つけることができます。
分析手法4:VOC(顧客の声)収集と分析
VOC(Voice of Customer)とは顧客の声を指します。
アンケート、インタビュー、問い合わせ内容、SNSの投稿など、様々な接点から得られる顧客の生の声は、Webサイト戦略を考える上で非常に貴重な情報源となります。
特に注目すべきは、顧客が使う言葉です。専門家である私たちが当たり前に使う言葉と、顧客が日常的に使う言葉には大きな隔たりがあることがよくあります。顧客の言葉を理解し、それをWebサイトのコンテンツに反映させることで、顧客にとって理解しやすく、共感を得やすい情報発信が可能になります。
VOC分析では、単に「何を言っているか」だけでなく、「なぜそう言うのか」という背景や文脈を理解することが重要です。表面的な要望の背後にある本質的なニーズを把握することで、より深い顧客理解につながります。
データに基づく顧客行動分析の実践
顧客理解を深める上で定性的な分析だけでなく、定量的なデータ分析も欠かせません。Webサイトから得られる様々なデータを活用することで、顧客の行動パターンや意思決定プロセスをより客観的に把握することができます。

アクセス解析データの戦略的活用
Google Analyticsなどのアクセス解析ツールから得られるデータは、顧客の行動を理解する上で非常に有益です。
単純なPV数やセッション数だけでなく以下のような指標に注目することで顧客の行動や傾向がわかります。
- 流入経路:どのような検索キーワードや参照元から訪問しているか
- ユーザーフロー:サイト内でどのようなページ遷移をしているか
- 滞在時間:どのページに長く滞在しているか
- 離脱率:どのページから離脱が多いか
- コンバージョン率:目標達成に至るまでの経路はどうなっているか
アクセスデータを分析することで、「顧客がどのような情報を求めてサイトを訪れ、どのように情報を探索し、どの段階で離脱または目標達成に至るのか」というプロセスが可視化されます。
特に注目すべきは「期待したとおりに顧客が行動していない箇所」です。
例えば重要なコンテンツページの離脱率が高い場合、そのページの内容やデザインに問題がある可能性があります。
あるいは想定したフローとは異なる経路でコンバージョンに至っている場合、顧客の実際の意思決定プロセスが当初の想定と異なっている可能性があります。
ヒートマップ分析による顧客の注目点把握
ヒートマップツールを使用するとユーザーがページ上のどの部分に注目し、どこをクリックしているかを視覚的に把握することができます。
- 最も注目されている情報は何か
- スクロールの深さ(どこまで読まれているか)
- クリックされているが、実はリンクになっていない要素はあるか
- 重要な情報やCTAが適切な位置に配置されているか
ヒートマップ分析はトップページや重要なランディングページなどの「アクセスが多い」ページやコンテンツの改善に役立ちます。
顧客の視線や行動パターンを理解することで、顧客が求めているものを提示できる、顧客が取得収集しやすい情報設計が可能になります。
フォーム分析とコンバージョン最適化
問い合わせフォームや資料請求フォームなどのコンバージョンポイントは、Webサイトの成果を左右する重要な要素です。
- フォームの完了率(どの程度の訪問者が最後まで入力を完了するか)
- 放棄率の高いフィールド(どの項目で入力を諦めるユーザーが多いか)
- 入力にかかる平均時間
- エラーが発生しやすい項目
フォーム分析結果を基にフォームの簡素化や入力支援機能の追加、説明文の改善などを行うことで、コンバージョン率を高めることができます。
例えば必須項目を最小限に抑える、入力例を示す、エラーメッセージを分かりやすくするといった改善策が考えられます。
フォーム送信後のサンクスページも重要な接点です。
適切なフォローアップ情報を提供することで次のステップへの案内ができます。
顧客理解に基づくWebサイト構造設計の実践
ここまで見てきた顧客理解の手法を基に、実際にWebサイトの構造をどのように設計していくべきかを考えてみましょう。
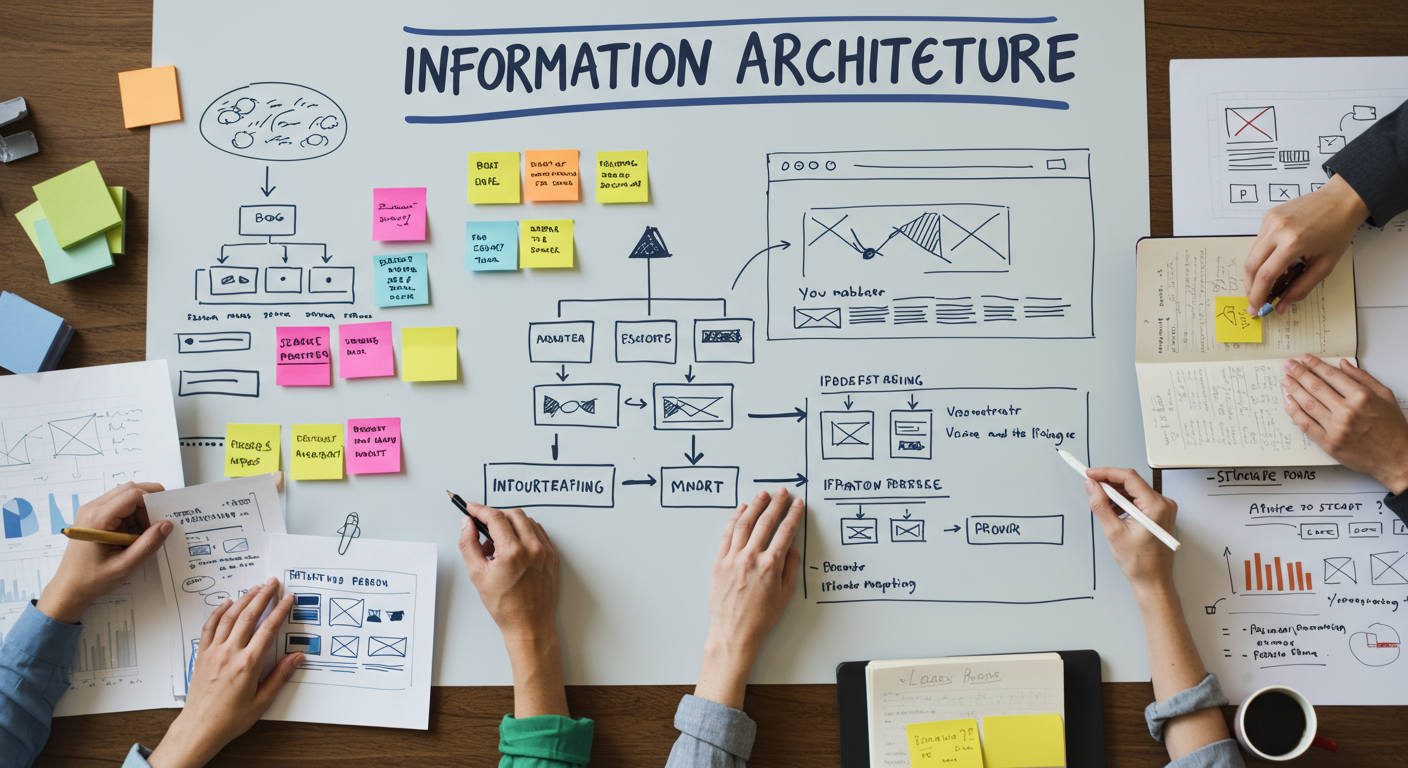
情報の階層化と優先順位付け
顧客理解に基づいてどの情報をどのような順序で提示するかを決定します。
以下の3つの視点からの優先順位付けが有効です。
- 顧客にとっての重要度:顧客が最も知りたい情報は何か
- ビジネスにとっての重要度:自社として最も伝えたい価値は何か
- 意思決定プロセスにおける順序:顧客はどのような順序で情報を求めるか
顧客視点を総合的に考慮し、トップページから下層ページへの情報の流れを設計します。特に重要なのは顧客の「知りたいこと」と企業の「伝えたいこと」のバランスです。
例えば製品・サービスを探している初期段階の顧客には…
- まず「どんな問題を解決できるのか」という価値提案を示す
- 次に「なぜこの会社を選ぶべきか」という差別化ポイントを伝える
- その後で具体的な製品・サービスの詳細や料金体系を提示する
という流れが効果的かもしれません。
顧客の言葉を活かしたコンテンツ設計
VOC分析(顧客の声分析)で得られた顧客の言葉を活用し、顧客にとって理解しやすく、共感を得やすいコンテンツを設計します。
- 専門用語の使用を最小限に抑え、必要な場合は分かりやすい説明を加える
- 顧客が実際に使う言葉や表現を取り入れる
- 抽象的な表現よりも具体的な事例や数値を示す
- 顧客の課題や悩みに共感する表現を用いる
例えば「高度なテクノロジーを駆使した統合ソリューション」といった抽象的な表現よりも、「入力作業を70%削減し、月末の請求書処理時間を半分に短縮」といった具体的な価値を示す方が、顧客の理解と共感を得やすくなります。
カスタマージャーニーに基づく導線設計
カスタマージャーニー分析で把握した顧客の意思決定プロセスに沿って、サイト内の導線を設計します。
各段階で顧客が求める情報を適切に提供し、次のステップをスムーズに案内することが重要です。
例えば「認知」段階の顧客には、問題提起と解決の可能性を示すコンテンツを提供し、「検討」段階の顧客には、比較検討に役立つ情報や事例を提供します。
「決定」段階の顧客には具体的な次のアクション(問い合わせ、資料請求など)を明確に示します。
各ページに適切なCTA(Call To Action)を配置し、顧客の行動を促すことが重要です。CTAは単なる「お問い合わせはこちら」ではなく、顧客にとっての価値や次のステップで得られるものを明確に示す表現にしましょう。
モバイルファーストの視点による最適化
業種にもよりますが、現在では大半のユーザーがスマートフォンからWebサイトにアクセスしています。
モバイル環境での使いやすさを最優先に考えた設計(モバイルファースト設計)が重要です。
- 限られた画面サイズでも重要な情報が一目で分かるようにする
- タップしやすいボタンサイズと間隔を確保する
- スクロールの深さを考慮し、重要な情報を上部に配置する
- ページの読み込み速度を最適化する
- フォームの入力項目を最小限に抑え、入力支援機能を充実させる
モバイルでの体験最適化は、単にスマートフォンユーザーの満足度を高めるだけでなく、検索エンジンでの評価にも直結する重要な要素です。
Googleも「モバイルファーストインデックス」という、「スマートフォンで見たときの速さ・見やすさ・使いやすさを重視する」ことを発言しています。
顧客理解に基づくWebサイト運用と継続的改善
Webサイトは公開して終わりではなく継続的に運用・改善していくことで価値を高めていきます。
顧客理解に基づいたWebサイト運用と改善のポイントを見ていきましょう。

データに基づく改善サイクルの構築
Webサイトの運用においては、PDCAサイクルを回し続けることが重要です。具体的には以下のようなプロセスの確立です。
- Plan(計画):顧客理解に基づいた改善仮説を立てる
- Do(実行):実際にサイトを改善する
- Check(評価):アクセス解析などで効果を測定する
- Act(改善):結果を分析し、次の改善計画を立てる
PDCAサイクルを回し続けることで、顧客のニーズや行動の変化に合わせて、Webサイトを常に最適な状態に保つことができます。
Dの実行がなければ今日も明日も何も変わらない。
大前提で実行が最重要であることは前提として、意外とおざなりになりがちなのがPの「仮説」と、Cの「検証」プロセスです。
「このページのこの部分を変更すれば、顧客はより理解しやすくなるはずだ」という仮説を立て、実際に変更を加えた後で効果を客観的に測定し、また仮説を立て実行する。
なぜやるのか?結果どうだったのか?を土台として、成果につながる可能性の高い実行の積み重ねが改善です。
A/Bテストによる継続的な最適化
A/Bテストとは、2つのバージョンを用意して、どちらがより効果的かを比較検証する手法です。
例えばトップページのヘッドラインやCTAの文言、ボタンの色や配置などを変えて、どちらがコンバージョン率が高いかを測定します。
- 一度に変更するのは1つの要素だけにする(複数変更すると、どの変更が効果をもたらしたのか分からなくなる)
- 十分なサンプル数を確保する(統計的に有意な結果を得るため)
- テスト期間を適切に設定する(季節変動などの影響を排除するため)
- 明確な成功指標を設定する(何を改善したいのかを明確にする)
A/Bテストを継続的に行うことで、課題の切り分けや特定、遷移率や成約率などの確率を向上させ、サイトのパフォーマンスを引き上げることができます。
継続的にテストすることで顧客の好みや行動パターンについての理解も深まっていきます。
顧客フィードバックの収集と活用
Webサイトの改善においては定量的なデータだけでなく、顧客からの直接的なフィードバックも非常に重要です。
- サイト上でのアンケート(例:「お探しの情報は見つかりましたか?」)
- 問い合わせフォームからの意見や質問の分析
- SNSでの言及やコメントのモニタリング
- ユーザーテストや座談会の実施
収集したフィードバックは単に「良い」「悪い」という評価だけでなく、「なぜそう感じたのか」という理由や背景を理解することでより本質的な「感情や感覚」観点の改善につながります。
フィードバックに基づいて改善を行った場合は、その結果を顧客に伝えることも大切です。
「お客様の声を反映して、〇〇を改善しました」というメッセージは、顧客との信頼関係構築にもつながります。
顧客理解を起点としたWebサイト戦略の実現
Webサイト戦略における顧客理解の深化と実践的分析手法について、様々な角度から見てきました。
顧客理解の本質は、単に「誰に向けて話しているか」を知るだけではなく、顧客の行動パターン、意思決定プロセス、潜在的なニーズや不満、そして彼らが抱える本質的な課題を把握することにあります。
ペルソナ設計、カスタマージャーニー分析、競合調査、VOC分析、アクセス解析など、様々な手法を組み合わせて多角的に顧客を理解することが重要です。
得られた顧客理解を基に情報の階層化と優先順位付け、顧客の言葉を活かしたコンテンツ設計、カスタマージャーニーに基づく導線設計、モバイルファーストの視点による最適化など、具体的なWebサイト設計に落とし込んでいきます。
公開後もデータに基づく改善サイクルの構築、A/Bテストによる継続的な最適化、顧客フィードバックの収集と活用を通じて、常に顧客のニーズに応え続けるWebサイトを運用していくことが大切です。
顧客理解を起点としたWebサイトが「活きた情報資産」に
組織の誰もがいつでも「説明できる」Webサイト。
内部にも外部にも使われる「活きた情報資産」。
顧客理解を起点としたWebサイト戦略によって、営業・採用・教育・承継に活用できる「情報資産」としてWebサイトを構築することができます。
Webサイトは「誰に、何を、どのように伝えるか」というコミュニケーションの場です。
顧客理解に基づいた戦略的なWebサイト設計・運用だから、成果につながるWebサイトになる。
顧客視点で企業の価値を翻訳・整理・構造化し、情報発信基盤を構築する—それがWebサイト戦略の本質です。
Webサイト制作でお悩みの方はBaseTreeのWebサイト制作サービスをぜひご検討ください。
顧客視点による価値の翻訳と将来を見据えた成長設計で、「情報発信基盤」構築をサポートします。