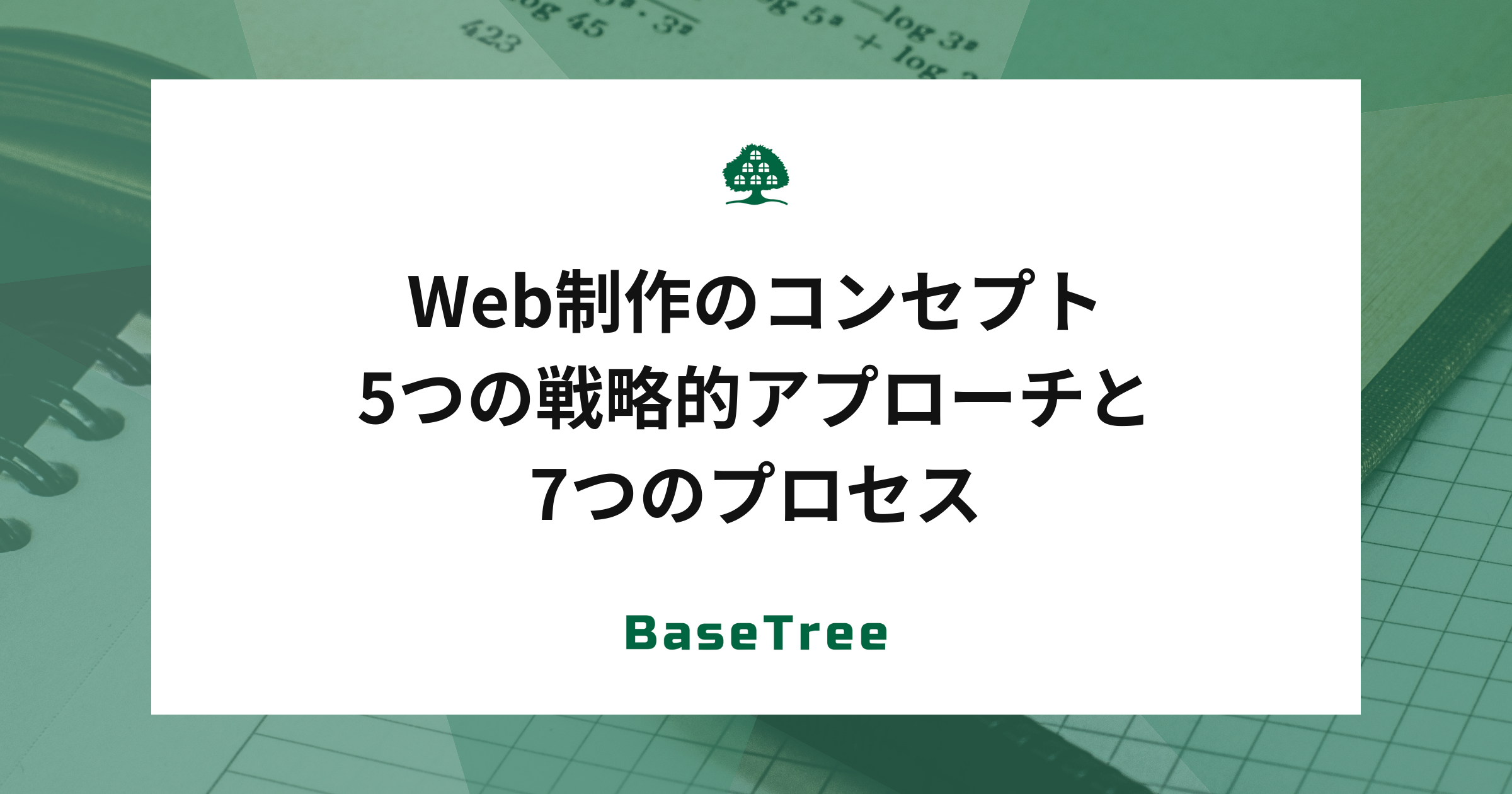Web制作のコンセプトは、Webサイトの存在価値そのもの
Webサイトを新規制作したり、リニューアルしたりする際に最も重要なのは「コンセプト」です。でも、このコンセプトをおろそかにしてしまう企業が驚くほど多いです。
コンセプトとは、そのWebサイトが「誰に」「何を」伝えたいのかを表す概念。
つまり、サイトの存在価値そのものと言えます。
「とりあえずホームページを作ろう」「競合他社がリニューアルしたから、うちも」という理由だけでサイト制作を始めると、結局は誰にも響かないサイトになってしまいます。
私は10年間、WEBディレクターとして多様なクライアントのサイト制作に携わってきました。その経験から言えるのは、成功するWebサイトには必ず明確なコンセプトがあります。
なぜコンセプト決めが重要なのか?
コンセプトがWebサイト全体の方向性を確定し、各コンテンツの方向性をそろえる役割を持つからです。
コンセプトを決めることで、何を取捨選択するかの明確な基準が生まれ、サイト制作に関わる全員が共通認識を持てるようになります。
コンセプトとテーマ、混同しやすい2つの概念
Web制作の現場では「コンセプト」と「テーマ」という言葉がよく使われますが、この2つは似て非なるものです。明確に区別できますか?
テーマとは「何のためのWebサイトを作るのか」という主題のこと。
例えば「オーガニックカフェのWebサイト」「医療分野に特化したリクルートサイト」などが該当します。
一方、コンセプトは「誰に何を伝えたいのか」を表す概念。
先ほどの「オーガニックカフェ」の例でいえば、「健康に気を使うお客様も安心して利用できる」「小さな子供を持つ女性にもカフェタイムを楽しんでほしい」といった内容がコンセプトです。
テーマは1つに絞ることが大切です。
そして、そのテーマを理解してもらうために、どういった切り口が有効かを考えたものがコンセプトになります。
この違いを理解せずに制作を進めると、「何のサイトか分かるけど、何を伝えたいのか分からない」という中途半端なWebサイトが出来上がってしまいます。
私の経験では、クライアントとの打ち合わせで最初にこの違いを明確にしておくことで、その後の制作プロセスがスムーズに進むケースが圧倒的に多いです。
成功サイトに共通する5つの戦略的アプローチ
成功するサイトに共通する5つの戦略的アプローチをご紹介します。
コンセプト決めの際に必ず押さえておきたいポイントです。
戦略的アプローチ1|5W1Hフレームワークによる明確化
コンセプトを決める際に有効なのが「5W1H」というフレームワークです。
6つの要素で考えていきます。
- What(何を)
- Why(なぜ)
- Who(誰が)
- When(いつ)
- Where(どこで)
- How(どうやって)
特に重要なのは「Who(誰が)」と「What(何を)」。
ターゲットユーザーを具体的に設定し、そのユーザーがWebサイトで何ができるのかを明確にすることで、コンセプトの核が見えてきます。
例えば「30代〜40代の子育て中の女性が、自宅で簡単に作れるオーガニック食材のレシピを探せる」というように、具体的に設定することが大切です。
ペルソナをはできるだけ詳細に行うことでコンセプトがより明確になります。
年齢、職業、家族構成、趣味、価値観、インターネット利用習慣など、多角的に考えてみましょう。
戦略的アプローチ2|顧客視点による価値の翻訳
多くの企業サイトが陥りがちなのは「自社視点」での情報発信です。
「当社は○○が強みです」「○○年の実績があります」という情報は、顧客にとって必ずしも価値ある情報とは限りません。
成功するサイトは、企業の強みや特長を「顧客視点」で再解釈し、「だからあなたにとってどんな価値があるのか」を伝えています。
例えば「創業30年の実績」という情報は、顧客視点では「長年の経験から生まれる安心感と信頼性」という価値に翻訳できます。
企業の特徴を顧客にとっての価値に変換する作業が、コンセプト決めでは重要です。
戦略的アプローチ3|競合との差別化要素の明確化
成功するサイトは競合他社との違いが明確です。
コンセプト決めの段階で、競合サイトの比較分析を行い、自社の差別化ポイントを見つけ出すことが重要です。
差別化要素は「価格」「品質」「サービス」「専門性」「独自性」など様々な観点から考えられます。
発見した差別化要素をWebサイトのどこで、どのように表現するかまで考えましょう。
差別化要素を見つけるには、業界上位サイトや地域競合などを対象に、ページ構成、表現方法、導線設計の傾向を比較分析します。
▶︎関連:競合を知りWebマーケティング戦略に活かす、Webサイト制作前にやっておきたい競合分析実践ガイド
戦略的アプローチ4|将来を見据えた成長設計
Webサイトは一度作って終わりではありません。
サービスや商圏の拡大、実績数、設備や提供体制の拡充など事業の成長に合わせて進化させていくもの。
だからこそ、コンセプト決めの段階で将来の拡張性を考慮することが重要です。
現在の事業規模に合わせつつも、今後の展開や施策追加にも対応できる構造を持たせることで、継続的な運用と長期的な投資効果を実現できます。
例えば、現在はシンプルな商品紹介が中心でも、将来的にはユーザーレビューやコミュニティ機能を追加することを視野に入れた設計にしておくことで、大幅なリニューアルなしに機能拡張が可能になります。
戦略的アプローチ5|情報の構造設計と優先順位付け
成功するサイトは情報の構造が明確です。
ユーザーが求める情報にスムーズにたどり着けるよう、情報の優先順位を考えた構造設計が必要です。
コンセプト決めの段階で、「どの情報を最も目立たせるか」「どのような順序で情報を提示するか」を考えることで、ユーザーにとって使いやすいサイトになります。
情報構造を設計する際は、ユーザーの行動パターンを想定したカスタマージャーニーマップを作成すると効果的です。「気づき→検討→選定→導入」の各段階で、ユーザーが必要とする情報を整理し、それをサイト構造に反映させていきます。
私の経験では、情報構造の設計がしっかりしているサイトほど、コンバージョン率が高い傾向にあります。ユーザーが迷わずに目的の情報にたどり着けるよう、直感的な導線設計を心がけましょう。
実践的な7つのコンセプト決定プロセス
5つの戦略的アプローチで、コンセプトの検討材料が集められました。
次に、Webサイトコンセプトを決めるための具体的な7つのプロセスをご紹介します。
プロセス1|事業理解で企業の核心を捉える
まずは、企業やサービスの本質を理解することから始めます。
- 情報整理シートによる棚卸し(提供サービス、ターゲット層、訴求ポイント、競合状況など)
- 経営者・事業責任者へのヒアリング(意思決定の軸、今後の方針、理念の源泉など)
- 営業担当者・採用担当者からの現場視点の収集(顧客・候補者が抱える課題など)
- 既存のWeb・広告データの分析(アクセス解析から見る現状の課題)
特に重要なのは、「なぜその事業を始めたのか」という原点を掘り下げることです。
他社にはない独自の価値観や強みが隠れています。
私がクライアントとの最初の打ち合わせで必ず聞くのは「御社の強みは何ですか?」ではなく「お客様はなぜ御社を選ぶのですか?」という質問です。
この視点の転換だけで、多くの気づきが得られます。
プロセス2|顧客理解でペルソナとニーズを明確化
次に、ターゲットとなる顧客像を具体的に描き出します。
- ペルソナの再定義と意思決定プロセスの明文化
- カスタマージャーニーの構築
- 失注・成功ケースの分解分析
ペルソナ設定では、「30代後半の共働き夫婦で、小学生の子どもがいる」といった具体的な属性だけでなく、「時間に追われている」「子どもの教育に関心が高い」といった価値観や課題まで掘り下げることが重要です。
実際の顧客の声を集めましょう。
アンケートやインタビューを通じて、「なぜ当社を選んだのか」「どんな点に満足しているか」を聞き出すことで、自社の強みを顧客視点で再発見できます。
プロセス3|競合調査で差別化ポイントの発見
競合サイトを比較分析し、差別化ポイントを見つけ出します。
- 競合サイトの情報構造・言語の調査
- 差別化要素の抽出と可視化
- 競合にないコンテンツ設計の立案
競合分析では、単に「どんなデザインか」ではなく、「どんな言葉で価値を伝えているか」「どのような構造でコンテンツを提示しているか」に着目することが重要です。
競合が「機能や性能」を前面に出している場合は「使用感や体験」を、「実績や歴史」を強調している場合は「新しい視点や革新性」を差別化ポイントにすると効果的です。
プロセス4|コンセプト立案と核になるメッセージの創出
ここまでの分析をもとに、サイトの核となるコンセプトを立案します。
コンセプトは「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを一文で表現できると理想的です。例えば「子育て世代のお母さんに、時短でできる健康的な料理のアイデアを、親しみやすい言葉で伝える」といった具合です。
コンセプトを立案する際は、複数の案を出し、それぞれのメリット・デメリットを検討します。
その上で、最も企業の強みを活かせて、かつターゲットのニーズに応えられるものを選びます。
短くてもインパクトのあるコンセプトが理想的です。
長すぎると関係者間で共有しにくく、制作過程で見失われがちになります。
プロセス5|情報設計でサイト構造と訴求優先順位の決定
コンセプトに基づいて、サイトの情報構造を設計します。
- サイトマップ・階層設計
- ページごとの情報設計方針の策定
- 導線設計と行動誘導
情報設計では、ユーザーがサイトを訪れた目的を最短で達成できるよう、直感的な構造を心がけます。
最も伝えたい情報を目立つ位置に配置するなど、優先順位を明確にします。
BaseTreeでは、情報設計の段階でクライアントと綿密な打ち合わせを行い、コンセプトに沿った構造になっているかを何度も確認します。
この段階での調整が、後の工程をスムーズにする鍵となります。
プロセス6|ビジュアル設計でコンセプトの視覚化
コンセプトを視覚的に表現するビジュアル設計を行います。
- ワイヤーフレーム作成
- デザインコンセプト策定
- 画面モックアップとレビュー
ビジュアル設計では、色使い、フォント、画像スタイルなどを通じて、コンセプトを視覚的に表現します。
例えば親しみやすさを伝えたいなら柔らかい色調や丸みを帯びたデザイン、専門性を強調したいなら洗練されたシンプルなデザインを選ぶといった具合です。
重要なのは「見た目の美しさ」ではなく「コンセプトとの一貫性」です。
どんなに美しいデザインでも、コンセプトと合っていなければ効果は半減します。
プロセス7|検証と改善:コンセプトの有効性確認
最後に、立案したコンセプトの有効性を検証し、必要に応じて改善します。
検証方法としては、ターゲットユーザーに実際にサイトを見てもらいフィードバックを得る、A/Bテストで複数のデザインやメッセージの効果を比較する、などがあります。
サイト公開後もアクセス解析を通じて、コンセプトが実際にユーザーに響いているかを継続的に検証することが重要です。ユーザーの行動データをもとに、必要に応じてコンセプトや表現方法を微調整していきます。
最初に立てたコンセプトが100%正解であることはほとんどありません。
検証と改善を繰り返すことで、より効果的なコンセプトへと進化させていくことが成果を生む、成果を最大化する上で欠かせません。
コンセプト決めで陥りがちな5つの落とし穴と対策
Webサイトのコンセプト決めではいくつかの落とし穴があります。
私が経験した典型的な5つの落とし穴と、その対策をご紹介します。
1. 自社視点に偏ったコンセプト
最も多いのが「自社が伝えたいこと」だけに焦点を当てたコンセプト。
「当社の強みを伝える」「製品の機能を紹介する」といったコンセプトは、顧客視点が欠けています。
対策
必ず「顧客にとってどんな価値があるのか」という視点を入れましょう。
「当社の技術力を伝える」ではなく「顧客の課題を解決する技術力を示す」というように変換します。
2. 抽象的すぎるコンセプト
「使いやすいサイトを作る」「分かりやすく伝える」といった抽象的なコンセプトも要注意です。
具体的な指針にならず、制作過程でブレが生じます。
対策
コンセプトは具体的に、できれば数値目標も含めて設定します。
「初めて訪れたユーザーが3クリック以内に必要な情報にたどり着ける」「専門知識がなくても製品の価値が理解できる」など、具体的な表現を心がけましょう。
3. 欲張りすぎるコンセプト
「すべてのターゲットに対応する」「あらゆる情報を網羅する」といった欲張りなコンセプトも失敗の元です。
焦点が定まらず、結局誰にも響かないサイトになりがちです。
対策
「誰に」「何を」伝えるかを絞り込みましょう。
すべてのターゲットに対応しようとするよりも、最も重要なターゲットに焦点を当て、そこで成功を収めることが先決です。
貴社にとってのメイン、大本命、ど真ん中は「誰」で、「何」を求めているのか。
他のターゲットは段階的に対応していくという考え方が必要です。
4. トレンドに振り回されるコンセプト
「最新のデザイントレンドを取り入れる」「他社が採用している機能を実装する」といった、トレンドに振り回されるコンセプトも危険です。
トレンドは移り変わりますが、企業の本質的な価値は変わりません。
対策
トレンドは表現方法の参考程度にとどめ、コンセプトの核は企業の本質的な価値に置きましょう。
「最新のデザインを取り入れる」ことよりも「企業の価値を最も効果的に伝えるデザインを採用する」という考え方が重要です。
5. 検証なしのコンセプト
コンセプトを決めたら終わり、という考え方も危険です。
どんなに練り上げたコンセプトでも、実際のユーザーに響くかどうかは検証してみないと分かりません。
対策
コンセプトは仮説と考え、実際のユーザー反応をもとに継続的に検証・改善していく姿勢が重要です。アクセス解析やユーザーフィードバックを活用し、PDCAサイクルを回していきましょう。
落とし穴を避けることで、より実用的なWebサイトコンセプトを作り上げることができます。
コンセプト決めは一度で完璧を目指すのではなく、継続的に改善していく過程と捉えることが成功への近道です。
成功するWebサイトは明確なコンセプトから始まる
Webサイトのコンセプト決めは、単なる準備段階ではなく、サイトの成否を左右する最も重要なプロセスです。本記事でご紹介した内容をまとめると、以下のポイントが重要です。
- コンセプトとは「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを表す概念であり、サイトの存在価値を定義するもの
- 成功するサイトに共通する5つのアプローチ(5W1Hフレームワーク、顧客視点による価値の翻訳、競合との差別化、将来を見据えた成長設計、情報の構造設計)を活用する
- コンセプト決定の7ステップ(事業理解、顧客理解、競合理解、コンセプト立案、情報設計、ビジュアル設計、検証と改善)を丁寧に進める
- コンセプト決めでよくある5つの落とし穴(自社視点、抽象的表現、欲張りすぎ、トレンド追従、検証不足)を避ける
- 成功事例から学び、自社の状況に適したアプローチを選択する
Webサイト制作においてデザインや機能は重要ですが、あくまでコンセプトを実現するための手段です。
明確なコンセプトがなければ、どんなに美しいデザインや最新の機能を取り入れても効果がありません。
コンセプト決めには時間と労力がかかりますが、この段階にしっかりと投資することで、その後の制作プロセスがスムーズになり、最終的には成果につながるWebサイトが完成します。
BaseTreeはWebサイトを単なる情報発信ツールではなく、営業・採用・教育・承継に活用できる「情報資産」として構築するお手伝いをしています。
Webサイトのコンセプト決めでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
貴社の本質的な価値を掘り下げ強みを見つけ、顧客にとってのメリットに翻訳するWebサイトづくりをサポートします。
詳細はBaseTreeのWebサイト制作ページをご覧ください。