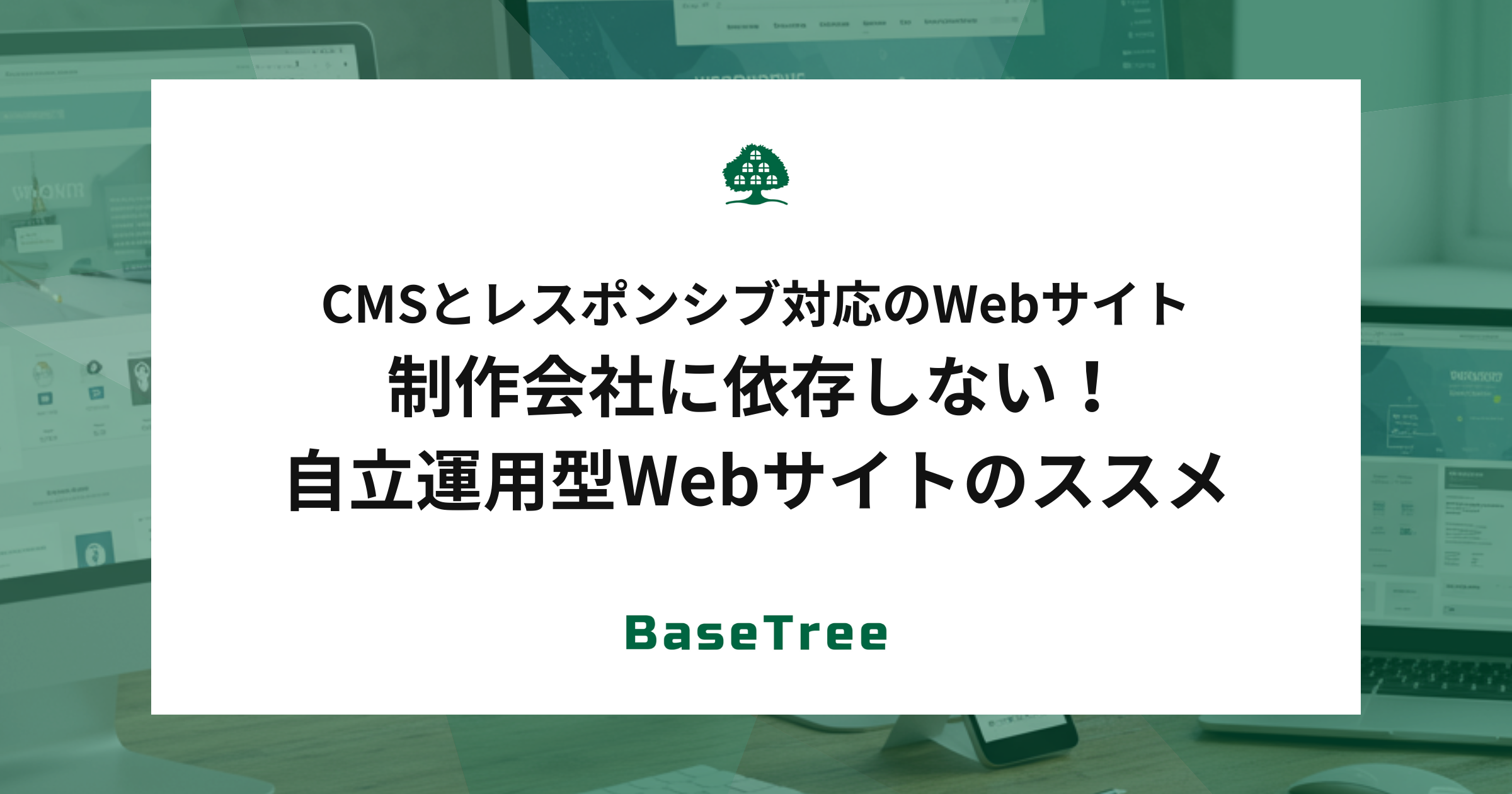「Webサイトの更新をお願いしたいのですが…」
「申し訳ありません。担当者が退職してしまって、すぐには対応できません」
このような会話、経験したことはありませんか?多くの企業がWebサイトの制作・運用を外部の制作会社に依存した結果、思うように更新できない、高額な保守費用が発生する、緊急時に対応してもらえないといった問題に直面しています。
Webサイトは単なる情報発信ツールではなく、営業・採用・教育・承継に活用できる「情報資産」です。この資産を他社に完全依存することは、ビジネスにおける大きなリスクとなり得ます。
10年間にわたりWeb制作に携わってきた経験から言えることは、「制作会社に依存しない自立型のWebサイト運用」こそが、持続可能なWeb戦略の鍵だということです。
なぜ制作会社依存から脱却すべきなのか
なぜ多くの企業がWebサイト運用で苦労しているのか?その根本原因は「制作会社への過度な依存」にあります。
Webサイトを外部に丸投げすると、一見すると楽に思えますが、実際には様々な問題が発生します。
高額な保守・運用コストの発生
制作会社に依存したWebサイト運用では、小さな修正や更新であっても都度費用が発生します。テキストの修正一つ、画像の差し替え一つに数万円の費用がかかるケースも珍しくありません。
ある中小企業では、月額5万円の保守費用を支払っていたにもかかわらず、実際の更新作業は月に1回程度のテキスト修正だけ。年間60万円もの費用を、わずかな作業のために支払っていたのです。
このような状況は、特に予算の限られた中小企業にとって大きな負担となります。
更新の遅延とタイムラグの発生
外部の制作会社に依頼する場合、更新までに時間がかかることが一般的です。依頼から実際の反映まで数日から数週間かかるケースも少なくありません。
これは市場の変化が激しい現代において致命的な問題となり得ます。競合他社が即座に情報を更新する中、自社だけが古い情報を掲載し続けることになるからです。
特に価格改定やキャンペーン情報、採用情報などタイムリーな更新が必要な情報ほど、このタイムラグの影響は大きくなります。
ブラックボックス化による知識・ノウハウの蓄積不足
制作会社に全てを任せることで、自社内にWebサイトに関する知識やノウハウが蓄積されません。その結果、制作会社との契約が終了した際に、サイトの構造や更新方法について理解している人材がいないという事態に陥ります。
私が支援した企業の中には、前の制作会社が作ったサイトの管理画面にすらアクセスできず、サーバーやドメインの契約状況も把握できていないケースがありました。これは企業にとって大きなリスクです。
Webサイトは企業の重要な資産であるにもかかわらず、その管理方法や構造を理解している人が社内にいないというのは、会社の通帳や印鑑の保管場所を誰も知らないようなものです。
自立型Webサイト運用のメリット

制作会社依存からの脱却は、単にコスト削減だけが目的ではありません。自立型のWebサイト運用には、ビジネス全体に波及する様々なメリットがあります。
コスト削減と予算の効率的活用
自社でWebサイトを更新・管理できるようになれば、小さな修正や日常的な更新にかかるコストを大幅に削減できます。これにより浮いた予算を、サイトの機能拡張やコンテンツ制作など、より価値を生み出す施策に投資することが可能になります。
ある製造業の中小企業では、自立型運用に切り替えた結果、年間の保守費用80万円が不要になりました。その予算を活用して、自社製品の詳細な解説動画を制作し、問い合わせ数が1.5倍に増加した事例もあります。
スピーディーな情報発信と即時対応力
自社で更新できる体制が整えば、新しい情報を即座にWebサイトに反映させることができます。市場の変化や顧客ニーズに迅速に対応することで、ビジネスチャンスを逃さない体制を構築できるのです。
特に昨今のように社会情勢が急速に変化する時代においては、この即時対応力が競争優位性につながります。制作会社に依頼して数日後に更新されるのを待つのではなく、必要な情報を必要なタイミングで発信できる体制は、現代のビジネスにおいて不可欠です。
社内のWebリテラシー向上とナレッジの蓄積
Webサイトの運用を内製化することで、社内のWebリテラシーが向上し、デジタルに関する知識やノウハウが蓄積されます。これは単にWebサイトの運用だけでなく、デジタルマーケティング全般やDX推進においても大きな資産となります。
実際に自社運用に切り替えた企業では、Webサイト更新のスキルを身につけた社員が、その経験を活かしてSNS運用やオンライン広告の管理にも携わるようになり、デジタルマーケティング全体の底上げにつながったケースが多く見られます。
Webサイトの自立運用は、単なるコスト削減策ではなく、企業全体のデジタル変革の第一歩と捉えるべきなのです。
Webサイト制作の失敗を防ぐ!CMSとレスポンシブ対応の重要性

Webサイトを制作する際、「とりあえずホームページを作れば良い」と考えていませんか?
10年間WEBディレクターとして様々なクライアントのサイト制作に携わってきた経験から言えるのは、ただ見た目が良いだけのサイトは「情報発信の道具」にすぎず、本当の価値を生み出せないということです。
多くの企業が抱えるWebサイトの課題は、自社都合の情報設計、価値の表現不足、情報の構造設計の欠如、顧客視点の欠如などが挙げられます。これらは単なるデザインの問題ではなく、「伝える構造と言語の未設計」という根本的な問題に起因しています。
今回は、Webサイト制作で失敗しないための重要な要素である「CMS(コンテンツ管理システム)」と「レスポンシブ対応」について、選び方のポイントを解説します。
適切なCMSとレスポンシブデザインを選ぶことで、あなたのWebサイトは単なる情報発信ツールではなく、営業・採用・教育・承継に活用できる「情報資産」として機能するようになります。
CMSとは?Webサイト運営の効率を高める仕組み
CMSとは「Content Management System(コンテンツ管理システム)」の略で、Webサイトのコンテンツを簡単に作成・管理するためのシステムです。専門的なプログラミング知識がなくても、誰でもWebサイトの更新ができるようになる便利なツールです。
CMSを使うことで、HTMLやCSSなどの専門知識がなくても、文章や画像を入力するだけでWebサイトを更新できます。まるでWordのような感覚で操作できるため、Web制作の専門家でなくても簡単に情報発信できます。
- コンテンツの作成・編集・削除が簡単にできる
- 複数人でのWebサイト運営が可能(権限管理機能)
- 公開スケジュールの設定ができる
- テンプレートによるデザインの統一感の維持
- スマートフォンなど様々な端末への対応(レスポンシブ対応)
- SEO対策の基本機能を搭載
CMSを導入することでWebサイトの運用コストを大幅に削減できるだけでなく、情報の鮮度を保ちながら継続的に発信できます。
BaseTreeでは、CMSを活用したWebサイト制作により、単なる情報発信ツールではなく、「経営資源」として機能するWebサイトの構築を支援しています。
CMSの種類と特徴比較
CMSには大きく分けて3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、自社の目的や運用体制に合ったものを選ぶことが重要です。
1. オープンソース型CMS
無料で利用できるオープンソースのCMSで、世界中の開発者によって機能改善が続けられています。カスタマイズの自由度が高く、プラグインで機能拡張も可能です。
- WordPress
世界中のWebサイトの約40%以上が利用する最も人気のあるCMS。プラグインやテーマが豊富で、ブログからコーポレートサイト、ECサイトまで幅広く対応。 - Joomla
WordPressとDrupalの中間的な位置づけで、中規模サイトに適しています。 - Drupal
高度なカスタマイズが可能で、大規模サイトや複雑な構造のサイトに向いています。
オープンソース型CMSは初期費用を抑えられる反面、カスタマイズやセキュリティ対策には専門知識が必要になることがあります。
2. クラウド型CMS
サーバーやシステムの管理が不要で、インターネット上でWebサイトの作成・管理ができるサービスです。初心者でも簡単に始められるのが特徴です。
- Wix:ドラッグ&ドロップで直感的に操作できるエディタを搭載。デザインテンプレートも豊富。
- Jimdo:日本語サポートが充実しており、初心者でも簡単に使いこなせます。
- Shopify:ECサイト構築に特化したCMSで、決済システムなども充実。
クラウド型CMSは手軽に始められる反面、カスタマイズの自由度はやや制限されます。また、月額料金が発生するサービスが多いため、長期運用のコストを考慮する必要があります。
3. 商用パッケージ型CMS
企業向けに開発された有料のCMSで、セキュリティや機能性に優れています。大規模サイトや特定の業界向けの専門機能を備えたものが多いです。
- Movable Type:日本企業に人気の高いCMSで、セキュリティに優れています。
- Sitecore:大規模サイト向けの高機能CMSで、マーケティング機能も充実。
- Adobe Experience Manager:企業の大規模サイト向けの統合型CMS。
商用パッケージ型CMSは機能性やセキュリティが高い反面、導入コストが高く、専門的な知識が必要になることが多いです。
レスポンシブWebデザインとは?モバイル時代の必須要素
レスポンシブWebデザインとは、様々な画面サイズのデバイス(PC、タブレット、スマートフォンなど)に対して、自動的に最適な表示を行う設計手法です。
スマートフォンからのインターネット利用が全体の過半数を超える現在、レスポンシブ対応は単なるオプションではなく、Webサイト制作における必須要素となっています。

Googleは2018年に「モバイルファーストインデックス」を導入し、モバイル端末向けのWebサイトを優先して評価するようになりました。つまり、スマートフォンで見やすいサイトでなければ、検索順位が下がってしまう可能性が高いです。
レスポンシブWebデザインには、主に以下の3つの種類があります。
1. レスポンシブレイアウト
画面サイズに応じて、あらかじめ設定された「ブレイクポイント」でレイアウトが切り替わる方式です。最も一般的なレスポンシブ対応の手法で、多くのCMSやテンプレートで採用されています。
2. リキッドレイアウト
画面サイズに応じて、コンテンツが流動的に変化する方式です。パーセンテージベースでサイズを指定するため、どのような画面サイズでもスムーズに対応できます。
3. フレキシブルレイアウト
レスポンシブとリキッドの特徴を組み合わせた方式で、より柔軟な対応が可能です。
最新のWebデザインでは、このフレキシブルレイアウトが増えています。
レスポンシブ対応のWebサイトを制作することで、デバイスごとに別々のサイトを作る必要がなくなり、管理の手間やコストを削減できます。また、ユーザーにとっても、どのデバイスからアクセスしても一貫した体験を提供できるというメリットがあります。
レスポンシブ対応を選ぶポイント|ユーザー体験を最大化する方法

レスポンシブWebデザインを選ぶ際には、以下のポイントを考慮して、ユーザー体験を最大化するデザインを選びましょう。
1. モバイルファーストの思考
現在のWeb制作では、「モバイルファースト」の考え方が主流です。まずスマートフォンでの表示を最適化し、そこからタブレット、PCへと拡張していく設計手法です。
スマートフォンでの使いやすさを優先することで、多くのユーザーにとって快適な体験を提供できます。特に、若年層や主婦層など、スマートフォンからのアクセスが多いターゲット層を持つ企業には重要なポイントです。
2. 表示速度の最適化
レスポンシブデザインでは、画像やコンテンツの表示速度も重要な要素です。特にモバイル環境では、通信速度の制約があるため、表示速度の最適化が必要です。
- 画像の最適化(サイズ圧縮、適切なフォーマット選択)
- 遅延読み込み(Lazy Loading)の実装
- 不要なスクリプトやスタイルの削減
- キャッシュの活用
表示速度が遅いサイトはユーザーの離脱率が高くなり、SEO評価にも悪影響を与えます。Googleの「Core Web Vitals」など、表示速度に関する指標も確認しておきましょう。
3. タッチ操作への対応
スマートフォンやタブレットでは、マウスではなく指でのタッチ操作が基本です。そのため、以下のような点に配慮したデザインを選ぶことが重要です。
- タップしやすいボタンサイズ(推奨は44px×44px以上)
- 十分な余白の確保
- スワイプやピンチなどのジェスチャー対応
- ホバー効果に依存しないデザイン(タッチデバイスではホバーができない)
タッチ操作に最適化されたデザインは、ユーザーのストレスを減らし、コンバージョン率の向上にもつながります。
4. コンテンツの優先順位付け
画面サイズが小さくなると、すべての情報を同じように表示することは難しくなります。そのため、コンテンツの優先順位を明確にし、重要な情報から表示するデザインを選びましょう。
例えば、スマートフォン表示では、企業のメッセージや主要サービス、問い合わせボタンなど、ユーザーが最も必要とする情報を優先的に表示し、詳細情報は下部に配置するなどの工夫が必要です。
自立型運用への移行ステップ

では、具体的にどのように制作会社依存から自立型運用へ移行すればよいのでしょうか。一朝一夕に全てを内製化することは難しいため、段階的なアプローチが重要です。
現状分析と課題の明確化
まず最初に行うべきは、現在のWebサイト運用状況の棚卸しです。
- 現在のWebサイトの構成と使用しているCMS(コンテンツ管理システム)
- サーバーやドメインの契約状況と管理者
- 更新頻度と更新内容の傾向
- 現在の保守・運用コスト
- 社内のWeb関連スキルを持つ人材の有無
棚卸しをすることで「サーバー契約が制作会社名義になっている」「CMSのログイン情報を持っていない」といった自立運用に向けた課題が見えてきます。
管理権限の移管と基盤の整備
次に、Webサイトの所有権と管理権限を自社に移管する作業を進めます。
- ドメイン契約を自社名義に変更
- サーバー契約を自社名義に変更または新規契約
- CMSの管理者アカウントを取得
- バックアップデータの取得と保管体制の構築
現在の制作会社の協力が必要になる場合があります。契約内容によっては引き継ぎに追加費用が発生することもあるため、事前に確認しておくことが重要です。
特にドメインは企業のブランドそのものであり、他社名義のままだと、契約終了時にWebサイトのURLが使えなくなるリスクがあります。必ず自社名義に変更しましょう。
更新業務の段階的な内製化
管理権限を取得したら、更新業務を段階的に内製化していきます。一度にすべての更新を自社で行おうとすると負担が大きいため、以下のように段階を踏むことをおすすめします。
- テキストや画像の差し替えなど、簡単な更新から始める
- ブログ記事やお知らせなど、定期的なコンテンツ更新に取り組む
- 新しいページの追加やレイアウト変更など、より複雑な作業に挑戦する
この過程で、社内のキーパーソンを育成することが重要です。Webサイト更新の担当者を明確に決め、必要なスキルを習得できるよう支援しましょう。
制作会社との新たな関係構築
自立型運用への移行は、制作会社との関係を完全に断つことではありません。むしろ、より戦略的なパートナーシップを構築することが目的です。
日常的な更新は自社で行いながら、大規模なリニューアルやデザイン変更、技術的に複雑な実装などは、引き続き専門家に依頼するというバランスが理想的です。
制作会社に依頼する際も、「何をどこまで自社で対応し、何を外部に依頼するか」を明確にすることで、必要な部分だけを外注する効率的な体制を構築できます。
CMSを選ぶ際のポイント|自社に最適なシステムの見極め方
CMSを選ぶ際には、自社の目的や運用体制に合ったものを選ぶことが重要です。以下のポイントを考慮して、最適なCMSを選びましょう。
1. 目的と規模に合わせた選択
まずは、Webサイトの目的と規模を明確にしましょう。単なる情報発信が目的なのか、ECサイトを構築したいのか、社内向けのイントラネットが必要なのかによって、最適なCMSは異なります。
- 小規模サイト・ブログ:WordPress、Jimdo、Wixなど
- 中規模コーポレートサイト:WordPress、Movable Type、Drupalなど
- ECサイト:Shopify、WordPress+WooCommerceなど
- 大規模・複雑なサイト:Drupal、Sitecore、Adobe Experience Managerなど
2. 使いやすさと学習コスト
CMSの操作性は、日々の更新作業の効率に直結します。特に、IT専門知識を持たないスタッフが更新作業を行う場合は、直感的に操作できるインターフェースを持つCMSを選ぶことが重要です。
WordPress、Wix、Jimdoなどは初心者にも扱いやすいインターフェースを提供していますが、Drupalなどは高機能な反面、学習コストが高めです。実際に操作してみて、自社のスタッフが使いこなせるかどうかを確認しましょう。
3. カスタマイズ性と拡張性
将来的なWebサイトの成長や機能拡張を見据えて、カスタマイズ性と拡張性も重要な選定ポイントです。
WordPressはプラグインが豊富で拡張性に優れていますが、クラウド型CMSはカスタマイズに制限があることが多いです。自社のWebサイトがどのように成長していくかを想定して、それに対応できるCMSを選びましょう。
4. セキュリティと保守性
Webサイトのセキュリティは非常に重要です。特に、顧客情報を扱うサイトや、ECサイトでは、セキュリティ対策が万全なCMSを選ぶ必要があります。
オープンソース型CMSは自社でセキュリティ対策を行う必要がありますが、クラウド型CMSはプロバイダーがセキュリティ対策を提供してくれることが多いです。また、定期的なアップデートやバックアップの容易さも確認しておきましょう。
5. コストパフォーマンス
初期導入コストだけでなく、運用コストも含めた総合的なコストパフォーマンスを考慮しましょう。
- 初期コスト:システム導入費、デザイン・開発費、トレーニング費用など
- 運用コスト:サーバー費用、保守費用、アップデート費用、拡張機能の追加費用など
無料のオープンソースCMSでも、カスタマイズやセキュリティ対策のために専門家に依頼する場合は費用が発生します。長期的な視点でコストを検討しましょう。
自立運用に最適なCMSの選び方
自立型Webサイト運用の成否を大きく左右するのが、CMSの選択です。適切なCMSを導入することで、専門知識がなくても効率的にサイトを更新・管理できるようになります。
中小企業に適したCMSの条件
CMSを選ぶ際は、以下のポイントを重視しましょう。
- 操作の直感性と学習コストの低さ
- セキュリティ対策の充実度
- 拡張性と将来的な機能追加の可能性
- サポート体制とコミュニティの活発さ
- コストパフォーマンス
特に中小企業の場合、専門的なIT人材が不足していることが多いため、操作の簡便さとサポート体制の充実は重要な選定基準となります。
代表的なCMSとその特徴
現在、多くのCMSが提供されていますが、中小企業の自立運用に適したものをいくつか紹介します。
まず、世界中で最も利用されているCMSの一つが「WordPress」です。無料で利用でき、豊富なテンプレートやプラグインが存在するため、様々なニーズに対応できます。また、情報も豊富で、困ったときに解決策を見つけやすいのも大きなメリットです。
次に「Wix」や「Jimdo」などのクラウド型CMSも、専門知識がなくても直感的に操作できる点で優れています。月額制のサービスですが、サーバー管理やセキュリティ対策も含まれているため、総合的なコストを考えると合理的な選択肢となります。
また、ECサイトを運営する場合は「Shopify」などのEC特化型プラットフォームも検討価値があります。商品管理や決済機能が標準で備わっているため、効率的に運用できます。
いずれのCMSを選ぶ場合も、自社のニーズと運用体制に合ったものを選ぶことが重要です。必要以上に複雑な機能を持つCMSを選ぶと、かえって運用の負担が増える可能性があります。
WordPress活用のポイント
特に中小企業のWebサイト運用では、WordPressが選ばれることが多いため、その活用ポイントを詳しく見ていきましょう。
WordPressの最大の魅力は、基本機能が無料で利用できる点と、豊富なプラグインによる拡張性です。しかし、自由度が高い分、初期設定や運用方法によってはセキュリティリスクが高まる可能性もあります。
WordPress運用のポイントは以下の通りです。
- 定期的なバージョンアップデートを欠かさない
- 必要最小限のプラグインのみを使用する
- 強固なパスワード設定と定期的な変更を行う
- 定期的なバックアップを取得する
- 不要なユーザーアカウントは削除する
これらの基本的なセキュリティ対策を実施することで、WordPressサイトを安全に運用することができます。
また、WordPressの管理画面は比較的直感的ですが、初めて使う方には戸惑う部分もあるでしょう。社内マニュアルを作成したり、操作方法を記録した動画を残したりすることで、担当者が変わっても円滑に引き継げる体制を整えることをお勧めします。
自立運用に必要なスキルと知識
自立型Webサイト運用を実現するためには、社内に一定のスキルと知識を持つ人材が必要です。ただし、プロレベルの専門知識は必ずしも必要ありません。最低限必要なスキルと、それを効率的に習得する方法を見ていきましょう。
最低限必要なWebの基礎知識
Webサイトを自立運用するために、最低限理解しておきたい基礎知識は以下の通りです。
- ドメインとサーバーの基本的な仕組み
- HTMLとCSSの基本的な構造
- 画像ファイルの種類と最適化方法
- SEO(検索エンジン最適化)の基本原則
- Webサイトのセキュリティ対策の基礎
これらの知識は、専門的な開発スキルがなくても、基本的な学習で身につけることができます。例えば、HTMLやCSSについては、タグの意味や基本的な構造を理解するレベルで十分です。
重要なのは、これらの知識を「使いこなす」ことではなく、「理解している」ことです。理解していれば、問題が発生した際に何が起きているのかを把握し、適切な対応ができるようになります。
効率的なスキルアップ方法
Webに関するスキルを効率的に習得するためには、以下のようなアプローチが有効です。
まず、オンライン学習プラットフォームの活用です。Udemyやプログラミングスクールのオンラインコースなど、初心者向けのWeb講座が多数提供されています。特にCMS操作に特化したコースを選ぶと、実務に直結するスキルを効率的に習得できます。
次に、実践を通じた学習です。実際のWebサイト更新作業を通じて学ぶことで、知識が定着しやすくなります。最初は簡単な更新作業から始め、徐々に複雑な作業にチャレンジしていくことで、自然とスキルが向上していきます。
また、コミュニティへの参加も効果的です。WordPressなどのCMSには、ユーザーコミュニティが存在します。こうしたコミュニティに参加することで、疑問点を解決したり、最新の情報を得たりすることができます。
社内の知識共有と継続学習の仕組み
Webサイト運用のスキルと知識は、特定の担当者だけが持っているのではなく、組織として共有・蓄積していくことが重要です。そのための仕組みづくりを考えましょう。
まず、操作マニュアルやナレッジベースの整備です。Webサイト更新の手順や注意点、トラブル対応方法などを文書化し、社内で共有できる状態にしておきます。特に頻繁に行う作業については、手順を詳細に記録しておくと良いでしょう。
次に、複数担当者制の導入です。Webサイト更新の担当者を複数名設定することで、知識の偏りを防ぎ、担当者の不在時にも対応できる体制を整えられます。
また、定期的な勉強会や情報共有の場を設けることも効果的です。Web技術は日々進化しているため、継続的な学習と情報のアップデートが欠かせません。外部セミナーへの参加や、新しい知識を得た際の社内共有の仕組みを整えましょう。
自立運用成功のための共通ポイント
様々な事例から見えてくる、自立型Webサイト運用成功のための共通ポイントは以下の通りです。
- 明確な役割分担と責任者の設定
- 段階的な移行プロセスの設計
- 基本的なセキュリティ対策の徹底
- 定期的なバックアップの取得
- 操作マニュアルの整備と知識の共有
- 継続的な学習と情報のアップデート
特に重要なのは「人」の要素です。Webサイト運用に前向きに取り組める担当者を選定し、その成長をサポートする体制を整えることが、自立運用成功の鍵となります。
また、完全に内製化することが目的ではなく、「自社でコントロールできる部分を増やす」という視点で取り組むことが重要です。専門性の高い部分は引き続き外部の力を借りながら、日常的な運用は自社で行うというバランスが理想的です。
自立運用を支える体制づくり

自立型Webサイト運用を長期的に維持するためには、適切な体制づくりが欠かせません。一時的に移行できても、その後の運用が続かなければ意味がありません。持続可能な運用体制を構築するためのポイントを見ていきましょう。
理想的な運用体制と役割分担
自立型Webサイト運用の理想的な体制は、以下のような役割分担で構成されます。
- Webサイト責任者:全体の方針決定と進捗管理
- コンテンツ担当:記事や画像などのコンテンツ作成・更新
- 技術担当:CMSの操作やトラブル対応
- 監視担当:セキュリティチェックやバックアップ管理
中小企業では一人が複数の役割を兼務することも多いですが、それぞれの責任範囲を明確にしておくことが重要です。特に「誰が最終的な責任を持つのか」を明確にしないと、問題が発生した際に対応が遅れる原因となります。
また、担当者だけでなく経営層の理解と支援も不可欠です。Webサイトは企業の重要な資産であり、その運用は経営課題の一つとして位置づけるべきです。定期的に経営層への報告や相談の機会を設けることで、必要なリソースの確保や意思決定がスムーズになります。
運用ルールとガイドラインの整備
効率的かつ安全な運用のためには、明確なルールとガイドラインが必要です。以下のような項目を文書化しておきましょう。
- 更新手順と承認フロー
- コンテンツの品質基準
- セキュリティ対策のチェックリスト
- トラブル発生時の対応手順
- 外部委託する範囲と判断基準
特に複数の担当者がいる場合は、統一された基準で運用するためのガイドラインが重要です。例えば、画像のサイズや形式、文章のトーンや表現方法など、細かい部分まで統一しておくことで、サイト全体の一貫性を保つことができます。
また、定期的なメンテナンスのスケジュールも明確にしておきましょう。CMSのアップデートやプラグインの更新、セキュリティチェックなど、定期的に行うべき作業を計画的に実施することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
持続可能な運用のための工夫
自立運用を長期的に維持するためには、担当者の負担を軽減し、モチベーションを維持する工夫が必要です。
まず、作業の自動化を検討しましょう。例えば、バックアップの自動化やセキュリティスキャンの定期実行など、技術的に自動化できる部分は積極的に取り入れることで、担当者の負担を減らすことができます。
次に、更新作業を日常業務に組み込む工夫です。特定のタイミングや曜日を決めて定期的に更新する習慣をつけることで、「特別な作業」ではなく「日常の一部」として定着させることができます。
また、成果の可視化も重要です。アクセス解析ツールを活用して、Webサイトの効果を数値で示すことで、運用担当者のモチベーション維持につながります。「更新したページへのアクセスが増えた」「問い合わせが増加した」といった成果を共有することで、作業の意義を実感できるようになります。
さらに、外部の力を適切に活用することも検討しましょう。全てを内製化するのではなく、専門性の高い部分や一時的に負荷が高まる作業については、外部リソースを活用するハイブリッド型の運用も効果的です。
BaseTreeのWebサイト制作アプローチ
BaseTreeでは、Webサイトを単なる情報発信ツールではなく、営業・採用・教育・承継に活用できる「情報資産」として位置づけています。その特徴的なアプローチをご紹介します。
1. 構造と言語の設計
BaseTreeのWebサイト制作の特徴は、「理念・構造・価値を言語と設計で伝える」ことに重点を置いている点です。単にデザイン的に美しいサイトを作るのではなく、組織として価値を正しく伝える情報構造を設計します。
これにより、誰が読んでも・誰が案内しても価値が伝わるWebサイトの構築を目指しています。結果として、「結局何をしている会社か分からない」「採用後に思っていたのと違うと言われる」といった問題を解決します。
2. 7ステップの制作プロセス
BaseTreeでは、Webサイト制作を7つのステップで構成しています:
- 事業理解:情報整理、経営者・事業責任者へのヒアリング、現場視点の収集、既存データ分析
- 顧客理解:ペルソナ再定義、カスタマージャーニー構築、事例分析
- 競合理解:競合サイト調査、差別化要素抽出、独自コンテンツ設計
- 情報設計・コンテンツ構成:サイトマップ設計、情報設計、導線設計
- UI設計・ビジュアル設計:ワイヤーフレーム作成、デザインコンセプト策定、モックアップ制作
- コーディング・CMS実装:WordPress導入、SEO対策、セキュリティ設定
- テスト・公開・運用:動作確認、更新マニュアル作成、修正対応
このプロセスにより、単なるWebサイト制作ではなく、経営の言語を構造として定義するところから始まる、成果と活用に直結するWebサイトを構築します。
3. CMS設計と保守体制
BaseTreeでは、WordPress等のCMSを用いた設計と保守・改善まで含む支援で、継続した社内更新で成果を高め続けられる仕組みを提供しています。
Webサイトは公開して終わりではなく、活用し改善し続ける仕組みが重要です。そのため、以下のような保守・管理体制を提供しています:
- CMS管理・アップデート:WordPress本体・プラグインの定期更新、脆弱性の検知とパッチ適用
- セキュリティ対策:二要素認証、ログイン試行制限の導入、不審アクセスの監視
- データバックアップと復旧体制:毎日・週次の自動バックアップ、障害発生時の復旧対応
- 改善支援・アクセス解析:GA4、Search Consoleの設定・分析サポート、改善提案
これらの体制により、Webサイトを「生きた営業・広報装置」として運用可能にします。
制作会社に依存しない自立型Webサイト運用の実現に向けて
本記事では、制作会社に依存しない自立型Webサイト運用の重要性とその実現方法について解説してきました。最後に、ポイントを整理しておきましょう。
自立運用がもたらす本質的なメリット
制作会社依存からの脱却は、単なるコスト削減策ではありません。それによってもたらされる本質的なメリットは以下の通りです。
- 情報発信の即時性と柔軟性の向上
- Webサイトを「使える資産」として最大限活用できる
- 社内のデジタルリテラシー向上とDX推進の基盤構築
- 外部環境の変化に左右されない安定した運用体制の確立
特に重要なのは、Webサイトを「他社に任せている広告媒体」から「自社でコントロールできる経営資源」へと位置づけを変えることです。これにより、営業・採用・教育・承継など様々な場面でWebサイトを戦略的に活用できるようになります。
段階的アプローチの重要性
自立運用への移行は、一朝一夕に実現するものではありません。段階的なアプローチが成功の鍵となります。
- 現状分析と課題の明確化
- 管理権限の移管と基盤の整備
- 更新業務の段階的な内製化
- 運用体制の構築と定着
特に初期段階では、制作会社と協力しながら移行を進めることが重要です。敵対的な関係ではなく、新たなパートナーシップの形を模索することで、スムーズな移行が可能になります。
持続可能な自立運用のために
自立運用を持続可能なものにするためには、以下の点に注意しましょう。
- 明確な役割分担と責任の所在
- 定期的なスキルアップと知識の更新
- 運用ルールとガイドラインの整備
- セキュリティ対策とバックアップの徹底
- 成果の可視化とモチベーション維持
完全な内製化が目的ではなく、「自社でコントロールできる範囲を広げる」という視点で取り組むことが大切です。専門性の高い領域は外部の力を借りながら、日常的な運用は自社で行うというバランスが、多くの企業にとって現実的な選択肢となるでしょう。
Webサイトは、単なる情報発信ツールではなく、企業の価値を伝え、ビジネスを成長させるための重要な「情報資産」です。適切なCMSとレスポンシブ対応を選び、戦略的に設計・運用することで、ビジネスの成長を加速させる強力なツールになります。
まずはWebサイトを自社の手に取り戻し、「情報資産」を自立運用・管理されるところからスタートしてみてはいかがでしょうか?
Webサイトでお悩みの方は、ぜひBaseTreeにご相談ください。
Webサイト制作についての詳細はこちらからご確認いただけます。