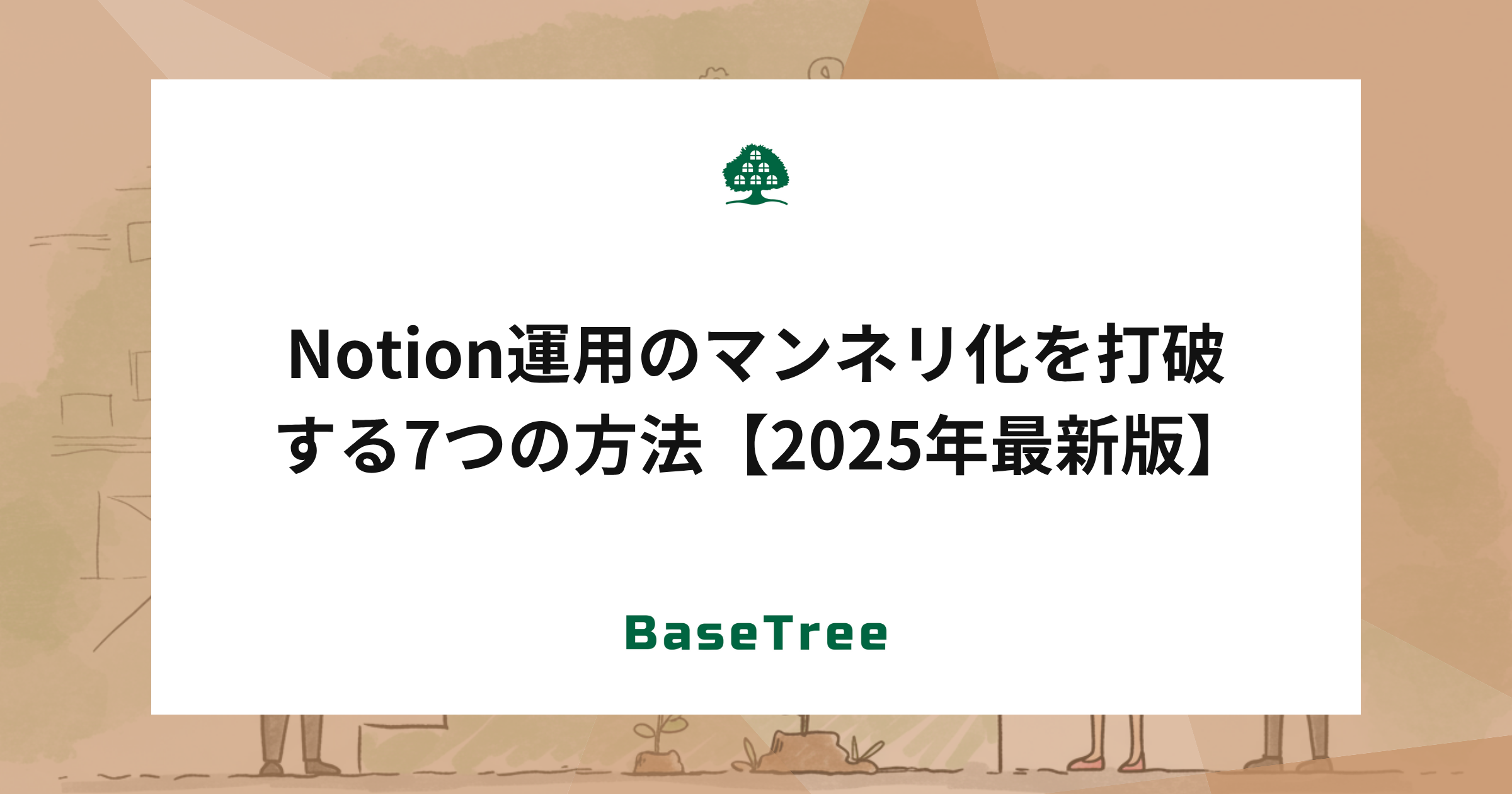Notionのマンネリ化とは?なぜ起こるのか
「最初は楽しく使っていたNotionなのに、いつの間にか更新が滞りがちに…」
Notionは柔軟性の高いオールインワンツールとして人気を集めていますが、導入して数か月経つと次第に使用頻度が下がり、情報が更新されなくなる「マンネリ化」が起きがちです。
せっかく構築したワークスペースが形骸化してしまうのは非常にもったいない。
Notionのマンネリ化が起こる主な原因は、初期設計の複雑さ、日々の運用負担、新機能への対応遅れなど複数あります。特に組織利用では、担当者の異動や業務多忙により更新が滞りやすく、結果として「誰も見なくなる」という悪循環に陥ることも。
今回は2025年最新の情報をもとに、Notion運用のマンネリ化を打破する7つの効果的な方法をご紹介します。
適切な運用方法を知ることで、Notionをより長くより効果的に活用できるようになります。
方法1 定期的な構造の見直しと最適化
Notionのマンネリ化を防ぐ第一歩は、定期的な構造の見直しです。
肥大化したワークスペースは検索性や視認性が低下し、次第に使われなくなっていきます。
半年ごとにワークスペース全体を評価し使われていないページや機能を整理することでNotionの使い勝手が格段に向上します。
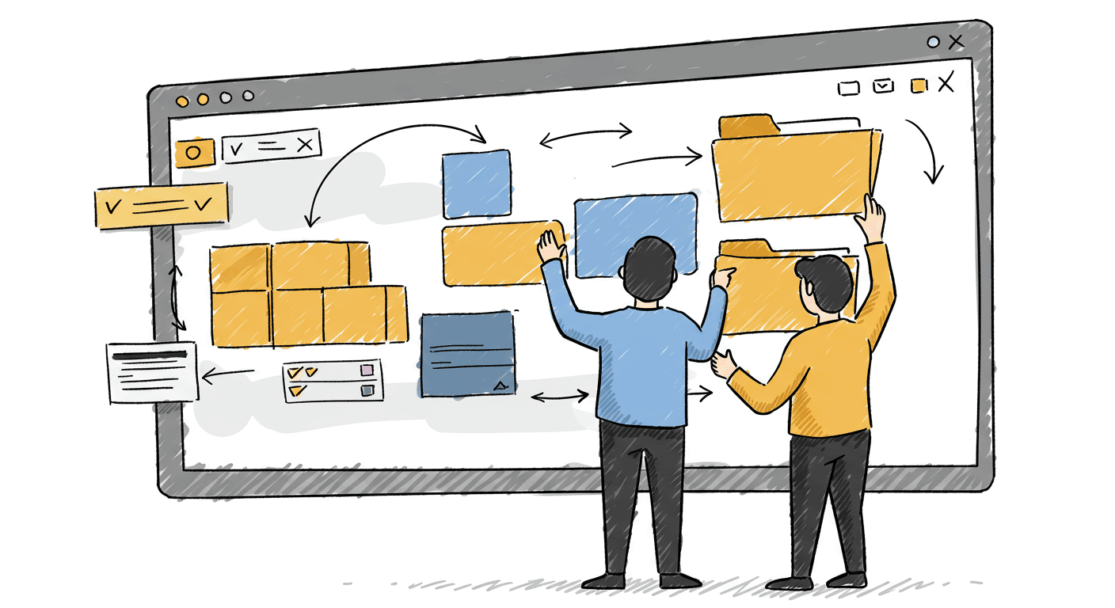
私が実際に行っている見直し方法をご紹介します。
まず、「最近3ヶ月間で一度も開いていないページ」をリストアップします。
次に、それらのページを「アーカイブする」「削除する」「リニューアル(更新)する」のいずれかに振り分けます。
このシンプルな作業だけでも、ワークスペースの見通しが劇的に改善されます。
2025年のNotionでは、利用状況を評価する機能も強化されています。
「最終アクセス日」や「編集頻度」などの指標を活用して、客観的にページの利用状況を把握できるようになりました。
これらのデータを参考にしながら業務フローに合わせた最適化を行いましょう。
未使用ページの整理だけでなく、頻繁に使うページへのアクセス性を高めることも重要です。
サイドバーのお気に入り機能やショートカットを活用して、日常的に使うページへのアクセスを時短しましょう。
自分のワークスペースに眠っている「デッドスペース」はありませんか?
方法2 新機能の積極的な学習と導入
Notionは常に進化し続けるツールです。
2025年に入ってからも数多くの新機能がリリースされています。
マンネリ化を防ぐ効果的な方法の一つが、新機能の積極的な学習と導入です。
新しい機能を取り入れることで、Notionの使い方に新鮮さが生まれ、モチベーションの維持につながります。
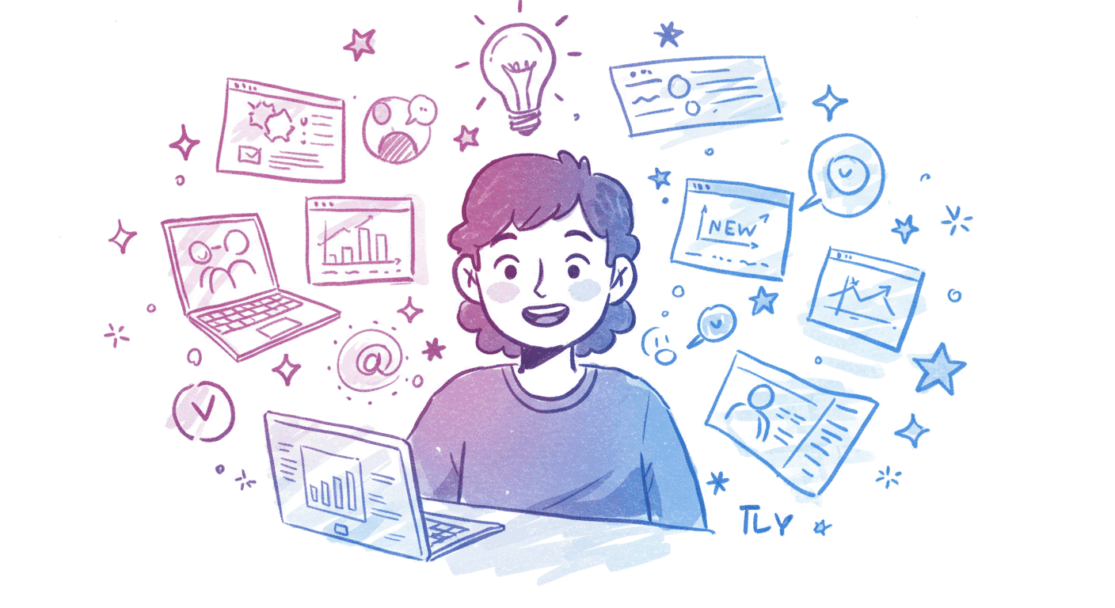
2025年前半の注目すべき新機能は、AIアシスタント機能の強化、カレンダービューの改善、データベース間の連携強化です。
特にNotion AIは、文章作成やデータ分析、情報整理などの作業を大幅に効率化してくれる便利なツールです。
新機能を学ぶ際のコツは一度に全てを取り入れようとせず、業務に直接役立ちそうな機能から段階的に導入していくこと。
例えば週に1つずつ新機能を試してみて、有用だと感じたものだけを本格的に活用するという方法。
チーム内で新機能の学習会を定期的に開催するのも良い方法です。
お互いの発見や活用法を共有することでチーム全体のNotionスキルが向上し、より創造的で自社にマッチした使い方が生まれやすくなります。
あなたは最近、どんなNotion新機能を試してみましたか?
方法3 業務改善アイデアの収集と実装
Notionの運用がマンネリ化する大きな原因の一つは「現状維持バイアス」。
一度構築したワークスペースを変更することに抵抗を感じ改善の機会を逃してしまうこと。
この状況を打破するには定期的に業務改善アイデアを収集し、Notionに反映させる仕組みが効果的です。
実際の業務フローに合わせてNotionを進化させることで、ツールの有用性が高まり、自然と利用頻度も上がります。
BaseTreeのNotionサービスでは「業務改善アイデア収集&共有」を重要な取組として位置づけています。
単なるツールの技術的サポートではなく、組織の業務そのものを改善するために使っていただきたいからです。
具体的な実践方法としては、まず、Notion内に「改善提案ボックス」を設置します。
シンプルなデータベースで、誰でも気軽に「こうしたら便利になるのに」というアイデアを投稿できる場所です。
投稿されたアイデアは定期的にレビューし、実装可能なものから順に取り入れていきます。
支援する中で「目安箱」とか「意見書」、「カイゼンBOX」などと各組織に合わせて呼称を決めていただいています。
次に、月に一度の「Notion改善デー」を設定するのも効果的です。
この日は通常業務の合間に少し時間を取り、みんなでNotionの使い方を見直したり、新しいテンプレートを作成したりする日とします。
Notionを扱うスキルの差異や、役職の垣根を超えて、「どうしたらもっと使いやすくなるか?」「何がめんどくさいか?」など楽しみながら改善できる雰囲気づくりが大切です。
さらに、他部署や他社の優れたNotion活用事例を積極的に収集し、自社の環境に合わせてカスタマイズするのも有効です。「Notionギャラリー」などのサービスでは、様々な業種・業態のテンプレートが公開されており、これらを参考にすることで新たな発想が生まれやすくなります。
業務改善のアイデアを形にする過程そのものが、Notionの新たな使い方を発見する機会になります。
チーム全員が「より良くしたい」という意識を持ち、小さな改善を積み重ねていくことが、マンネリ化防止にとって重要です。
方法4 チーム全体のスキルアップ支援
Notionの運用がマンネリ化する原因の一つに「スキルの偏り」があります。
一部の熟練者だけが高度な機能を使いこなし他のメンバーは基本的な使い方しかできないという状況です。
この問題を解決するにはチーム全体のNotionスキルを底上げする取り組みが効果的です。
全員のスキルが向上すれば、より創造的な使い方が生まれ、Notionの可能性が広がります。
「Notionで何ができるのかわからない、どこまでできるのかわからない」と、改善点も見出せなければ、意見も発せない。
当たり前のように思えますが、この「わからないの放置」が見落としがちな要素です。
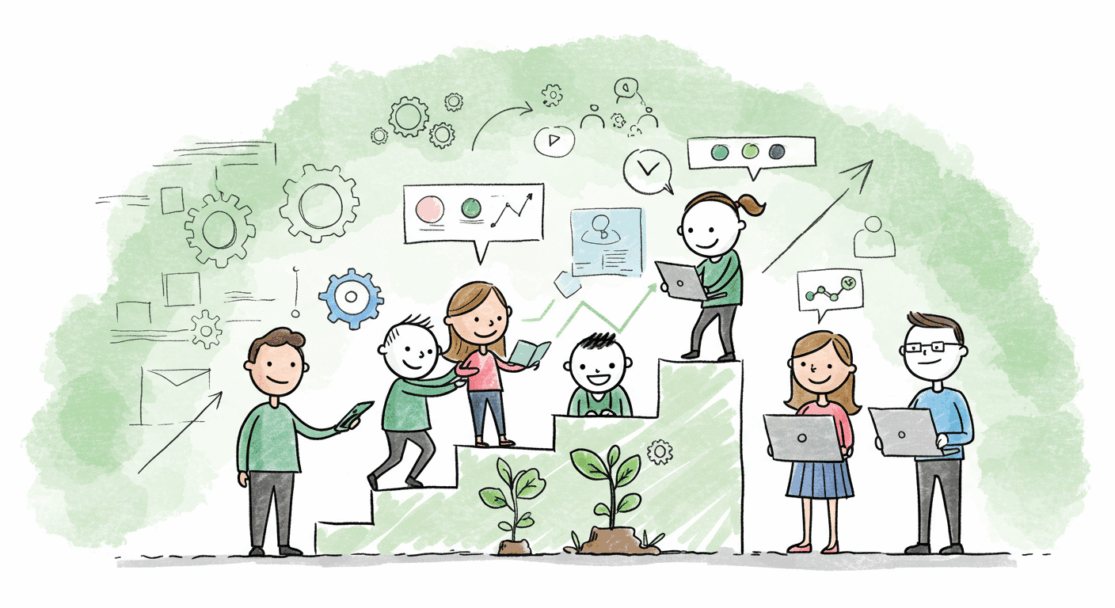
BaseTreeのNotion運用支援サービスでは「チーム全体のNotionスキル向上」を重要なポイントと捉えています。
単に個々のスキルを上げるだけでなく、組織全体のナレッジマネジメント能力を高めるための取り組みです。
スキルアップ支援の具体的な方法としては、まず「Notionスキルマップ」を作成し、チームメンバーそれぞれの得意分野と学習したい分野を可視化します。
社内で教えられるメンバーがいれば先生になっていただきレクチャーする、互いに教え合える環境が生まれチーム全体のスキル向上が加速します。
次に、「Notionテクニック共有会」を定期的に開催するのも効果的です。
15分程度の短い時間でも構いません。
各メンバーが発見した便利な使い方やショートカットを共有する場を設けることで、全員のスキルが徐々に向上していきます。
「お気に入りの順序をドラッグ&ドロップで並び替えられる」、なんて共有もありました。
一見地味で些細なハックですが、全員が知り、できるようになれば、何時間効率化できるでしょう?
さらに「Notion活用術ドキュメント」を作成し、チーム内で共有するのも有効です。
基本的な操作方法から応用テクニックまで実際の業務に即した形でまとめておくことで、新メンバーの教育コストも削減できます。
2025年現在、Notionの機能は非常に多岐にわたっています。
全ての機能を全員が完璧に使いこなす必要はありませんが、基本的な機能と自分の業務に関連する機能については、一定レベル以上のスキルを身につけましょう。
チーム内でNotionのスキルを高め合う文化を育てることが、マンネリ化防止と持続的な活用に繋がります。
あなたのチームでは、どのようなスキルアップ支援を行っていますか?
方法5 ワークスペースの視覚的リニューアル
Notionの運用がマンネリ化する意外な原因の一つが「視覚的な飽き」です。
毎日同じ見た目のワークスペースを見続けることで次第に新鮮さが失われ、更新するモチベーションも低下していきます。
この問題を解決するには定期的なビジュアルリニューアルが効果的です。
見た目を変えるだけでも使う側の気持ちが新たになり、活用意欲が高まります。
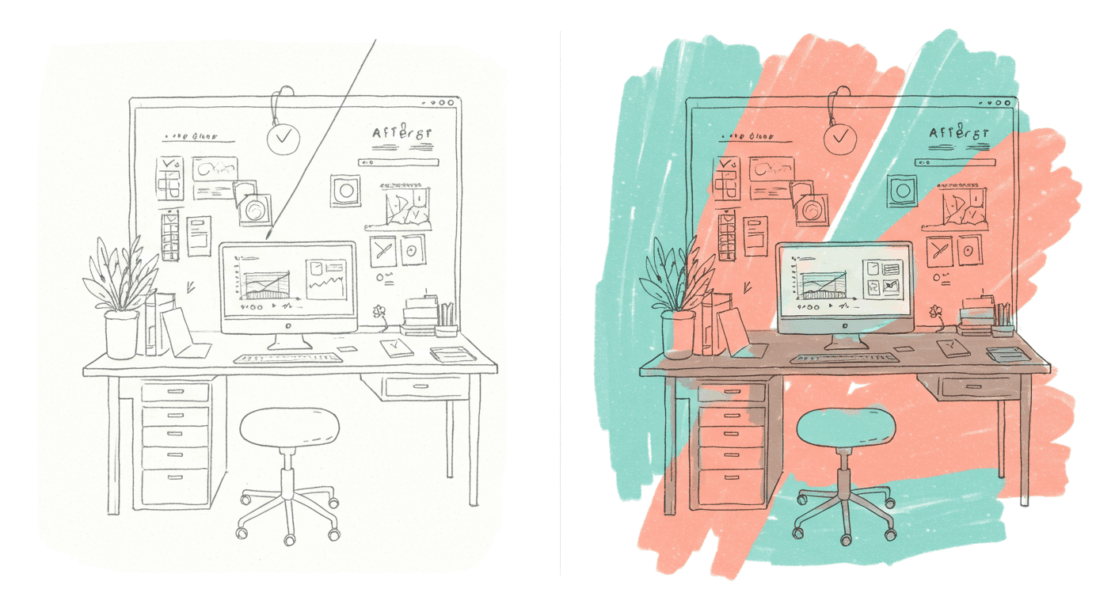
2025年のNotionでは、カスタマイズ機能がさらに充実し、より自由度の高いデザインが可能になっています。
これらの機能を活用して、季節ごとや四半期ごとにワークスペースの見た目を刷新してみましょう。
視覚的リニューアルの具体的な方法としては、まずカバー画像やアイコンを定期的に変更します。
プロジェクトの進捗状況や季節感を反映した画像に更新するだけでも、ワークスペース全体の印象が大きく変わります。
Notionの公式ギャラリーには高品質な画像が多数用意されていますので、それらを活用するのも良いでしょう。
次にカラーテーマを変更してみます。
2025年のNotionではカスタムカラーテーマ機能が強化され、より細かな色調整が可能になっています。
チームのブランドカラーに合わせたりプロジェクトの性質に合わせた色調を設定したりすることで、視覚的な一貫性と新鮮さの両方を実現できます。
さらに、レイアウトの見直しも効果的です。
同じ情報でも表示方法を変えるだけで見え方が大きく変わります。
例えばリスト表示からギャラリー表示、カレンダー表示、カンバン表示などに切り替えてみると、新たな気づきが得られることもあります。
一度に全てを変更する必要はありません。
小さな変化を定期的に加えていくことで「いつの間にか全く違うワークスペースになっていた」という状態を目指しましょう。
視覚的な刷新は単なる見た目の問題ではなく、情報の整理方法や思考のプロセスにも影響を与えます。
新しい見え方が新しいアイデアや働き方を生み出すきっかけになるのです。
方法6 自動化機能の活用拡大
Notionの運用がマンネリ化する大きな原因の一つは「日常的な更新作業の負担」です。
手動での情報更新やタスク管理が続くと次第に面倒に感じられ、更新頻度が落ちていきます。
この問題を解決するには自動化機能を積極的に活用することが効果的です。
繰り返し行う作業を自動化することで運用負担を軽減し、より創造的な活用に時間を使えるようになります。
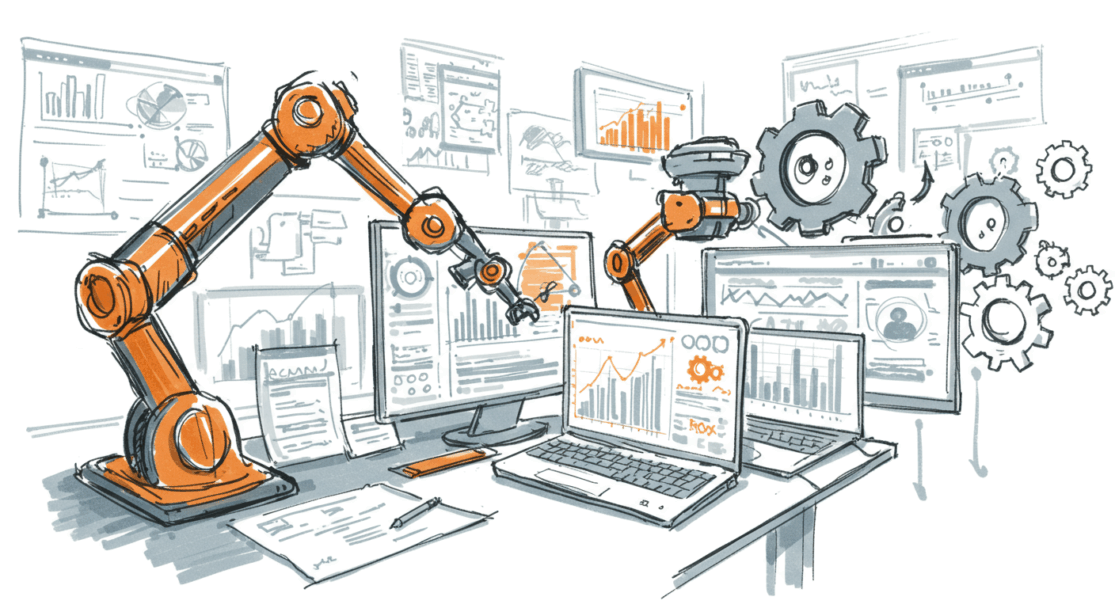
2025年のNotionでは、自動化機能がさらに強化され、より複雑なワークフローの自動化が可能になっています。
特に「繰り返し」機能と外部サービスとの連携機能は、日常的な運用負担を大幅に軽減してくれます。
自動化の具体的な活用方法としては、まず定期的なタスクの自動生成を設定します。
例えば「毎週月曜日にチームミーティングの議事録ページを作成する」「毎月1日に月次レポートのテンプレートを準備する」といった繰り返し作業を自動化することで準備の手間を省けます。
次に、データベース間の連携を自動化します。
例えば「プロジェクトデータベース」に新しい案件が追加されたら、自動的に「タスクデータベース」に関連タスクが生成されるといった連携を設定できます。
情報の一貫性が保たれ二重管理の手間も省けます。
さらに、外部サービスとの連携も効果的です。
SlackやGoogle Calendar、Emailなどと連携することで、情報の流れをスムーズにし、Notionへの情報集約を自動化できます。
例えば特定のSlackチャンネルに投稿された重要メッセージを自動的にNotionのデータベースに保存する、といった連携が可能です。
自動化を検討する際のコツは、「頻度が高く、パターン化できる作業」から始めること。
毎日・毎週行っている定型作業を洗い出し、それらを一つずつ自動化していくことで大きな効果を実感できます。
自動化によって生まれた時間をより創造的な活用や戦略的な改善に充てることで、Notionの価値をさらに高めることができるでしょう。
方法7 外部専門家によるレビューと最適化
Notionの運用がマンネリ化する根本的な原因の一つは「内部視点の限界」です。
同じメンバーで長期間運用していると既存の枠組みや使い方に縛られ、新たな可能性に気づきにくくなります。
この問題を解決するには外部の専門家による定期的なレビューと最適化が非常に効果的です。
客観的な視点からの指摘や提案により自分たちだけでは気づけなかった改善点が明らかになります。
BaseTreeのNotion運用支援サービスでは「半年ごとに構造の見直しを実施」することを重要なサポート内容として位置づけています。
単なる技術的なチェックではなく、業務フローや組織の変化に合わせた最適化を専門家の視点から行うものです。
外部専門家によるレビューと最適化の具体的なメリットは、まず客観的な視点から評価すること。
日々の運用に慣れてしまうと見落としがちな非効率な部分や改善点を、専門家は外部だからこそ冷静に指摘できます。
「当たり前」と思っていた運用方法に、実は大きな改善の余地があることも少なくありません。
次に、最新のベストプラクティスを取り入れられます。
Notion専門家は様々な企業や組織の導入・運用事例を知っているため、業界や用途に応じた最適な活用方法を提案してくれます。他社の成功事例を自社の環境に合わせてカスタマイズすることで、短期間で大きな改善が可能になります。
さらに、チームのスキルアップにもつながります。
専門家によるレビューの過程で、チームメンバーは新たな機能や使い方を学ぶことができます。
単発の研修よりも実践的で、実際の業務に即したスキルアップが可能です。
2025年現在、Notionの機能は非常に多岐にわたり、すべてを把握して最適に活用することは容易ではありません。
専門家のサポートを受けることで、自社の状況に最適な機能だけを効果的に取り入れることができます。
外部の視点を定期的に取り入れることでマンネリ化を防ぎNotionの可能性を最大限に引き出す。
IT化や業務効率化のための、地味ですが重要な投資と言えるのではないでしょうか。
Notion運用のマンネリ化打破で得られる4つのメリット
ここまで7つの方法をご紹介してきましたが、実践することで具体的にどのようなメリットが得られるでしょうか。
Notion運用のマンネリ化を打破することで得られる主な効果を4つご紹介します。
1. 業務効率の継続的な向上
マンネリ化を防ぎ常に最適な状態でNotionを運用することで、業務効率が継続的に向上します。
情報の検索性が高まり必要な情報にすぐにアクセスできるようになるため、日々の業務がスムーズに進みます。
BaseTreeのNotion運用支援サービスでは「業務改善につながるアイデア創出」を促進します。
Notionの運用改善は単なるツールの問題ではなく、業務プロセス全体の最適化につながるからです。
2. 最新機能による競争優位性の確保
Notionは常に新機能を追加しており、積極的に取り入れることで競争優位性を確保できます。
2025年に強化されたAI機能やデータ分析機能などを活用することで、他社よりも一歩先を行く業務改善が可能になります。
BaseTreeのNotionサービスでは、「Notionの最新機能を常に活用できる環境の維持」を重要なメリットとして位置づけています。技術の進化に遅れることなく、常に最先端の機能を業務に取り入れることができます。
3. 組織知の効果的な蓄積と活用
マンネリ化を防いで活発にNotionを運用することで、組織内の知識やノウハウが効果的に蓄積・共有されます。
過去の成功事例や失敗から学んだ教訓が適切に記録され、新しいメンバーも含めてチーム全体の知識レベルが向上します。
特に2025年の組織環境では、リモートワークやハイブリッドワークが一般的になっており、物理的な距離を超えた知識共有の重要性がさらに高まっています。
Notionを効果的に運用することで、場所や時間を問わず必要な情報にアクセスできる環境を整えることができます。
4. チームの創造性と協働性の向上
Notionの運用を活性化することで、チームの創造性と協働性も向上します。
使いやすく整理されたワークスペースではアイデアの共有や協力が促進され、より革新的なプロジェクトが生まれやすくなります。
また、全員がNotionを積極的に活用することで、情報の透明性が高まり、チーム内のコミュニケーションも円滑になります。
特に新しいメンバーの受け入れやリモートワーク環境において大きなメリットとなります。
これらのメリットは単発的な改善ではなく、継続的な取り組みによって初めて実現するものです。
7つの方法を組み合わせて実践しNotionの可能性を最大限に引き出していきましょう!
Notion運用のマンネリ化打破で組織力を向上させよう
Notionは非常に柔軟で強力なツールですが、その可能性を最大限に引き出し続けるには、マンネリ化を防ぐ継続的な取り組みが欠かせません。
今回ご紹介した7つの方法を実践いただくことでNotionを長期にわたって効果的に活用し、組織の生産性と創造性を高めることができます。
まず定期的な構造の見直しと最適化を行い、ワークスペースを常に整理された状態に保ちましょう。
次に新機能の積極的な学習と導入で、Notionの可能性を広げていきます。
業務改善アイデアの収集と実装により実際の業務フローに合わせた進化を促し、チーム全体のスキルアップ支援で全員がNotionを使いこなせる環境を整えましょう。
さらにワークスペースの視覚的リニューアルで新鮮さを保ち、自動化機能の活用拡大で運用負担を軽減します。
そして外部専門家によるレビューと最適化で、客観的な視点から継続的な改善を図りましょう。
これらの取り組みにより、業務効率の継続的な向上、最新機能による競争優位性の確保、組織知の効果的な蓄積と活用、チームの創造性と協働性の向上といった大きなメリットを得ることができます。
2025年の組織環境において、効果的な情報管理と知識共有はますます重要になっています。
Notionを単なるツールではなく、組織の成長と進化を支える基盤として位置づけ、継続的に改善していくことが、長期的な成功への鍵となるでしょう。
Notion運用でお悩みの方は、専門家のサポートを受けることも検討してみてください。
BaseTreeのNotion運用支援サービスでは、バージョンアップ支援、改善・最適化、スキル・ノウハウ共有など、包括的なサポートを提供しています。
詳細はNotion運用支援をご覧ください。
Notionの可能性は無限大です。
マンネリ化を打破し、Notionをさらに進化させ、貴社に眠る可能性を最大限に引き出していきましょう。