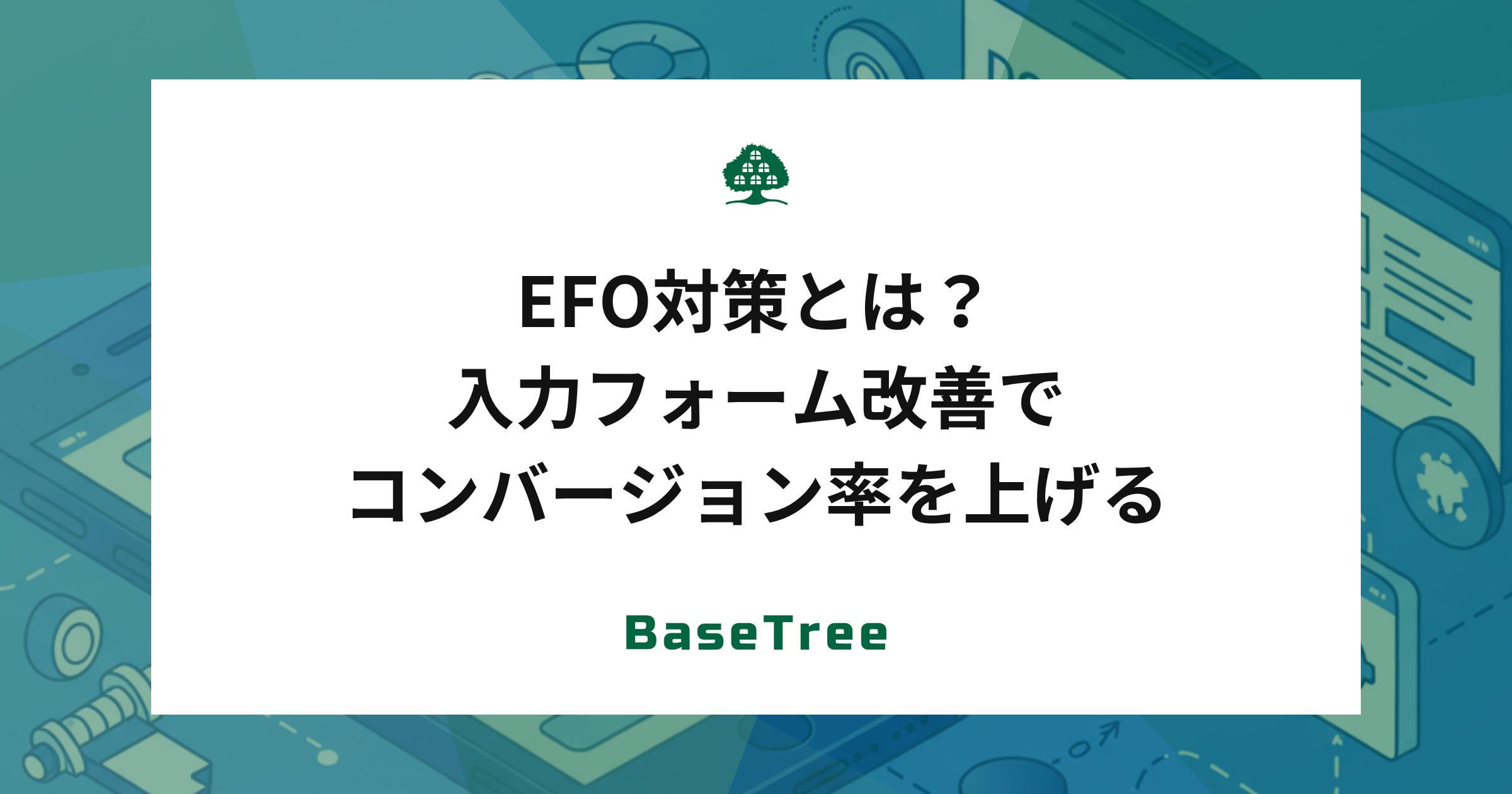EFO対策とは、入力フォーム最適化
EFOとは「Entry Form Optimization(入力フォーム最適化)」の略称で、Webサイト上の入力フォームを改善し、ユーザーがスムーズに情報を入力できるようにするプロセスを指します。
入力フォームでの離脱率は最大70%にも達するといわれています。
サービスに興味を持っていても、フォームが使いにくいとユーザーは途中で離脱してしまいコンバージョンに繋がりません。
EFO対策はフォーム入力のストレスを軽減し、コンバージョン率(CVR)向上を目的とする施策です。
EFOは内部SEO対策の一貫
EFOは一見するとSEOとは無関係に思えるかもしれません。
実はSEO、特に内部SEO対策として重要な役割を果たします。
内部SEO対策とはサイト内部の構造や要素を最適化して検索エンジンからの評価を高める施策。
タイトルタグや見出しの最適化やサイト構造の改善などが含まれますが、EFOもその一環です。
なぜEFOが内部SEO対策として重要なのか。その理由は以下の3点に集約されます。
- ユーザー体験(UX)の向上
Googleのアルゴリズムはユーザー体験を重視しており、使いやすいフォームはUXの向上に直結します - 滞在時間・直帰率の改善
フォームが最適化されていると、ユーザーの滞在時間が長くなり直帰率が下がります - コンバージョン率の向上
最終的なゴールであるコンバージョンが増えることで、サイト全体の評価が高まります
つまり、EFO対策はSEO対策の一部で、ユーザーが最後に目にする重要なページです。
なぜフォームで離脱が起きるのか?
入力フォームで離脱が起きる原因は何か?途中で入力を諦めてしまう主な理由を見ていきましょう。
入力項目や入力ステップが多すぎる
フォームの入力項目数は、離脱率と直接的な相関関係があります。必要以上に多くの情報を求めると、「面倒くさい」と感じて離脱してしまいます。
特にスマートフォンでの入力はPCと比べ手間がかかるため、項目数の多さはより深刻な問題です。実際に入力項目を減らすだけでコンバージョン率が5%以上改善したケースもあります。
全角・半角の指定がわかりづらく面倒
日本特有の問題として、全角・半角の区別があります。
「メールアドレスは半角で入力してください」「お名前は全角で入力してください」といった指示が明確でないと、エラーが発生しユーザーのストレスになります。
さらに入力途中でエラーが表示されず、送信ボタンを押した後にまとめてエラーが表示されると、修正作業が煩わしくなります。
どこでエラーになっているのかわからない
エラーメッセージが不明確だったり、エラー箇所がわかりにくかったりすると、ユーザーは何を修正すればいいのかわからず、イライラして離脱してしまいます。
「入力内容に誤りがあります」といった抽象的なメッセージではなく、具体的にどの項目に問題があるのかを明示することが重要です。
EFO対策の具体的な改善施策
フォームの使いやすさを向上させ、コンバージョン率の改善が期待できる具体的なEFO対策を見ていきましょう。

1. 入力項目をできるだけ減らす
最も効果的なEFO対策は、入力項目を必要最小限に絞ること。
各項目が「本当に必要か?」を厳しく問い直しましょう。
例えば、資料請求の段階で住所や電話番号まで聞く必要があるでしょうか?メールアドレスだけで十分なケースも多いはずです。
不要な項目を削除するだけでコンバージョン率が大きく改善することがあります。
2. 入力エラーを早めに気づかせる
入力中にリアルタイムでエラーをチェックし、問題があればすぐに通知する仕組みを導入しましょう。送信ボタンを押した後にまとめてエラーを表示するのではなく、各項目の入力が完了した時点でバリデーションを行います。
例えば、メールアドレスの形式が正しくない場合は、次の項目に移る前に通知することで、ユーザーはすぐに修正できます。
3. 入力例を表示する
各入力欄にプレースホルダーとして入力例を表示することで、ユーザーは何をどのように入力すべきかが一目でわかります。
特に日付や電話番号など、フォーマットが重要な項目では、「例:2025年8月1日」「例:03-1234-5678」のように具体的な例を示すことが効果的です。
4. 住所やメールアドレス入力を助ける補助機能をつける
郵便番号から住所を自動入力する機能や、メールアドレスのドメイン候補を表示する機能など、入力を支援する仕組みを導入しましょう。
特に住所入力は手間がかかるため、郵便番号からの自動入力機能は非常に効果的です。また、メールアドレスの入力ミスを防ぐために、確認用の再入力欄を設けるのではなく、入力されたアドレスの確認を促す方法も検討しましょう。
5. 入力欄の文字種に合わせて最適なキーボードに自動切替する
スマートフォンでの入力体験を向上させるために、入力内容に応じた最適なキーボードを自動的に表示させましょう。
例えば、電話番号の入力欄では数字キーボード、メールアドレスの入力欄ではメールアドレス用キーボード(@マークが表示されるもの)を表示させることで、入力の手間を大幅に削減できます。
6. スマートフォン用にボタンの大きさを修正
フォームの操作性はデバイスごとに最適化しましょう。
特にスマートフォンでは、指でタップしやすいサイズと配置を考慮しましょう。
送信ボタンが小さすぎると押しにくく誤操作のもとになります。
ボタンのサイズを拡大し、目立つ色に変更し、誤操作による離脱を軽減しましょう。
7. ユーザーにとって不要な項目を削除、簡素化
資料請求フォームの最後に「どこで当社を知りましたか?」というアンケート項目。
マーケティング担当者にとっては有益な情報でも、ユーザーにとっては不要な入力項目です。
項目を削除してコンバージョン後にアンケートを取る、別の方法で情報収集することも検討しましょう。
削除しない場合はチェックボックスやラジオボタンで「クリックすればいいだけ」な設問に変更できないか検討しましょう。
EFOツールの選び方と主要機能比較
EFO対策は専用のツールを活用するのも一つの方法です。
ここでは、EFOツールの主な機能と選び方のポイントを解説します。
EFOツールの主な機能
EFOツールには以下のような機能が備わっています。
自社のニーズに合わせて、必要な機能を持つツールを選びましょう。
- 入力補助機能:郵便番号からの住所自動入力、メールアドレス補完など
- エラー検知・表示機能:リアルタイムでのバリデーションチェック
- 分析機能:フォームの離脱率、エラー発生率などの計測
- A/Bテスト機能:複数のフォームデザインを比較検証
- レスポンシブ対応:デバイスに応じた最適化表示
目的別EFOツールの選び方
EFOツールを選ぶ際は、自社の課題や目的に合わせて検討することが重要です。
離脱率の改善が急務な場合は、分析機能が充実したツールを選びましょう。フォームのどの段階で離脱が発生しているかを特定できれば、効果的な改善策を講じることができます。
入力エラーが多発している場合は、リアルタイムバリデーション機能や入力補助機能が充実したツールが適しています。ユーザーが入力しやすい環境を整えることで、エラーの発生を未然に防ぐことができます。
スマホユーザーが多い場合は、モバイル最適化機能に優れたツールを選びましょう。スマートフォンでの入力体験を向上させることで、モバイルからのコンバージョン率を大きく改善できる可能性があります。
BtoBサイトにおけるEFO対策の特徴と注意点
BtoBサイトでは、BtoCサイトとは異なるEFO対策が求められます。BtoBならではの特徴と注意点を理解し、効果的なフォーム最適化を行いましょう。
マーケティングと営業の連携が重要
BtoBサイトでのEFO対策は、マーケティング部門と営業部門の連携が不可欠です。マーケティングの視点では「入力項目は少なく」が鉄則ですが、営業の視点では「顧客情報は詳しく」が理想です。
この相反する要求をバランスよく調整するためには、両部門が協力してフォーム設計を行う必要があります。例えば、初回の資料請求では最小限の情報のみを取得し、その後のナーチャリングプロセスで徐々に詳細情報を収集するといった段階的なアプローチが効果的です。
リード獲得と商談獲得の2種類のフォーム設計
BtoBサイトでは、「見込み顧客(リード)獲得」と「商談獲得」という2つの目的に応じたフォーム設計が必要です。
リード獲得用フォームは、ホワイトペーパーやセミナー申込など、比較的ハードルの低いオファーに対するものです。この段階では、名前、会社名、メールアドレスなど最小限の情報のみを取得し、コンバージョン率を高めることを優先します。
一方、商談獲得用フォームは、製品デモや見積り依頼など、購買意欲の高いユーザーに対するものです。この段階では、業種、従業員数、予算など、より詳細な情報を取得し、営業活動に役立てることを優先します。
段階的な情報収集戦略
BtoBの購買プロセスは長期にわたるため、一度にすべての情報を取得しようとするのではなく、段階的に情報を収集する戦略が効果的です。
例えば、初回の資料請求では基本情報のみを取得し、その後のメールマーケティングやウェビナー参加などの機会に追加情報を収集していきます。このアプローチにより、ユーザーの負担を軽減しつつ、必要な情報を徐々に蓄積することができます。
EFO対策の実装手順
EFO対策を内部SEO効果と連動させるための具体的な実装手順を解説します。これらのステップに沿って改善を進めることで、フォームの使いやすさとSEO効果の両方を高めることができます。
現状分析と課題の特定
まずは現在のフォームの状況を詳細に分析し、課題を特定しましょう。Google Analyticsなどのツールを使って、フォームの離脱率や完了率、エラー発生率などを計測します。
また、ヒートマップツールを使って、ユーザーがフォーム上でどのように行動しているかを可視化することも効果的です。どの項目で迷っているか、どこでエラーが発生しているかを把握することで、改善すべきポイントが明確になります。
改善施策の優先順位付け
特定した課題に対して、効果が高いと思われる改善施策をリストアップし、優先順位をつけましょう。
優先順位をつける際は、以下の基準を参考にしてください。
- 実装の容易さ:技術的なハードルが低く、すぐに実装できる施策を優先
- 期待される効果:コンバージョン率の向上に大きく貢献すると思われる施策を優先
- ユーザーの不満度:ユーザーが特に不便を感じている部分の改善を優先
A/Bテストによる効果検証
改善施策を実装する際は、可能な限りA/Bテストを行い、効果を検証しましょう。A/Bテストとは、現行版(A)と改善版(B)を同時に運用し、どちらのパフォーマンスが優れているかを比較する手法です。
例えば、入力項目数を減らした新しいフォームと、従来のフォームを並行して運用し、コンバージョン率の差を測定します。統計的に有意な差が出た場合、より効果の高い方を本格的に採用します。
SEO指標との連動分析
EFO対策の効果を内部SEOの観点からも分析しましょう。具体的には、以下の指標の変化に注目します。
- 滞在時間:フォームが使いやすくなることで、サイト全体の滞在時間が延びる可能性があります
- 直帰率:フォームページでの直帰率が低下すれば、サイト全体の評価向上につながります
- ページビュー数:スムーズなフォーム体験により、サイト内の他ページも閲覧される可能性が高まります
これらの指標がポジティブに変化していれば、EFO対策が内部SEOにも好影響を与えていると判断できます。
モバイルファーストなEFO対策 スマホ最適化ポイント
Webサイトへのアクセスの多くはスマートフォンからです。特に日本ではスマホからのアクセス比率が非常に高いため、モバイルに最適化されたEFO対策が不可欠です。
タップしやすいUI設計
スマートフォンでは、指でタップするため、クリックよりも正確な操作が難しくなります。そのため、ボタンやリンクは十分な大きさと間隔を確保しましょう。
具体的には、タップ対象は最低44×44ピクセル以上のサイズを確保し、周囲に十分な余白を設けることをおすすめします。特に送信ボタンは大きめに設計し、目立つ色や位置に配置することで、タップミスを防ぎます。
入力のしやすさを重視した設計
スマートフォンでのキーボード入力は、PCと比べて手間がかかります。そのため、入力の手間を極力減らす工夫が重要です。
例えば、プルダウンメニューやラジオボタンなど、キーボード入力を必要としない選択肢を活用しましょう。また、入力内容に応じた最適なキーボードを表示させる設定も効果的です。電話番号欄では数字キーボード、メールアドレス欄ではメールアドレス用キーボードが自動的に表示されるようにしましょう。
ステップ型フォームの活用
スマートフォンの画面は小さいため、一度に多くの入力項目を表示すると圧迫感が生じます。そこで、入力プロセスを複数のステップに分割する「ステップ型フォーム」が効果的です。
ステップ型フォームでは、1画面あたり2〜3項目程度に絞り、ユーザーが集中して入力できる環境を整えます。ただし、ステップ数が多すぎると離脱の原因になるため、全体で3〜5ステップ程度に抑えることをおすすめします。
また、現在のステップと残りのステップを視覚的に表示することで、ユーザーの不安を軽減し、最後まで入力してもらいやすくなります。
EFO対策とプライバシー配慮の両立
EFO対策を進める上で、ユーザーのプライバシーへの配慮も欠かせません。特に2025年8月現在、Cookie規制やプライバシー保護の流れが強まっており、適切な対応が求められています。
個人情報の取得と利用目的の明示
フォームで個人情報を取得する際は、その利用目的を明確に表示することが法的にも求められています。単に「プライバシーポリシーに同意する」というチェックボックスを設けるだけでなく、具体的にどのような目的で情報を利用するのかを簡潔に説明しましょう。
例えば、「ご入力いただいた情報は、資料送付と関連サービスのご案内にのみ使用します」といった具体的な説明があると、ユーザーの安心感につながります。
必要最小限の情報取得
プライバシーへの配慮という観点からも、取得する個人情報は必要最小限に抑えることが重要です。特に初回接触の段階では、名前とメールアドレスのみを取得し、関係性が深まった段階で追加情報を取得するアプローチが効果的です。
また、任意項目と必須項目を明確に区別し、ユーザーが自分の判断で情報提供の範囲を決められるようにしましょう。
セキュリティ対策の可視化
フォームのセキュリティ対策を可視化することで、ユーザーの安心感を高めることができます。SSL証明書の取得(https化)はもちろん、セキュリティシールの表示や、「このフォームは暗号化されています」といったメッセージの表示も効果的です。
特に金融情報や機密性の高い情報を取得する場合は、セキュリティ対策をアピールすることで、ユーザーの不安を軽減し、コンバージョン率の向上につながります。
EFO対策はコンバージョン率向上を目的とした内部SEO対策
EFO対策は単なるフォーム改善にとどまらず、内部SEO対策としても重要な役割を果たします。ユーザー体験の向上がサイト全体の評価を高め、結果的に検索順位の向上にもつながるのです。
本記事では、EFO対策の基本概念から具体的な改善施策、BtoBサイトならではの注意点、モバイル最適化のポイントまで、幅広く解説してきました。最後に、EFO対策を成功させるための重要ポイントをまとめます。
- ユーザー視点を最優先:自社の都合ではなく、ユーザーにとって使いやすいフォームを設計する
- データに基づく改善:感覚や思い込みではなく、実際のデータを分析して改善点を特定する
- 継続的な最適化:一度の改善で終わらせず、定期的に効果を検証し、さらなる改善を重ねる
- 全体最適を意識:マーケティングと営業、UXとSEOなど、複数の視点からバランスの取れた最適化を行う
EFO対策は、比較的少ない工数で大きな効果が期待できる施策です。特に、すでに一定のトラフィックがあるサイトでは、フォームの最適化によってコンバージョン率を劇的に向上させることも可能です。
ぜひ本記事を参考に、自社サイトのフォーム改善に取り組んでみてください。ユーザー体験の向上とコンバージョン率の改善、そして内部SEO効果の最大化につながるはずです。
Webマーケティングと情報管理で組織の資産を構築し、継続的な成長を支援するBaseTreeでは、SEO対策を含むWebマーケティング支援サービスを提供しています。EFO対策を含む内部SEO対策でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
詳細はSEO対策のページをご覧ください。