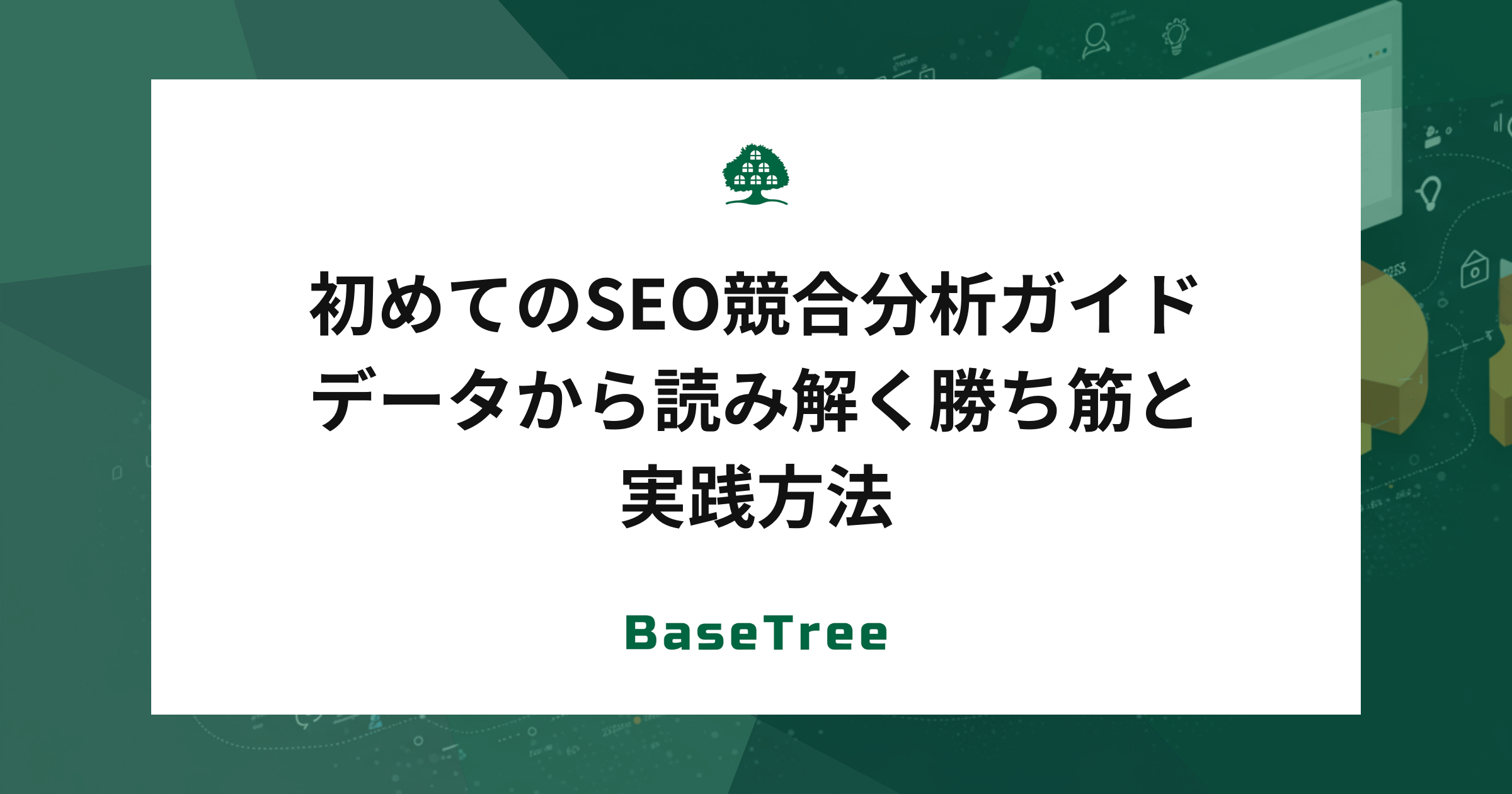「競合サイトの分析をしたいけど、何から始めればいいのかわからない…」
こんな悩みを抱えるWebサイト運営者やマーケティング担当者は少なくありません。SEO対策において、競合分析は成功への近道です。
なぜなら、すでに検索上位を獲得している競合サイトには、Googleが評価する要素が詰まっているから。その「勝ちパターン」を分析し、自社サイトに取り入れることで、効率的に順位向上を目指せます。
SEO競合分析とは?成功するための基本的な考え方
SEO競合分析とは、検索結果で上位表示されているサイトの戦略やコンテンツを調査し、そのサイトが「なぜ評価されているのか」を紐解く作業です。
単に「ライバルの真似をする」だけではなく、Googleが評価する要素を見極め、自社サイトの改善に活かすことが目的です。SEOの世界では「データに基づいた戦略的アプローチ」が成功の鍵を握っています。
競合分析で得られる主なメリットは以下の3つです。
- 市場のニーズを把握できる:ユーザーがどんな情報を求めているのかが明確になります
- 自社の立ち位置が見える:競合との比較により、自社の強みや課題が浮き彫りになります
- キーワード戦略を洗練できる:競合が狙うキーワードや取りこぼしているニッチを見つけられます
ただし検索結果に表示されるすべてのサイトが「本当の競合」とは限りません。例えば楽天やAmazonなどの大手ポータルサイトは、膨大な商品数と強力なドメインパワーにより検索上位を獲得していますが、一般的な企業サイトとは土俵が違います。
あなたが本当に意識すべき競合は、同じ業界で似たテーマや形式のコンテンツを展開しているサイトです。
競合サイトの正しい見つけ方と選び方
効果的なSEO競合分析の第一歩は「誰と戦うべきか」を正しく見極めること。
まず自社サイトが獲得したいキーワードをリストアップしましょう。そのキーワードで検索し、検索結果の1ページ目(上位10件)に表示されるサイトをチェックします。

本当の競合を見極める3つの視点
- 規模感:自社と似た規模や事業形態で運営されているか
- 形式:情報発信のスタイルが一致しているか(例:記事/ブログ/商品ページなど)
- 対象:地域・業種・ターゲット層が重なっているか
例えばあなたのサイトがコラム形式で運営されているなら、同じくコラムで上位表示されているサイトが競合になります。
一方、商品ページやサービス案内のページは、目的が異なるため直接の比較対象にはなりません。
地域密着型の事業であったり特定の専門分野に特化している場合、競合もその条件に合わせて見極めることが重要です。全国展開の大企業や大型ポータルサイトは、実際のターゲットや商圏が異なるケースも多く、競合として意識しすぎる必要はありません。
むしろ、同じ地域や業界で同規模のターゲット層に向けてアプローチしているサイトこそ、本当に参考にすべき相手です。
正しい競合を見極めることは、SEO戦略の「軸」を定める上で極めて重要です。闇雲に強大なサイトと比較するのではなく、自社と条件が近いサイトを基準にすることで、より現実的かつ効果的な改善策が見えてきます。
SEO競合分析の7つのポイントと調査手順
競合サイトを特定したら次は具体的な分析に入ります。効果的な競合分析を行うには、以下の7つの観点から調査することがポイントです。

1. 流入キーワードの分析
競合サイトがどのようなキーワードで検索流入を獲得しているかを調査することで、自社サイトが見逃している重要なキーワードを発見できます。
調査には「Ubersuggest」や「Semrush」などのSEOツールが便利です。無料プランでも基本的な分析は可能です。
競合サイトが上位表示を獲得している「ロングテールキーワード」は狙い目です。検索ボリュームは少ないものの、ユーザーの具体的な意図を反映しており、コンバージョン率が高い傾向があります。
2. ドメインパワーの評価
ドメインパワーとはサイト全体の評価や信頼性を数値化したものです。ドメインの年齢、被リンク(バックリンク)の数と質、コンテンツの量と質などから算出されます。
「Ahrefs」や「Moz」などのツールで、ドメインオーソリティ(DA)やドメインレーティング(DR)として確認できます。自社サイトと競合サイトのドメインパワーを比較することで、現実的な目標設定が可能になります。
3. 被リンク(バックリンク)の調査
被リンクは「他のサイトからのリンク」のことで、SEOにおいて重要な評価要素です。競合サイトがどのようなサイトから被リンクを獲得しているかを調査することで、自社サイトの被リンク戦略に活かせます。
「Ahrefs」や「Semrush」のバックリンク分析機能を使えば、競合サイトの被リンク元を一覧で確認できます。特に複数の競合サイトに共通する被リンク元は、自社サイトも獲得を目指すべき重要なターゲットとなります。
4. コンテンツの品質と構成
競合サイトのコンテンツを詳細に分析し以下の点を確認します。
- コンテンツの長さ(文字数)
- 見出し(H1、H2、H3など)の構成
- キーワードの使用頻度と配置
- 画像・動画などのマルチメディアの活用
- 内部リンクの設計
上位表示されているページの見出し構成を分析することで、ユーザーが求める情報の全体像が見えてきます。上位表示されているページを参考に、より包括的で価値の高いコンテンツを作成しましょう。
5. アクセス数と流入経路
競合サイトのアクセス数や流入経路を推測すると、マーケティング戦略が立案しやすくなります。「SimilarWeb」などのツールを使えば、競合サイトのおおよそのアクセス数や流入元を確認できます。
検索流入の割合が高いサイトはSEOに力を入れている可能性が高く、参考にできる点が多いでしょう。一方、SNSからの流入が多いサイトは、ソーシャルメディア戦略を調査する価値があります。
6. 内部リンク構造の分析
サイト内のページ同士がどのようにリンクで結ばれているかという「内部リンク構造」は、SEOにおいて重要な要素です。競合サイトの内部リンク構造を分析することで「SEO対策に強いサイト」を設計するヒントが得られます。
「Screaming Frog SEO Spider」などのクローラーツールを使えば、競合サイトの内部リンク構造を可視化できます。サービスページや商品ページなどへの内部リンクが多い傾向があれば、それはGoogleに「このページは重要です」と伝えるための戦略と考えられます。
7. サイト運営元企業の分析
競合サイトを運営している企業や組織についても調査しましょう。企業規模、事業内容、マーケティング予算などを把握することで、競合の戦略をより深く理解できます。
企業のプレスリリースやSNSアカウント、採用情報なども参考になります。例えばSEO専門家やコンテンツマーケターの採用募集があれば、今後さらにコンテンツマーケティングに注力する可能性が高いと予測できます。
SEO競合分析に役立つツールと活用法
効率的に競合分析を行うには適切なツール活用が欠かせません。ここではSEO競合分析に役立つ主要ツールとその活用法を紹介します。
1. 無料で使えるSEO競合分析ツール
予算に制約がある場合でも以下の無料ツールを組み合わせることで、基本的な競合分析が可能です。
- Google Search Console:自サイトのパフォーマンスデータを確認できます
- Google Analytics:アクセス解析の基本ツールです
- Ubersuggest(無料プラン):基本的なキーワード分析や競合サイト分析が可能です
- Screaming Frog SEO Spider(無料版):500URLまでのサイト構造分析ができます
- PageSpeed Insights:ページ速度や技術的な問題を分析できます
2. 有料のプロフェッショナルツール
より詳細な分析や大規模なサイト運営には、以下の有料ツールが有効です。
- Semrush:総合的なSEO分析が可能な人気ツールです
- Ahrefs:特に被リンク分析に強みを持つツールです
- Moz Pro:キーワード調査やサイト分析が充実しています
- SimilarWeb:競合サイトのトラフィック推定に特化しています
- GRAN SEARCH:日本語に特化した分析が可能なツールです
月額料金が発生しますが、無料トライアル期間を活用すれば初期分析を無料で行うことも可能です。
3. ツールを使った実践的な分析手順
ツールを使った効果的な競合分析の手順は以下の通りです。
- キーワード分析:競合サイトが上位表示されているキーワードをリストアップします
- コンテンツギャップ分析:競合が上位表示されているが、自社サイトが対応していないキーワードを特定します
- 被リンク分析:競合サイトの被リンク元を調査し、獲得可能な被リンク先をリストアップします
- サイト構造分析:競合サイトの内部リンク構造やページ階層を分析します
- 技術的SEO分析:ページ速度、モバイル対応、構造化データなどの技術的要素を比較します
各分析結果を統合することで、競合サイトの強みと弱みが明確になり、自社サイトの改善点が見えてきます。
データから読み解く勝ち筋の見つけ方
競合分析で得たデータを活用し、実際にSEO戦略を立案する方法を解説します。
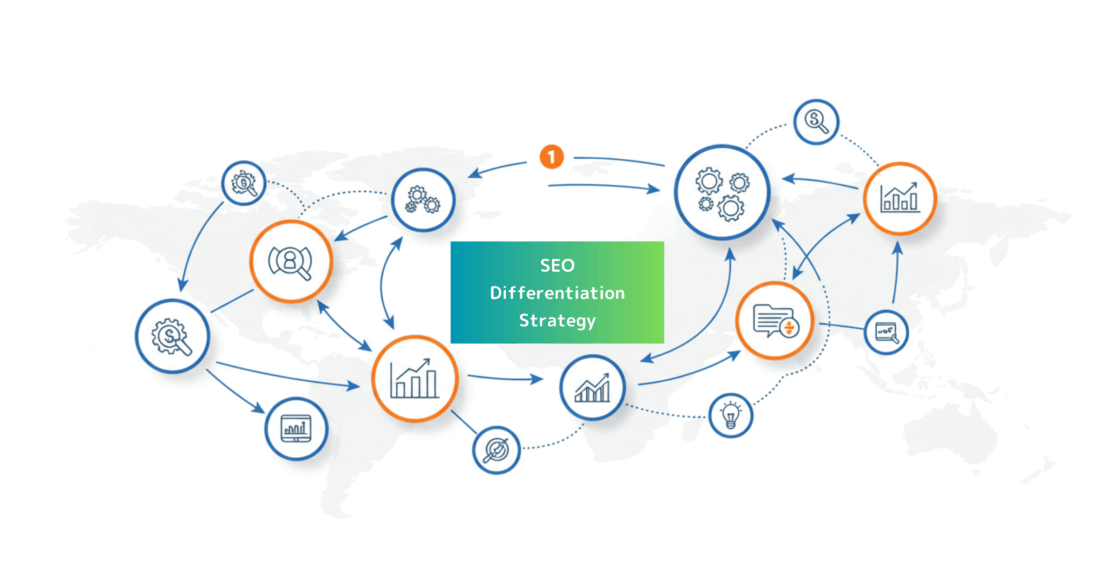
1. コンテンツギャップの特定と活用
コンテンツギャップとは「競合サイトは上位表示されているが、自社サイトがまだ対応していないキーワードやトピック」のこと。コンテンツギャップが特定できれば、さらに効果的なコンテンツ戦略を立てられます。
例えばSemrushの「キーワードギャップ」機能や、Ahrefsの「コンテンツギャップ」機能を使えば、複数の競合サイトと自社サイトを比較し、取りこぼしているキーワードを一覧で確認できます。
複数の競合サイトが共通して上位表示されているキーワードは、市場で需要が高く、重点的に対策すべきキーワードだと推測できます。
2. 競合のコンテンツ戦略から学ぶ
上位表示されている競合サイトのコンテンツを詳細に分析し以下の点に注目しましょう。
- コンテンツの深さと網羅性:トピックをどれだけ深く、広くカバーしているか
- ユーザー体験の設計:情報の提示方法、ナビゲーション、視覚的要素の活用
- 更新頻度とフレッシュネス:コンテンツの更新頻度や最新情報の反映
- ユーザーエンゲージメント:コメント、シェア、滞在時間などの指標
競合サイトが持つコンテンツの量と質を分析することで「なぜこのコンテンツが評価されているのか」が見えてきます。単に競合のコンテンツを真似るのではなく、競合の強さを理解し、それを上回る価値の高いコンテンツを作成することが重要です。
3. 技術的SEOの差別化ポイント
技術的SEO(テクニカルSEO)の面でも競合サイトと自社サイトを比較すると、改善点が見えてきます。
- ページ速度:PageSpeed Insightsで競合サイトのスコアを確認し、自社サイトより優れている場合は改善を検討
- モバイル対応:モバイルフレンドリーテストで競合サイトの対応状況を確認
- 構造化データ:Schema.orgなどの構造化データの実装状況を比較
- サイトマップとクロール効率:XMLサイトマップの設計や内部リンク構造の最適化
技術的SEOは見た目の変化が少なく地味な作業ですが、競合との差別化を図る上で重要な要素です。特にCore Web Vitalsのスコアが低い競合サイトがあれば、ここを改善することで優位性を確保できる可能性があります。
4. 独自の強みを活かした差別化戦略
競合分析は重要ですが、最終的には自社の強みを活かした独自の戦略が必要です。競合サイトの分析から得た知見を基に以下のような差別化ポイントを検討しましょう。
- 専門性の深掘り:特定の分野やトピックに特化した深い知見を提供
- 独自データの活用:自社だけが持つデータや調査結果を公開
- ユーザー体験の向上:より使いやすく、価値の高い情報提供方法を開発
- 地域特化:特定の地域に特化したコンテンツや情報を提供
競合と同じことをするだけでは競合に追いつくことも、ましてや上回ることはできません。競合分析で得た情報を基に、さらに一歩先を行く戦略を立てることがSEOで真の成功を収める秘訣です。
SEO競合分析から実践へ、具体的な改善方法
競合分析で得た知見を実際のSEO施策に落とし込む手順を解説します。

1. 優先順位の決定と実行計画の策定
競合分析で見つかった改善点は通常多岐にわたります。すべてを一度に実行するのは現実的ではないため、以下の基準で優先順位を決定しましょう。
- 効果の大きさ:SEO効果が大きいと予想される施策を優先
- 実装の容易さ:少ない労力で実装できる対策から着手
- 事業への影響:コンバージョンや売上に直結する施策を重視
優先順位が決まったら具体的な実行計画を策定します。各施策の担当者、期限、必要なリソースを明確にし、進捗を管理できる形にしましょう。
2. コンテンツ戦略の実行
コンテンツギャップ分析で見つかったキーワードやトピックに基づき、コンテンツ戦略を実行します。
- 新規コンテンツの作成:未対応のキーワードに対して新たなコンテンツを作成
- 既存コンテンツの最適化:競合分析で得た知見を基に、既存コンテンツを改善
- コンテンツクラスター構築:関連するトピックをまとめたコンテンツクラスターを設計
コンテンツ作成は競合サイトの良い点を取り入れつつ、さらに価値を高める工夫をしましょう。例えばより詳細な情報、より最新のデータ、より実践的なアドバイス、より視覚的な補足説明を加えるなど、競合より分かりやすいもの、ためになるものを提供しましょう。
3. 技術的SEOの改善
競合サイトとの技術的SEOの比較で見つかった課題に対処します。
- ページ速度の最適化:画像の圧縮、不要なスクリプトの削除、キャッシュの活用など
- モバイル対応の強化:レスポンシブデザインの改善、タップターゲットの最適化など
- 構造化データの実装:Schema.orgマークアップの追加や最適化
- 内部リンク構造の改善:重要なページへの内部リンクを増やし、クローラビリティを向上
技術的SEOの改善は即効性はないものの、長期的なSEO効果が期待できます。特にCore Web Vitalsのスコア向上は、ユーザー体験の改善にもつながります。
4. 外部SEO施策の実行
競合の被リンク分析で見つかったリンクリストを活かし、外部SEO施策を実行します。
- 高品質な被リンク獲得:競合が被リンクを獲得しているサイトにアプローチ
- ブランドメンションの増加:業界メディアやブログでの言及を増やす施策
- ソーシャルシグナルの強化:SNSでの共有や言及を促進する取り組み
被リンク獲得は単に数を増やすのではなく、関連性の高い質の良いサイトからの自然な被リンクを目指しましょう。競合サイトの被リンク元を分析し、同様のアプローチで被リンクを獲得できる可能性があります。
5. 効果測定とPDCAサイクル
SEO施策の効果を定期的に測定しPDCAサイクルを回すことが重要です。
- KPIの設定:検索順位、オーガニックトラフィック、コンバージョン率など
- 定期的なモニタリング:週次や月次でKPIの推移を確認
- 競合との比較分析:自社と競合のパフォーマンスを継続的に比較
- 施策の改善:効果が出ている施策は強化し、効果が低い施策は見直し
SEO対策は一度の施策で完結するものではなく、継続的な改善が必要です。競合も常に進化しているため、定期的に競合分析を行い、最新の状況に合わせて戦略を調整しましょう。
SEO競合分析で陥りがちな3つの失敗ポイント
最後にSEO競合分析を成功させるための注意点を紹介します。競合分析を行う際には以下の点に注意しましょう。
- 競合の真似だけに終始する:競合の戦略を理解し、それを超える価値を提供することが重要です
- データの過信:ツールが提供するデータは推定値であることを理解し、複数の情報源で検証しましょう
- 自社の強みを見失う:競合分析に没頭するあまり、自社の独自性や強みを活かせなくなることがあります
競合分析はあくまで参考情報であり、最終的には自社の状況や目標に合わせた戦略が必要です。
継続的な競合分析が大事
SEOの世界は常に変化しています。検索アルゴリズムの更新、競合の戦略変更、市場トレンドの変化など、様々な要因によって最適なSEO戦略も変わります。
競合分析は一度きりではなく、定期的(四半期ごとなど)に行ってください。継続的な競合分析により、市場の変化や競合の動向を把握し、常に一歩先を行く戦略を立てることができます。
特に以下のタイミングでは競合分析を再実施することをおすすめします。
- 検索順位に大きな変動があったとき
- 新たな競合が市場に参入したとき
- Googleのアルゴリズムが大幅に更新されたとき
- 自社の事業戦略や目標が変わったとき
変化に柔軟に対応し、常に最適なSEO戦略を追求することが、長期的な成功には欠かせません。
データに基づいたSEO競合分析が、SEO対策効率を上げ、成果を上げる
SEO競合分析は、検索上位を獲得するための効率的な道筋を示してくれます。本記事で解説した内容をまとめると、以下のようになります。
- SEO競合分析とは、検索結果で上位表示されているサイトの戦略やコンテンツを調査し、その成功要因を自社サイトに活かすプロセス
- 効果的な競合分析のためには、まず「誰と戦うべきか」を正しく見極める
- 競合サイトは、流入キーワード、ドメインパワー、被リンク、コンテンツ、アクセス数、内部リンク構造、運営元企業の7つの観点から分析
- 分析結果を基に、コンテンツギャップの特定、コンテンツ戦略の改善、技術的SEOの最適化、独自の差別化戦略を立案
- 施策の実行は優先順位を決めて計画的に行い、効果を測定しながらPDCAサイクルを回す
- 競合分析は一度きりではなく、市場や競合の変化に合わせて定期的に行うことで、常に最適な戦略を追求
SEO競合分析は、闇雲にコンテンツを作成したり、SEO施策を実行したりするよりも、はるかに効率的にSEO効果を高められる方法です。本記事で紹介した手法を活用し、データに基づいた戦略的なSEO対策を実践してください。
検索エンジンの世界は常に変化していますが、競合分析の本質は変わりません。常に市場と競合を注視し、ユーザーにとって最も価値のある情報を提供することがSEO対策の本質です。
埼玉県・群馬県でSEO対策にお悩みの方は、ぜひBaseTreeにご相談ください。
データに基づいた論理的・構造的なSEO戦略の設計から、内部SEO対策、コンテンツSEO、外部SEO対策、分析・改善まで、一貫したサポートを提供しています。
詳細は埼玉・群馬県特化のSEO対策ページをご覧ください。