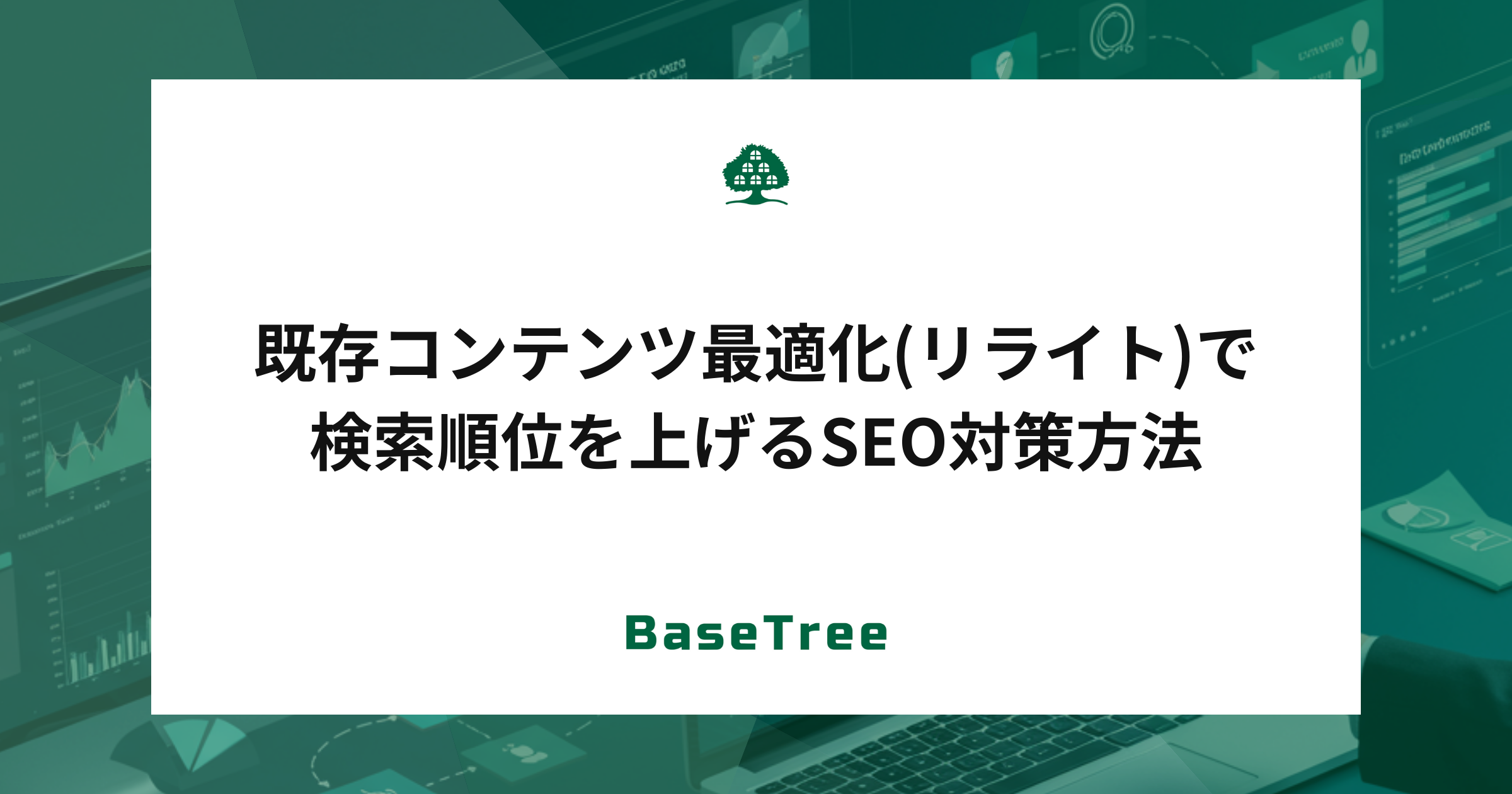SEO対策は新規記事を出し続けることだけではない。既存コンテンツ最適化(SEOリライト)もSEO対策の1つ
「新しいコンテンツをたくさん作っているのに、なぜか検索順位が上がらない…」
「一体何をすれば、ウェブサイトの集客は改善するのだろうか…」
埼玉県や群馬県で事業を営む経営者やウェブサイト担当者なら、このような悩みを一度は抱えたことがあるのではないでしょうか。多くの情報が溢れる中で、自社の進むべき道が見えずに困惑するのも無理はありません。
2025年現在のSEO対策において、最も費用対効果が高く、確実な成果に繋がりやすい戦略は、必ずしも新規コンテンツの作成だけではありません。むしろ、今ある資産、つまり既存コンテンツの最適化(リライト)こそが、少ないリソースで大きな成果を生み出します。
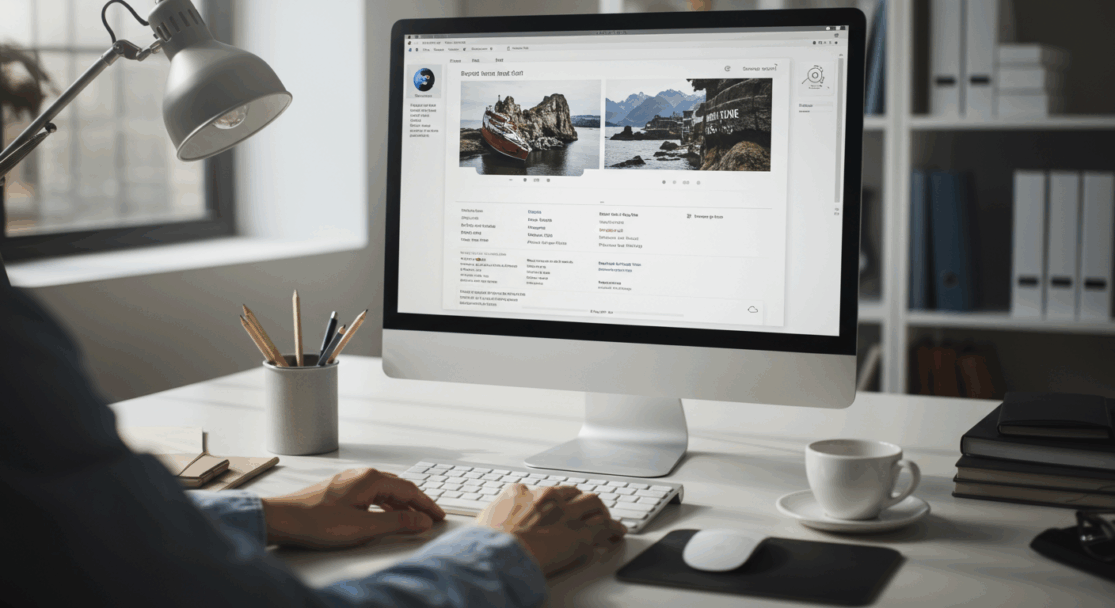
10年以上にわたりウェブディレクターとして多くの企業サイトを見てきた経験から断言できるのは、ほとんどの企業が「量」を追い求めるあまり、すでに持っているコンテンツの「質」を磨く機会を見逃しているということ。
本記事では、なぜ今「既存コンテンツの最適化」が重要なのか、そして具体的にどのように進めれば検索順位を上げ、事業の成果に繋げられるのかを、具体的な手順を交えながら解説します。
既存コンテンツ最適化とは何か?
まず「既存コンテンツ最適化」の基本と、2025年のSEO環境においてなぜ重要視されるのかを紐解いていきます。
①既存コンテンツ最適化の定義と重要性
既存コンテンツ最適化とは、すでに公開されているウェブページやブログ記事を見直し、検索エンジンとユーザー双方にとっての価値を高める改善活動全般を指します。一般的に「リライト」とも呼ばれますが、単なる文章の書き換えにとどまりません。情報の追加、構成の見直し、技術的な改善までを含む包括的なアプローチです。
Googleのアルゴリズムは年々進化し、単に新しい情報を発信するサイトよりも、一つのトピックに対して深く、正確で、信頼できる情報を提供しているサイトを高く評価する傾向が強まっています。つまり「量の追求」から「質の深化」へと評価基準がシフトしています。
この変化こそ、既存コンテンツ最適化が重要性を増している最大の理由です。
②新規作成より最適化を優先すべき理由とメリット
「新しい情報を発信し続けないと、サイトが評価されないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、特にリソースが限られる中小企業にとっては既存コンテンツの最適化から始める方がはるかに賢明な戦略と言えます。
既存コンテンツ最適化(リライト)の主なメリットは以下です。
- リソースの効率的活用
新規コンテンツを1本作成するには、企画、調査、執筆、編集、公開と多くの時間とコストがかかります。一方、既存コンテンツの最適化は、すでにある土台を活かすため、より少ない労力で成果を出せる可能性が高いのです。 - 検索順位の向上
Googleにすでにインデックス(認識)されているページは、一定の評価を持っています。最新情報への更新や、ユーザーの検索意図に沿った内容の追加、内部リンクの強化などを行うことで、評価をさらに高め、短期間での順位上昇が期待できます。 - ユーザー体験の改善
情報が整理され、より深く、分かりやすくなったコンテンツは、ユーザーの満足度を高めます。サイトへの滞在時間が延び、直帰率が下がるなど、エンゲージメントの向上に直結します。 - コンバージョン率の向上
ユーザーの疑問や悩みに的確に答える質の高いコンテンツは、信頼を生み、最終的なゴールである「問い合わせ」や「購入」といったコンバージョン率を高める効果があります。
実際、支援したクライアントの中には新規コンテンツ作成に月10万円をかけていたものの成果が出ず、既存コンテンツの最適化に方針転換した結果、わずか3ヶ月で主要キーワードの検索順位が平均12位上昇し、問い合わせ数が1.5倍になった事例もあります。
闇雲に新規記事を追加する前に、まずは自社サイト内にある「伸びしろのあるページ」を見つけ出し、磨き上げること。それが中小企業におけるSEO戦略の正攻法です。
最適化すべきページの選び方・優先順位の付け方
すべての既存コンテンツを一度に最適化するのは非効率です。成果を最大化するためには、どのページから手をつけるべきか、戦略的に優先順位を決める必要があります。ここでは効果が出やすい「お宝ページ」を見つけ出すための3つの視点を紹介します。

| 優先度 | タイプ | 特徴 | 確認ツール |
| 高 | あともう一歩のページ | 検索順位が6位〜20位。表示回数は多い。 | Google Search Console |
| 中 | 過去のスター記事 | 過去にアクセスが多かったが、現在は減少。 | Google Analytics |
| 中 | コンバージョン貢献ページ | 問い合わせや購入に近いページ。 | Google Analytics |
| 低 | 上記以外 | アクセスも少なく、コンバージョンにも遠い。 | – |
3つの視点に基づき最適化すべきページのリストを5〜10ページ程度作成してみてください。その上で優先度の高いものから順に取り組んでいくのが最も効率的な進め方です。
①「あともう一歩」のページを狙う(11位~20位のコンテンツ)
検索結果の2ページ目(11位~20位)や、1ページ目の下位(6位~10位)に表示されているコンテンツは、最適化によって最も効果が出やすいローハンギングフルーツ(手の届きやすい果実)です。Googleから一定の評価は得ているものの、上位表示されるには何かが少し足りない状態です。
少しテコ入れをするだけで、1ページ目の上位にランクインし、アクセス数が飛躍的に伸びる可能性があります。
確認方法
Google Search Consoleの「検索パフォーマンス」レポートを確認しましょう。
「ページ」タブで各URLの「平均掲載順位」と「表示回数」「クリック数」を確認します。
- 表示回数は多いのに順位が低い(20位以下)
- 順位はそこそこ良いのに(20位以上)、クリック数が少ない(1クリックもない)
この条件に合致するページが、最優先で取り組むべき候補です。
②かつてのスター記事を復活させる(流入が減少したコンテンツ)
「以前はこの記事から多くのアクセスがあったのに、最近はめっきり減ってしまった…」
このような、過去にトラフィックを集めていたが、現在は検索順位が下がってしまったコンテンツも最適化のターゲットになり得ます。
順位が下がった原因は、主に以下の2つが考えられます。
- 情報が古くなってしまった
- 競合サイトがより質の高いコンテンツを公開した
かつてのスター記事は、情報の鮮度を高め、競合コンテンツと比較して不足している情報を補うことで、かつての輝きを取り戻せる可能性が高いでしょう。
確認方法
Google Analyticsで「行動」>「サイトコンテンツ」>「すべてのページ」レポートを開きます。期間を過去1年〜2年などに設定し、現在の期間と比較することで、アクセス数が大きく減少しているページを特定できます。
③ゴールに近いページを強化する(コンバージョン貢献度の高いコンテンツ)
ウェブサイトの最終目的は、問い合わせや資料請求などのコンバージョンを獲得することです。すでにコンバージョンを生み出しているページや、コンバージョンに至るまでの経路でよく閲覧されているページを強化することで、事業への直接的なインパクトを最大化できます。
例えば「サービス料金」ページや「導入事例」ページなど。ページ内容をより充実させ、ユーザーの最後のひと押しとなるような情報を加えることで、コンバージョン率の向上が期待できます。
確認方法
Google Analytics 4 の「コンバージョン」>「目標」>「目標達成プロセス」や「コンバージョン経路」レポートを確認します。どのページがコンバージョンの獲得に貢献しているかを分析し、優先順位を決定します。
既存コンテンツ最適化の実践的な7つの手法
優先順位が決まったら、いよいよ具体的な最適化作業に入ります。ここでは2025年の最新SEO動向を踏まえた7つの手法を解説します。
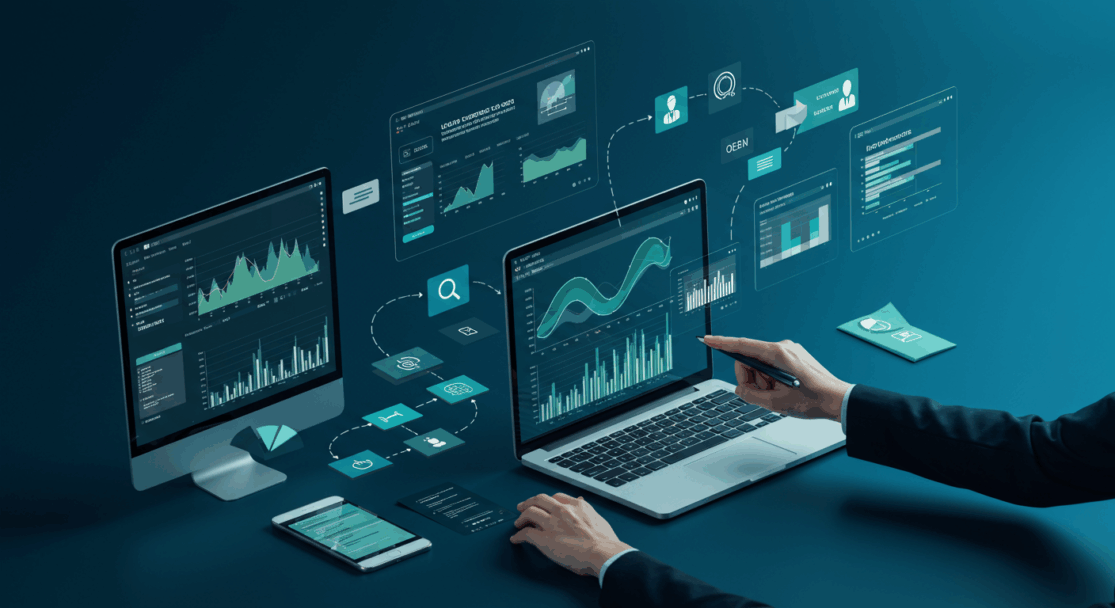
①コンテンツの「鮮度」と「正確性」を高める
情報が古いコンテンツは、ユーザーと検索エンジンの両方から信頼を失います。まず取り組むのは、コンテンツの情報を最新状態にアップデートすることです。
- 古い統計データや事例を最新のものに置き換える
- 法改正や業界のトレンドなど、環境の変化を反映させる
- 公開日・更新日を明確に記載し、定期的な見直しを行う
例えば「2023年のSEOトレンド」という記事があれば、タイトルと内容を「【2025年最新版】SEOトレンド解説」に更新し最新の情報へと刷新します。これだけでコンテンツの価値は格段に上がります。
②ユーザーの「検索意図」に合わせて情報を拡充する
検索順位が伸び悩む最大の原因は、ユーザーが本当に知りたいこと(検索意図)とコンテンツ内容にズレがあること。
実際にキーワード(検索対策したい語句)で検索し、上位表示されている競合サイトを徹底的に分析しましょう。そして自社のコンテンツに不足している情報や視点を見つけ出し、追加していきます。
- 検索意図の深掘り
例えば「WordPress 始め方」で検索するユーザーは、単なるインストール手順だけでなく、サーバー選び、必要な費用、初期設定、よくあるトラブルなども知りたいはずです。 - 網羅性の向上
競合がカバーしているトピック(話題、議題)は自社でもれなくカバーしましょう。その上で自社独自の知見や経験に基づく情報を加えることで差別化を図ります。 - 形式の最適化
FAQ(よくある質問)セクションを追加したり、ステップバイステップ(段階を追った手順や方法)のガイド形式にしたり、図解や動画を追加したりと、ユーザーが最も理解しやすい形式で情報を提供します。
③キーワード最適化と関連語句の追加
メインキーワードだけでなく、それを説明する上で自然に使われる関連キーワードや共起語も適切に記述しましょう。コンテンツの専門性と網羅性を検索エンジンに伝えることができます。
- タイトルタグ、h1見出し、メタディスクリプション
これらの最も重要な要素に、メインキーワードを含めます。 - h2、h3などの見出し
各セクションの話題や議題を表す見出しに、関連キーワードを配置します。 - 本文
本文中には共起語(例えば「SEO対策」なら「検索順位」「キーワード」「コンテンツ」「内部リンク」など)を不自然にならないように織り交ぜていきます。
注意点
キーワードを詰め込みすぎる「キーワード過多」は逆効果です。あくまでユーザーにとって読みやすい文章を心がけましょう。
④サイトの回遊性を高める「内部リンク」最適化
内部リンクはユーザーをサイト内の関連ページへ案内し、より深く情報を得てもらうための道しるべです。同時にサイト内のどのページが重要かを検索エンジンに伝える重要な役割も果たします。
- 関連性の高いコンテンツ同士を繋ぐ
「SEO対策の基礎」という記事から、「タイトルタグの付け方」「内部リンクの重要性」といった、より具体的な記事へリンクを貼ります。 - 古い記事から新しい記事へリンクを貼る
サイトの情報を最新に保つ上で効果的です。 - 重要なページへリンクを集める
最もコンバージョンさせたいサービスページなどへ、関連するブログ記事からリンクを設置します。このとき、「詳しくはこちら」のような曖昧なテキストではなく、「〇〇サービスの料金プランを見る」のように、リンク先の内容がわかる具体的なアンカーテキストを使用することが重要です。
⑤検索結果でクリック率を高める「メタデータ」の最適化
タイトルタグとメタディスクリプションは、検索結果ページ(SERPs)でユーザーが最初に目にする情報です。この2つが魅力的でなければ、たとえ1位に表示されてもクリックしてもらえません。
タイトルタグ
- 文字数は30文字前後が目安です。
- 重要なキーワードはできるだけ前半に含めます。
- ユーザーが「自分のための情報だ」と思えるような、具体的で魅力的な文言を考えます。(例 「WordPress 使い方」→「【2025年最新】初心者でも簡単!WordPressの始め方と基本設定」)
メタディスクリプション
- 文字数は80〜100文字程度が目安です。
- ページの要約を簡潔に記述し、ユーザーがクリックすることで何を得られるのかを伝えます。
- キーワードを含めつつ、クリックを促す行動喚起(CTA)の文言を入れると効果的です。
⑥検索エンジンに正しく伝える「構造化データ」の実装
構造化データ(スキーママークアップ)は、検索エンジンがページの内容をより深く、正確に理解するのを手助けするコードです。
適切に実装することで、検索結果で通常より多くの情報(レビュー評価、価格、FAQなど)を表示させるリッチリザルトとして表示される可能性が高まり、クリック率の向上に繋がります。
- コンテンツの種類に応じたマークアップを実装する
ブログ記事なら「Article」、よくある質問なら「FAQPage」、手順を解説するなら「HowTo」、製品情報なら「Product」など、様々な種類があります。 - 正確性を検証する
実装後は、Googleが提供する「リッチリザルトテストツール」でエラーがないか必ず確認しましょう。
⑦ユーザー体験を向上させる「ページ表示速度」と「モバイル対応」
どれだけ良いコンテンツでも、ページの表示が遅かったり、スマートフォンで見づらかったりすれば、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。ページ表示速度とモバイルフレンドリー対応は、今や検索順位を左右する重要な要素(コアウェブバイタル)です。
- 画像の最適化
ファイルサイズを圧縮し、適切な形式(WebPなど)を使用します。 - 不要なコードやプラグインの削除
サイトの動作を重くしている原因を特定し、削除または代替案を検討します。 - モバイルでの表示確認
スマートフォンの画面で文字が小さすぎないか、ボタンが押しにくくないかなどを実機で確認します。
ある調査では、ページ表示速度が1秒遅れるだけで、コンバージョン率が7%低下するというデータもあります。技術的な改善は、ユーザー体験とSEOの両方に直接的な効果をもたらします。
失敗しないための実践的ワークフローと注意点
理論を学んでも、いざ実践するとなると何から手をつければ良いか分からなくなりがちです。ここでは成果を出すための実践的なワークフローと、多くの人が陥りがちな失敗例とその対策を解説します。

①成果を出すための5ステップ・ワークフロー
この流れに沿って進めることで、抜け漏れなく、効率的に最適化作業を行うことができます。
【ステップ1】現状分析と課題特定
- Google Search ConsoleとGoogle Analyticsで、対象ページの現状(順位、クリック率、直帰率、滞在時間など)を詳細に分析します。
- 上位表示されている競合コンテンツを分析し、自社コンテンツとのギャップ(情報の網羅性、専門性、分かりやすさなど)を洗い出します。
【ステップ2】改善計画の策定
- 分析結果に基づき、「どの情報を追加するか」「構成をどう変更するか」「どの技術的要素を改善するか」といった具体的な改善計画を立てます。
- この段階で、「誰の、どんな悩みを解決するページにするのか」というゴールを再確認することが重要です。
【ステップ3】コンテンツの改善実施
- 計画に沿って、実際にリライト作業を行います。古い情報の更新、新しい情報の追加、見出し構造の最適化、図解や画像の追加など、ユーザーの理解を助ける工夫を凝らします。
【ステップ4】技術的SEO要素の最適化
- コンテンツの改善と並行して、タイトルタグ、メタディスクリプション、画像のalt属性、内部リンク、構造化データなどの技術的な要素を最適化します。
【ステップ5】効果測定と継続的な改善
- 最適化後、最低でも1ヶ月は様子を見ます。Google Search Consoleで検索順位とクリック率の変化を追い、Google Analyticsでユーザー行動の変化を分析します。
- 結果が良ければその要因を分析し、他のページにも展開します。結果が出なければ、何が原因かを再度分析し、さらなる改善を加えます。
SEO対策は一度やれば終わりではありません。
このPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を継続的に回していくことが長期的な成功の秘訣です。
②既存コンテンツ最適化で陥りがちな5つの失敗と対策
良かれと思ってやった改善が、実は逆効果になってしまうケースも少なくありません。よくある失敗例を知り、同じ轍を踏まないようにしましょう。

【失敗1】とにかく文字数を増やしてしまう
- 要因
Googleは文字数を見ているのではなく、ユーザーの疑問に答えられているかを見ています。無関係な情報をだらだらと書き連ねても、ユーザーが離脱するだけで評価は上がりません。 - 対策
「ユーザーの次の疑問は何か?」を常に考え、その答えとなる情報を追加しましょう。冗長な表現は削り、簡潔で分かりやすい文章を心がけます。
【失敗2】検索意図を無視し、自社の宣伝ばかりする
- 要因
情報を探しに来たユーザーに対して、いきなり売り込みをかけても嫌われるだけです。検索意図が「情報収集」であるにも関わらず、コンテンツが「販売」に偏っていると、すぐに離脱されてしまいます。 - 対策
まずはユーザーの悩みを解決することに徹しましょう。信頼関係を築いた上で、自然な流れで自社サービスを紹介するのが正しい順序です。
【失敗3】内容は変えずに公開日だけを更新する
- 要因
小手先のテクニックでGoogleを欺くことはできません。ユーザーが見たときに「どこが更新されたの?」と不信感を抱かれ、サイト全体の信頼性を損なうリスクすらあります。 - 対策
実質的な内容の更新を行った上で、更新日を明記しましょう。「2025年〇月〇日更新: 〇〇の情報を最新化」のように、更新内容を具体的に示すとさらに親切です。
【失敗4】不自然なほどキーワードを詰め込む
- 要因
文章が読みにくくなり、ユーザー体験を著しく損ないます。これは検索エンジンからもペナルティを受ける可能性がある、時代遅れの手法です。 - 対策
キーワードは自然な文脈で使いましょう。類義語や関連語をバランス良く使用することで、トピックの網羅性を高めることができます。常に「人間に向かって書いている」という意識が重要です。
【失敗5】一度の最適化で満足してしまう
- 要因
SEO環境は常に変化しています。競合サイトも日々コンテンツを改善しており、一度上位表示されても安泰ではありません。 - 対策
特にアクセスの多いページや、事業の成果に直結する重要なページは、四半期に一度など定期的に見直しを行いましょう。継続的な改善こそが、安定した上位表示を維持する唯一の方法です。
2025年以降のSEOトレンドと未来の最適化戦略
AIの台頭など変化の激しい時代において、今後どのような視点でコンテンツを最適化していくべきか。未来のトレンドを解説します。

①E-E-A-Tのさらなる重要化
E-E-A-Tとは、Googleがコンテンツの品質を評価するために用いる基準で経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字を取ったものです。この指標の重要性は、今後ますます高まります。
既存コンテンツを最適化する際は、以下の点を強化することが不可欠です。
- 「経験」を示す 実際の体験談、導入事例、具体的なケーススタディなど、その人にしか書けない一次情報を盛り込みます。
- 「専門性」と「権威性」を示す 著者情報を明記し、その分野での実績や資格などをアピールします。公的機関のデータや専門家の見解を引用することも有効です。
- 「信頼性」を高める 情報の引用元を明記し、サイト運営者情報を明確に開示します。セキュリティ対策(HTTPS化)も基本です。
②AI検索時代への対応
Googleの「AI Overview(AIによる概要)」など、AIが検索結果の要約を生成する機能が拡大しています。これにより、ユーザーがサイトをクリックせずに検索を終えてしまう「ゼロクリック検索」が増加すると予想されます。
この変化に対応するためには、AIに引用されやすい、分かりやすく構造化されたコンテンツを作成することが重要になります。
- 結論ファーストで書く 冒頭で問いに対する答えを明確に提示します。
- 定義や手順を明確にする 「〇〇とは」といった定義や、番号付きリストでの手順説明は、AIが引用しやすい形式です。
- FAQコンテンツを充実させる ユーザーの具体的な疑問にQ&A形式で答えるコンテンツは、AIにそのまま活用されやすい傾向があります。
③マルチモーダルコンテンツの重要性
テキストだけでなく、画像、図解、インフォグラフィック、動画、音声などを組み合わせた「マルチモーダルコンテンツ」の価値が高まっています。
複雑な内容を図で示したり、手順を動画で解説したりすることで、ユーザーの理解度は飛躍的に向上します。これはサイトの滞在時間を延ばし、エンゲージメントを高める効果もあり、間接的にSEO評価の向上にも繋がります。既存の記事に、内容を補足する動画やインフォグラフィックを追加するだけでも、大きな価値向上になります。
「既存コンテンツ」という今ある資産を、「最適化(リライト)」で付加価値を高める「既存コンテンツ最適化」こそ、中小企業のためのSEO対策
本記事では、新規コンテンツの作成に追われる多くのウェブ担当者が見落としがちな、「既存コンテンツの最適化」という強力なSEO戦略について、その重要性から具体的な実践方法、未来のトレンドまで解説しました。
最後に重要なポイントをもう一度おさらいします。
- なぜ「既存コンテンツ」の最適化かなのか
新規作成よりも少ないリソースで、短期間に大きな成果が期待できる費用対効果の高い戦略だから。 - 何から始めるか
検索順位が6位〜20位の「あともう一歩」のページから優先的に手をつける。 - どう進めるか
ユーザーの検索意図を深く理解し、情報の「鮮度」「正確性」「網羅性」を高める。 - 何を気をつけるか
文字数稼ぎやキーワードの詰め込みはNG。常にユーザーにとっての価値を最優先する。 - これからは
E-E-A-T(特に自身の経験)を重視し、AIにも分かりやすい構造化された情報提供を意識する。
2025年のSEO環境はもはや「量」で勝負する時代は終わりました。自社サイトという畑にすでに蒔かれている「種(既存コンテンツ)」を見つけ出し、丁寧に水をやり、光を当てることで、力強い芽を育て、大きな果実を実らせることができます。
もし「自社のどのコンテンツから手をつけるべきかわからない」「具体的な改善方法がわからない」「そもそも分析する時間がない」とお考えなら、外部の専門家を活用するのも1つの手です。
BaseTreeは埼玉県・群馬県の中小企業を中心に、データに基づいた論理的なSEO対策サービスを提供しています。 既存コンテンツの診断・最適化から、サイト全体のSEO戦略設計、新規コンテンツ制作まで、お客様の事業成長に貢献するためのあらゆる支援が可能です。
検索順位の向上とその先にある事業の成果にお悩みの方は、ぜひ一度私たちにご相談ください。無料相談にて、貴社サイトの課題と可能性を診断させていただきます。