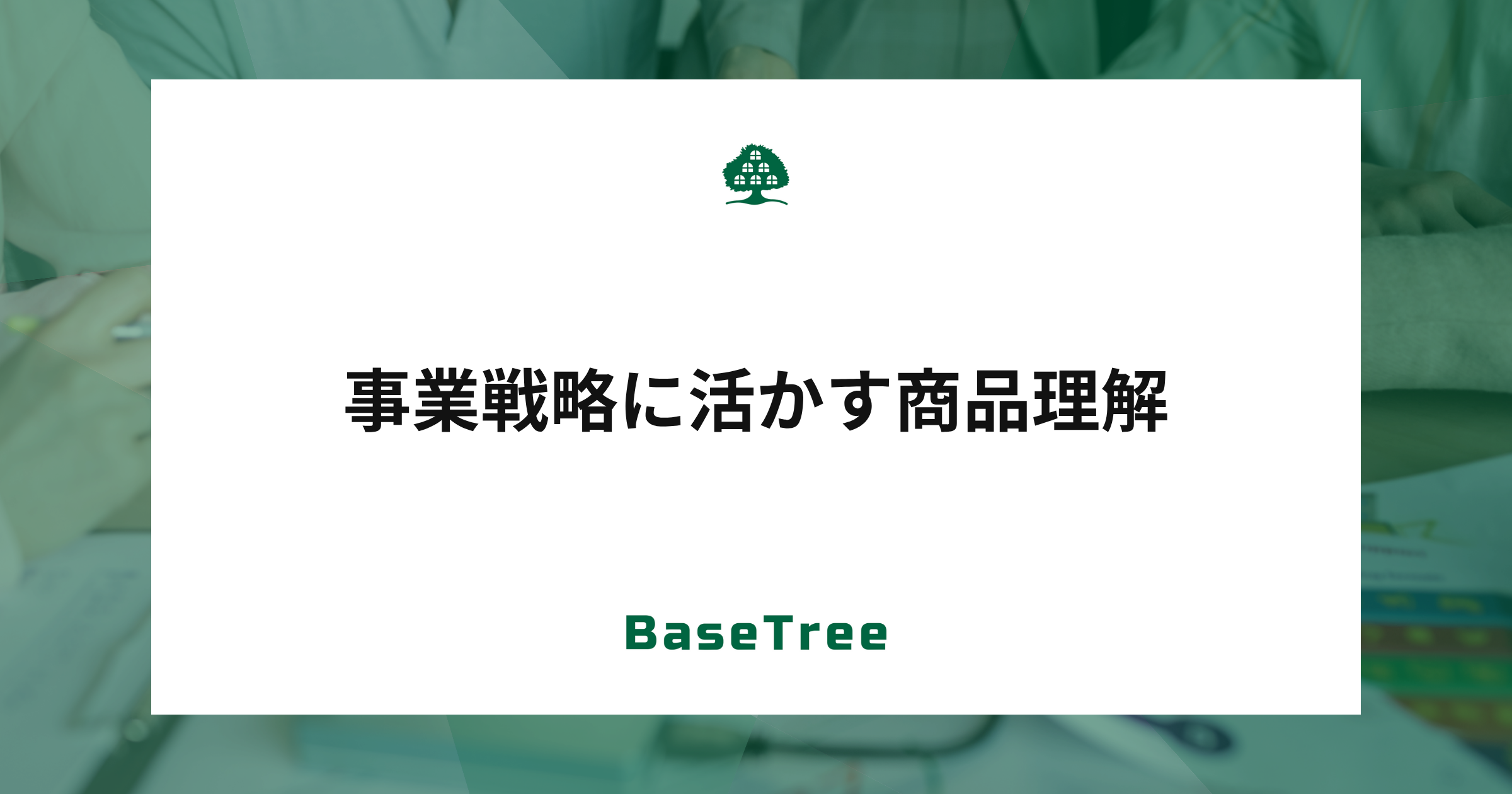事業戦略における商品理解の重要性とは?
事業やサービスの戦略を練る上で最も重要な要素の一つに自社の商品やサービスを深く理解することがあります。
単に「何を売っているか」を知るだけでは不十分なのです。
真の商品理解とは、価値・強み・市場での位置づけ・顧客にとってのメリットや買う意味を包括的に把握すること。
これが事業戦略の核心です。
2025年現在、市場環境は刻々と変化し顧客の期待も高度化しています。
このような状況下で自社の商品を正確に理解し、その理解を戦略に活かすことが事業やサービスの成功に直結します。
商品理解が不足しているとどんなに優れた戦略でも空回りします。
なぜなら、戦略の基盤となる最も重要な要素が欠けているからです。
では、なぜ多くの企業が商品理解に苦戦しているのでしょうか?
なぜ商品理解が難しいのか?
商品理解が難しい理由はいくつかあります。
最も一般的な理由は自社の商品やサービスに対する「思い込み」です。
長年同じ商品を扱っていると客観的な視点を失いがちです。
また、市場の変化に伴い商品の価値や位置づけも変わっていくもの。
昨日と同じ環境が今日も続くとは限りません。
特に2025年の現在、デジタルトランスフォーメーションの加速により商品の価値提案は急速に変化しています。
スマートフォンの台頭からメール→LINE→SNS、TVやチラシ→Youtubeへと目まぐるしい技術の進歩に伴って、顧客とのコミュニケーションの方法や、情報取得方法や手段も数年前とは大きく異なっているのではないでしょうか。
商品理解を難しくするもう一つの要因は組織内のサイロ化です。
ここでは情報の分断、細分化、専業化などを意味します。
情報共有が不足していると、営業部門/マーケティング部門/製品開発部門がそれぞれ異なる視点で商品を捉え、統一した商品理解が生まれません。
さらに、顧客の声を正確に捉えられていないことも大きな障壁です。
顧客が本当に求めているものと、企業が考える「顧客が欲しいもの」の間に、しばしばギャップが存在するのです。
これらの課題を乗り越え真の商品理解を達成するためのアプローチとして、体系的に事業やサービスを分析する「フレームワーク」があります。
貴社は商品理解のための「取り組み」をしていますか?
商品理解の基本フレームワーク
商品理解にはフレームワークの活用が効果的です。
本記事では2025年の市場環境に適した商品理解のための基本フレームワークを紹介します。
1. 商品の本質的価値の特定
商品やサービスが顧客にもたらす本質的な価値を明確にします。
単なる機能や特徴ではなく顧客の問題をどのように解決するか、あるいは顧客の生活や業務をどのように改善するかという観点から考えます。
BaseTreeの場合
例えば、「Webマーケティング戦略サービス」の本質的価値は「自社の価値を再発見し、その価値を最も必要とする顧客に確実に届けるための設計図を提供すること」です。
2. 顧客ペルソナとの関連付け
商品が対象とする具体的な顧客像(ペルソナ)を設定し、その顧客にとっての商品の意味を明確にします。ペルソナの課題、目標、行動パターンを理解することで、商品の価値をより具体的に捉えることができます。
埼玉北部や群馬県の企業でWebマーケティング戦略に悩んでいる状況を具体的にイメージすることで、提供すべき価値が明確になります。
3. 競合との差別化ポイントの明確化
市場における競合商品と比較して、自社商品の独自性や優位性を特定します。これは単なる機能比較ではなく、顧客にとっての価値の違いを明確にすることが重要です。
BaseTreeの戦略設計の特徴は、事業理解の深度、顧客理解の精度、市場理解の客観性、実行計画の実現性にあります。これらの要素が競合との差別化ポイントとなります。
商品理解を深めるための5つの方法
商品理解を深めるためには、多角的なアプローチが必要です。以下に、効果的な5つの方法を紹介します。
1. データ分析による客観的理解
顧客データ、売上データ、市場データなどを分析することで、商品の実際のパフォーマンスや市場での位置づけを客観的に把握します。感覚や印象ではなく、事実に基づいた理解を目指します。
例えば、検索キーワード分析を通じて顧客の検索行動を分析し、競合状況や市場規模を定量的に把握することで、勝てるキーワード領域を特定できます。
また、競合ベンチマークを行うことで、競合他社のデジタル戦略、強み・弱みを調査し、差別化できる領域と戦うべき土俵を明確化できます。
2. 顧客インタビューと行動観察
実際の顧客と直接対話し、商品の使用状況や感想、改善点などを聞き取ります。また、顧客が商品を使用する様子を観察することで、表面化していないニーズや課題を発見できます。
顧客の生の声を聞くことで、「SEOを外注したがアクセスが増えない」「LPを作っても成果が出ない」「広告費だけがかさんで手応えがない」といった具体的な悩みが見えてきます。
3. クロスファンクショナルな商品レビュー
営業、マーケティング、製品開発、カスタマーサポートなど、異なる部門のメンバーが集まり、それぞれの視点から商品を評価します。多様な視点を統合することで、より包括的な商品理解が可能になります。
事業モデル、商品特性、提供体制、組織体制など現在の経営資源を網羅的に棚卸しするためには、様々な部門の知見を集める必要があります。
これにより、強みとなる要素を客観的に整理し、中長期ビジョンの確認も行うことができます。
4. 競合分析と市場調査
競合商品の特徴や市場動向を調査し、自社商品の相対的な位置づけを把握します。これにより、差別化ポイントや改善点が明確になります。
検索データ、競合分析、業界トレンドなど市場における自社のポジションを客観的に把握することで、勝てる領域をデータに基づき選定できます。
5. 商品ジャーニーマッピング
顧客が商品を知り、購入し、使用し、リピート購入するまでの一連のプロセスをマッピングします。各段階での顧客の体験や感情を理解することで、商品の強みや改善点を発見できます。
認知から購入、リピートに至る顧客の行動パターンを分析し、各段階での課題と機会を特定することが重要です。
これらの方法を組み合わせることで、より深い商品理解が可能になります。あなたの会社では、どの方法を取り入れていますか?
事業戦略に商品理解を活かす具体的ステップ
商品理解を深めたら、次はそれを事業戦略に活かすステップです。以下に、具体的なプロセスを紹介します。
1. 商品価値の再定義と明確化
商品理解に基づいて、商品の本質的価値を再定義し、明確に言語化します。これが戦略立案の出発点となります。
長年事業を続けてきた企業には必ず「選ばれる理由」があるにも関わらず、それを明確に表現できていないケースが多く見られます。商品理解を通じて、この「選ばれる理由」を明確にすることが重要です。
例えば、BaseTreeのWebマーケティング戦略サービスの場合、「自社の価値を再発見し、その価値を最も必要とする顧客に確実に届けるための設計図を提供する」という本質的価値を明確にしています。
2. ターゲット顧客の再設定
商品理解に基づいて、最も価値を感じるターゲット顧客を再設定します。すべての顧客に等しく価値を提供するのではなく、特定のセグメントに焦点を当てることで、効果的な戦略が立案できます。
「誰に」「何を」「どのように」伝えるかが不明確なため、メッセージが抽象的になり成果につながらないケースが多く見られます。顧客設定が感覚的で、実際の顧客行動と乖離しているケースも少なくありません。
定性・定量データを組み合わせ、実際の顧客行動に基づいたターゲット顧客を設計することが重要です。想像ではなく事実に基づいた顧客理解を行うことで、より効果的な戦略を立案できます。
3. 差別化戦略の策定
商品の強みと競合分析に基づいて、市場での差別化戦略を策定します。これにより、競争優位性を確立し、持続的な成長を実現します。
強みや立ち位置、競合との違いが整理されておらず、戦うべき領域が定まっていないと、同質化した訴求で顧客に選択理由を提供できません。
競合分析を通じて戦うべき領域を特定し、優位性が活きる戦略を策定することが重要です。
4. マーケティングメッセージの最適化
商品理解に基づいて、顧客に響くマーケティングメッセージを開発します。商品の本質的価値を伝えるメッセージは、より高い反応率を生み出します。
客観的な分析により自社の強みを発見し、競合との明確な差別化ポイントを言語化することで、より効果的なマーケティングメッセージを開発できます。
すべての施策に論理的根拠を設け、「なぜその施策なのか」を明確にした戦略的アプローチを取ることが重要です。
5. 商品開発・改善の方向性設定
商品理解に基づいて、今後の商品開発や改善の方向性を設定します。顧客ニーズと自社の強みを踏まえた商品進化が、持続的な競争力につながります。
限られた予算内で最大の効果を生む施策の組み合わせを提案し、投資対効果を重視した現実的なプランを策定することが重要です。
効果・コスト・実現可能性を総合評価し、取り組むべき順序の明確化と根拠を提示することで、より効果的な商品開発・改善が可能になります。
商品理解を組織文化に根付かせる方法
商品理解は一度きりの取り組みではなく、組織文化として根付かせることが重要です。以下に、そのための方法を紹介します。
1. 定期的な商品レビューセッションの実施
四半期ごとなど定期的に、全社または部門横断で商品レビューセッションを実施します。市場の変化や顧客フィードバックを踏まえて、商品理解を常に更新します。
定量的な成果指標を設定し、継続的な改善サイクルを構築することで、データに基づく意思決定が可能になります。
戦略の背景と根拠を明文化し、関係者全員が同じ方向を向いて取り組める体制を構築することが重要です。
2. 顧客との継続的な対話の仕組み構築
顧客フィードバックを継続的に収集する仕組みを構築します。定期的な顧客満足度調査、ユーザーテスト、顧客インタビューなどを通じて、商品理解を常に更新します。
戦略を単なる資料で終わらせず、現場で使える実践的な設計図として提供し、実行まで継続的にサポートすることが重要です。
カスタマージャーニー、ペルソナ設計、強み分析、施策優先度、効果測定結果など、すべての資料と進捗をリアルタイムで確認可能にすることで、プロジェクトの透明性を確保できます。
3. 商品知識の共有と教育
商品に関する知識や理解を組織内で共有し、教育する仕組みを構築します。新入社員研修や定期的な勉強会などを通じて、全社員が商品理解を深める機会を提供します。
市場調査・競合分析・顧客データに基づいた客観的な戦略設計で、社内共有しやすい根拠ある戦略を提供することが重要です。
限られたリソースの中で最大の成果を出すための現実的で実践可能な戦略を設計し、全社員で共有することで、組織全体の商品理解が深まります。
4. 商品理解を評価指標に組み込む
社員評価や部門評価の指標に、商品理解の度合いや商品理解に基づく行動を組み込みます。これにより、商品理解が組織文化として定着します。
問い合わせ数、リード獲得数、コンバージョン率など、測定可能な数値目標を設定し、進捗を可視化することが重要です。
各施策のスケジューリングと、社内外のリソース配置を最適化し、実行可能性を担保した工程表を作成することで、商品理解に基づく行動が評価される仕組みを構築できます。
事例で学ぶ 商品理解が事業戦略を変えた瞬間
商品理解が事業戦略を大きく変え、成功につながった事例を紹介します。
ケーススタディ Webマーケティング戦略の再構築
ある中小企業は、Webマーケティングに多くの投資をしていたにもかかわらず、思うような成果が出ていませんでした。SEO対策、Web広告、SNSマーケティングなど、様々な施策を実施していましたが、売上には直結していませんでした。
そこで、BaseTreeのWebマーケティング戦略サービスを活用し、自社の商品理解から始める包括的なアプローチを採用しました。
まず、事業モデル、商品特性、提供体制、組織体制など現在の経営資源を網羅的に棚卸し。強みとなる要素を客観的に整理しました。また、中長期ビジョンの確認も行いました。
次に、顧客行動の可視化や最適なタッチポイント設計を行い、ターゲット顧客理解を深めました。認知から購入、リピートに至る顧客の行動パターンを分析し、各段階での課題と機会を特定しました。
さらに、検索キーワード分析や競合ベンチマークを通じて、市場における自社のポジションを客観的に把握。差別化できる領域と戦うべき土俵を明確化しました。
これらの商品理解に基づいて、限られた予算内で最大の効果を生む施策の組み合わせを提案。投資対効果を重視した現実的なプランを策定しました。
その結果、Webサイトのセッション数が206%増加し、コンバージョン数が232%増加するという成果を達成しました。商品理解に基づく戦略的なアプローチが、大きな成果につながった事例です。
あなたの会社でも、商品理解を深めることで、同様の成果が期待できるかもしれません。
2025年の商品理解トレンドと今後の展望
2025年現在、商品理解のアプローチにも新たなトレンドが生まれています。以下に、最新のトレンドと今後の展望を紹介します。
1. データドリブンな商品理解の進化
AIや機械学習の進化により、より高度なデータ分析が可能になっています。顧客行動データ、市場データ、競合データなどを統合的に分析し、より精緻な商品理解を実現するアプローチが主流になっています。
検索データ、競合分析、業界トレンドなど市場における自社のポジションを客観的に把握し、勝てる領域をデータに基づき選定する手法がより洗練されています。
2. 顧客共創型の商品理解
顧客を商品理解のプロセスに積極的に巻き込む「共創」アプローチが広がっています。顧客との対話や協働を通じて、より深い商品理解を実現する取り組みが増えています。
定性・定量データを組み合わせ、実際の顧客行動に基づいたターゲット顧客を設計する手法が進化しています。想像ではなく事実に基づいた顧客理解を行うことの重要性がより高まっています。
3. 持続可能性視点の商品理解
環境や社会への影響を考慮した商品理解が重要性を増しています。商品のライフサイクル全体を通じた環境負荷や社会的価値を理解し、それを戦略に反映させるアプローチが広がっています。
事業モデル、商品特性、提供体制、組織体制だけでなく、環境や社会への影響も含めた現在の経営資源を網羅的に棚卸しする取り組みが増えています。
4. クロスボーダー商品理解の重要性
グローバル化の進展により、異なる文化や市場における商品理解の重要性が高まっています。同じ商品でも、市場によって価値や位置づけが大きく異なることを理解し、それを戦略に反映させるアプローチが求められています。
埼玉北部や群馬県の企業だけでなく、グローバル市場を視野に入れた商品理解の重要性が高まっています。
5. 商品理解のデジタルツール進化
商品理解を支援するデジタルツールが急速に進化しています。顧客行動分析、競合分析、市場分析などを支援するツールが充実し、より効率的かつ精緻な商品理解が可能になっています。
MA(マーケティングオートメーション)、CMS、アクセス解析ツール、ABテストツールなど、商品理解を支援するツールの活用がより一般的になっています。
これらのトレンドを踏まえ、自社の商品理解アプローチを進化させることが、2025年以降のビジネス成功の鍵となるでしょう。
商品理解が事業戦略を成功に導く
本記事では事業戦略に活かす商品理解の方法論について解説してきました。
商品理解の重要性、難しさ、基本フレームワーク、深める方法、事業戦略への活かし方、組織文化への根付かせ方、成功事例、最新トレンドと展望など、多角的な視点から商品理解について考察しました。
2025年現在市場環境は刻々と変化し顧客の期待も高度化しています。
このような状況下では、自社商品を正確に理解し戦略に活かすことが事業・サービスの成功に直結します。
商品理解は一度きりの取り組みではなく継続的なプロセスです。
市場の変化や顧客ニーズの変化に合わせて常に商品理解を更新し戦略に反映させることが重要です。
BaseTreeのWebマーケティング戦略サービスは「自社の価値」を再発見し、その価値を最も必要とする顧客に確実に届けるための設計図を作成します。
事業理解からスタートし、データに基づいた論理的・構造的な戦略を設計します。
「やるべきこと」と「やらなくていいこと」を明確に区別し優先順位をつけ、限られたリソースでも着実に成果を生むWebマーケティングの設計図をつくります。
まずは自社の商品を客観的に見つめ直すところから始めてみてはいかがでしょうか。
より詳細なWebマーケティング戦略についてのご相談は、Webマーケティング戦略のページをご覧ください。
BaseTreeが皆様の課題解決をサポートします。