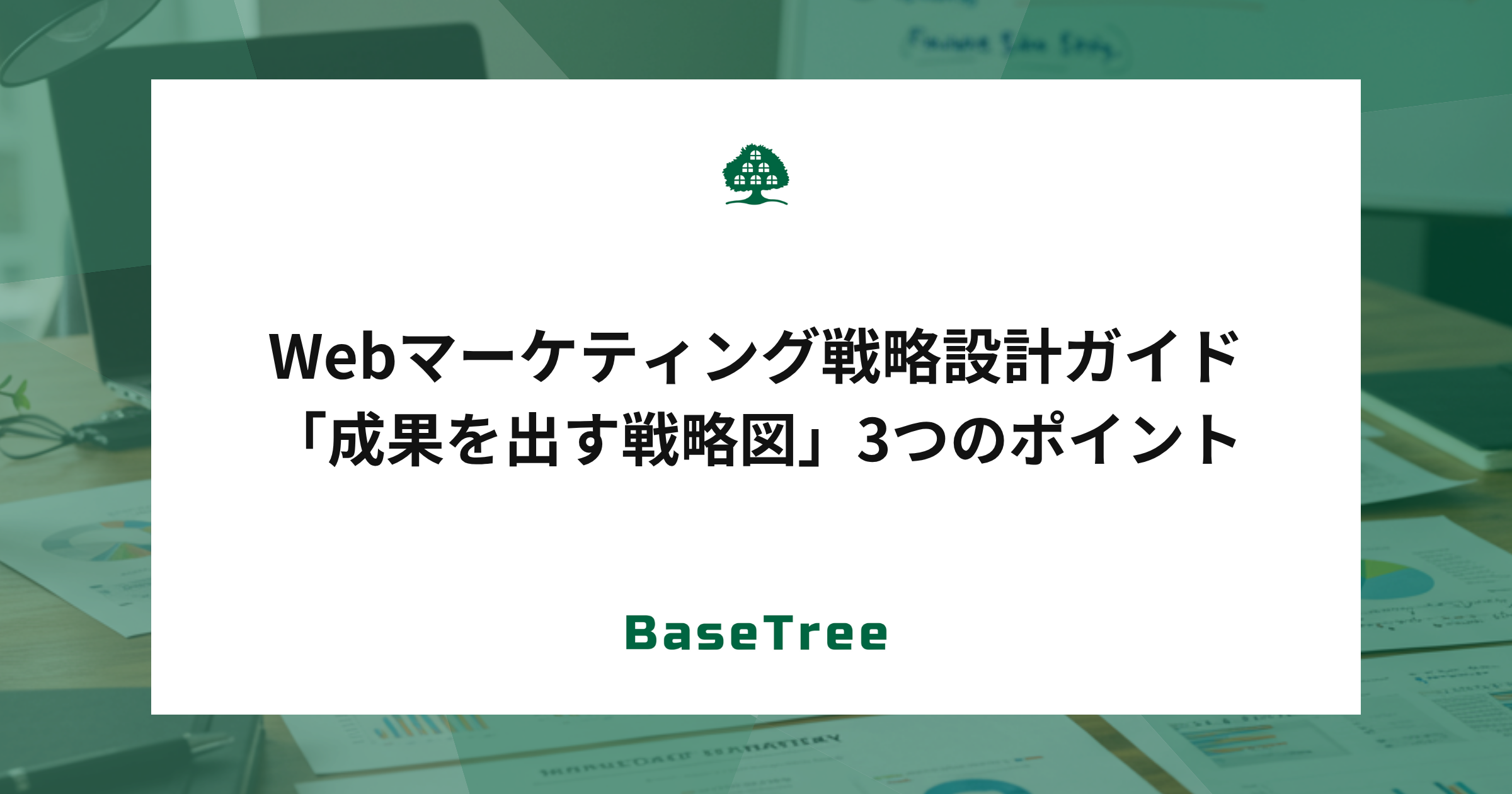「Webマーケティングは重要だとわかっているけど、どう戦略を立てればいいのかわからない…」
このような悩みを抱えている方は少なくありません。Webマーケティングの世界は日々変化し、何から手をつければいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。
実は成果を出すWebマーケティング戦略には明確な道筋があります。
それは「自社の強み」を理解し、「ターゲット顧客」を明確にし、「市場環境」を分析した上で、最適な施策を選択することです。
この記事では10年間のWebディレクターとして多様なクライアントの支援経験から、Webマーケティング戦略の立て方3つのポイントを解説します。
Webマーケティング戦略とは?
Webマーケティング戦略とは、「自社の価値」を再発見し、その価値を最も必要とする顧客に確実に届けるための設計図です。
多くの企業がWebマーケティングに取り組んでいますが、明確な戦略なく場当たり的に施策を実行しているケースが少なくありません。SEOを外注したけどアクセスが増えない、LPを作ったけど成果が出ない、広告費だけがかさんでいく…このような状況に陥っている企業は、根本的な「戦略」が欠けていることがほとんどです。

では、なぜ戦略が重要なのでしょうか?
それは限られたリソース(予算・人員・時間)で最大の成果を出すためです。「やるべきこと」と「やらなくていいこと」を明確に区別し、優先順位をつけ、リソースを効率的かつ効果的に投下する、筋道と順序と手段が明確なWebマーケティングが展開できるからです。
戦略がない状態でよく見られる問題点
- 目的と手段の混同(SEOやSNSが目的化してしまう)
- 顧客像の曖昧さ(誰に何を伝えたいのかが不明確)
- 強みや価値の言語化不足(なぜ選ばれるのかが伝わらない)
- 競合との差別化不足(同質的な訴求になってしまう)
- 施策の未整理(何から手をつけるべきかわからない)
- 成果基準の未設定(効果測定ができない)
戦略不在の問題を解決するためには、体系的にWebマーケティング戦略を立てる必要があります。
Webマーケティング戦略を立てる3つのポイント
Webマーケティング戦略の立てかたは以下の3つのポイントを抑えましょう。

ポイント1|事業理解・商品理解(自社の価値を明確にする)
Webマーケティング戦略の第一歩は、自社の事業と商品を深く理解すること。
表面的な理解ではなく、事業モデル、商品特性、提供体制、組織体制まで現在の経営資源を網羅的に棚卸しします。
- 事業の強み・弱み
- 提供している価値(顧客にとっての本質的なベネフィット)
- 競合との差別化ポイント
- 中長期的なビジョン
私が支援する時まず最初に行うのがこの「事業理解」です。
多くの企業が、内部に身を置くがゆえに当たり前すぎて、自社の強みを明確に言語化できていません。長年事業を続けてこられたということは必ず「選ばれる理由」があります。それを明確に表現できていない、把握できていないケースが多いのです。
ポイント2|ターゲット顧客理解(誰に価値を届けるのか)
次はターゲット顧客の理解です。
「誰に(Who)」「何を(What)」「どのように(How)」伝えるかが不明確だと、メッセージが抽象的になり結果的に成果につながりません。また自社の商品を必要としているすべてのターゲットに、一度に全てを伝えようとしてしまう問題もあります。
メインとなるターゲットは誰で、何を、どのように解決したいのか/して欲しいのか?まずはメインターゲットの理解を深めましょう。
メインターゲットの理解が深まりメッセージが明確になると、副次的にメインターゲット以外のターゲット(前述のすべてのターゲット)にも有効なメッセージになります。
ターゲット顧客理解のポイント
- 顧客行動の可視化(認知から購入、リピートに至るまでの道筋)
- 顧客の課題・ニーズの特定
- 顧客の情報収集方法の把握
- 最適なタッチポイントの設計

BtoB企業の場合は購買に至るまでのプロセスが複雑です。
現場の担当者が情報収集を始め、上司への報告、稟議、予算確保など、複数のステップと関係者が存在します。この購買プロセスを理解して各段階で必要な情報を提供します。
「BtoB企業の購買プロセスの57%は、営業担当者に会う前に終わっている」とも言われています。つまり、顧客は自社のWebサイトや各種コンテンツを通じて、すでに判断材料の半分以上を得ているのです。
だからこそ、顧客がどのような情報を求め、どのような判断基準で選択しているのかを理解することが、Webマーケティング戦略を練る上で欠かせません。
ポイント3|市場理解(環境分析と差別化)
次に市場環境を客観的に分析します。
自社の価値、顧客が求めることを理解した上で、競合状況や市場トレンドを調査するからこそ勝てる領域が見えてきます。
市場理解のポイント
- 検索キーワード分析(顧客の検索行動を把握)
- 競合ベンチマーク(競合他社のデジタル戦略、強み・弱みを調査)
- 市場規模と成長性の把握
- 業界トレンドの分析
検索キーワード分析はWebマーケティングにおいては特に重要です。
「顧客がどのような語句を用いて検索するのか?」を知ることで、顧客の悩みや関心事、自社の事業や商品に関する理解度を客観的に把握し推察できます。
各キーワードの検索ボリューム(検索数)や競合状況(アクセス数や掲載順位、Web広告出稿の有無)を分析することで、SEO対策の効果予測や優先順位付けができます。
競合分析では、単に「他社が何をしているか」を見るだけでなく、「なぜそれをしているのか」「どのような効果があるのか」まで深堀りすることが大切です。競合の強みと弱みを理解することで、自社の差別化ポイントを明確にできます。
Webマーケティング戦略に基づく施策選定と優先順位付け
3つのポイントを抑えた戦略の土台ができたら、次は具体的な施策を選定し優先順位をつけていきます。

効果的な施策選定の考え方
Webマーケティングの施策はSEO、リスティング広告、SNS、コンテンツマーケティング、メールマーケティングなど、選択肢は多岐にわたり。すべてを同時に実行することは、リソースの観点から現実的ではありません。
Webマーケティング施策選定のポイント
- 顧客接点(ターゲット顧客がよく利用するチャネルは?)
- 実現可能性(自社のリソースで継続できるか?)
- 投資対効果(コストに見合った成果が期待できるか?)
BtoB企業の場合、一般的にはSNSよりもSEOやコンテンツマーケティングの方が効果的なケースが多いです。なぜなら、ビジネスの意思決定者は特定の課題解決のために検索エンジンを使って情報収集することが多いからです。
一方、消費者向けの商品であれば、InstagramやTikTokなどのSNSを活用した視覚的なアプローチが効果的です。
「他社がやっているから」「トレンドだから」という理由だけで施策を選ぶのではなく、「なぜその施策を選ぶのか」という明確な根拠を持ってリソースを投下する施策を選定しましょう。
施策の優先順位付け
施策を選定したら、次は施策の中で優先順位をつけます。
限られたリソースを最大限に活用するためには「今すぐやるべきこと」「後でやること」「やらないこと」を明確に区別することが重要です。
優先順位付けの基準
- 効果の大きさ(成果への貢献度)
- 実現の難易度(技術的・人的リソース)
- 実施までの期間(すぐに始められるか)
- 継続性(一度きりか継続的か)
私の支援では、まず「基盤整備」から始めます。
Webサイトの改善、Google Analytics・Search Consoleの設定、Google Business Profileの最適化など、基本的な土台づくりです。
その上で短期的な成果が見込める施策(リスティング広告など)と中長期的な成果が期待できる施策(SEO、コンテンツマーケティングなど)を組み合わせていきます。
戦略的に施策を選ぶと「なぜこの施策をやるのか」が明確になっているので社内での合意形成もスムーズになり、効果測定の基準も明確になるためPDCAサイクルを回しやすくもなります。
Webマーケティング戦略の実行計画と成果指標の設定
戦略と施策が決まったら、次は具体的な実行計画と成果指標を設定します。
「何を」「いつまでに」「誰が」「どのように」実行するのかを明確にし、その効果をどう測定するかを決めておきましょう。
実行計画は戦略を現実のアクションに落とし込むための重要なステップです。

実行計画の策定
- タイムライン(短期・中期・長期のスケジュール)
- 担当者・役割分担
- 必要なリソース(予算・ツール・外部パートナーなど)
- マイルストーン(中間目標)
実行計画を立てるポイントは「現実的」であること。
理想的な計画を立ててもリソース不足で実行できなければ意味がありません。特に中小企業の場合、マーケティング専任担当者がおらず本業と並行して無理なく続けられる計画が重要です。
例えば「毎日SNSに投稿する」という計画は、専任担当者がいなければ継続は難しいのが実情です。まずは「週1回の投稿」から始め、SNS自体に慣れるなど現実的な目標設定が大切です。
また、リソースやノウハウ不足は外部パートナーとの協業も検討しましょう。すべてを内製化するのではなく、専門性が必要な領域は外部の力を借りることで効率的に進められます。
成果指標(KPI)の設定
「測定できないものは改善できない」と言われるように、Webマーケティングでは明確な成果指標を設定することが不可欠です。
成果指標を設定する際のポイント
- 最終目標(KGI)と中間指標(KPI)を区別する
- 測定可能な具体的な数値を設定する
- 施策ごとに適切な指標を選ぶ
- 定期的に測定・分析できる仕組みを作る
例えば最終目標が「問い合わせ数の増加」であれば、中間指標としては「Webサイトのセッション数(アクセス数)」「サービスページの閲覧数」「滞在時間」などが考えられます。
SEOであれば「対策キーワードの検索順位」「オーガニック流入数」、リスティング広告であれば「クリック率」「コンバージョン率」「獲得コスト」などが重要な指標となります。
成果指標を設定するときは見栄えの良い数字に惑わされず最終的なビジネス目標に紐づいた指標を選びましょう。例えばSNSのフォロワー数は増えても実際の問い合わせや売上に繋がらなければ意味がありません。
Webマーケティング戦略の実行と改善サイクル
Webマーケティング戦略は立てて終わりではありません。
実行し、効果を測定し、改善していくサイクルを回すことで、徐々に成果を高めていくことこそが最重要です。

PDCAサイクルの回し方
Webマーケティングの改善サイクルは、一般的にPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルで考えます。
- Plan(計画):戦略と施策の計画
- Do(実行):施策の実行
- Check(評価):効果測定と分析
- Act(改善):分析結果に基づく改善
PDCAサイクルを回すためのポイント
- 適切な頻度で効果を測定する(施策によって週次・月次・四半期など)
- データに基づいた客観的な評価を行う
- 小さな改善を積み重ねる(一度に大きく変えるのではなく)
- 成功・失敗の要因を深堀りし、次のアクションに活かす
例えばSEO対策なら月次で検索順位やオーガニック流入の推移を確認し、効果が出ているキーワードと出ていないキーワードを分析します。効果が出ているキーワードの特徴(検索ボリューム、競合状況、コンテンツの質など)を把握し次のコンテンツ制作に活かす、というのがPDCAサイクルです。
データ分析と意思決定
Webマーケティングの大きな強みはほぼすべての活動がデータとして測定できること。データを分析し客観的な事実に基づいて次のアクションを計画します。
データ分析のポイント
- 単なる数値の羅列ではなく、「なぜそうなったのか」の要因分析
- 複数の指標を組み合わせた総合的な判断
- 時系列での変化と外部要因(季節性、市場環境など)の考慮
- 定性的な情報(ユーザーの声、問い合わせ内容など)との組み合わせ

例えばWebサイトの直帰率が高い場合は「コンテンツが魅力的でない」と判断するのではなく、「どのページで」「どのような流入経路の場合に」直帰率が高いのかを分析します。検索キーワードとページ内容のミスマッチ、ページの読み込み速度、モバイル対応の問題など、様々な要因が考えられます。
データ分析に基づく意思決定は、「感覚」や「経験」だけに頼った判断よりも精度が高く組織内での合意形成もスムーズになります。
Webマーケティング戦略設計で成果を出す3つのポイント
Webマーケティング戦略の立て方で抑えておくべき3つのポイントを解説しました。
- 事業理解・商品理解:自社の価値を明確にする
- ターゲット顧客理解:誰に価値を届けるのかを明確にする
- 市場理解:環境分析と差別化を図る

このポイントを抑えた上で具体的な施策を選定し、優先順位をつけ、実行計画と成果指標を設定することで、実践的なWebマーケティングが展開できます。
重要なのは「戦略あっての施策」という考え方です。SEOやSNS、Web広告などの施策は、あくまでも目的を達成するための手段です。
目的と手段を混同せず「なぜその施策を選ぶのか」という明確な根拠を持つことが成果を創出し続ける上で重要です。
Webマーケティングは一度始めたら終わりではなく、PDCAサイクルに準じた継続的な改善を実践しましょう。
戦略を「つくって終わり」にせず、戦略〜実行まで一貫した取り組みを続けることで、Webマーケティング思考そのものが強力な経営資源となり継続的な成果を生み出します。
ぜひこの記事で紹介した内容を実践してみてください。
Webマーケティング戦略の立案から実行まで、専門的なサポートが必要な場合は、ぜひBaseTreeのWebマーケティング戦略サービスをご検討ください。
事業理解、顧客理解、市場理解から一緒に実践し、データに基づいた論理的・構造的な戦略設計で成果につながるWebマーケティングをサポートします。