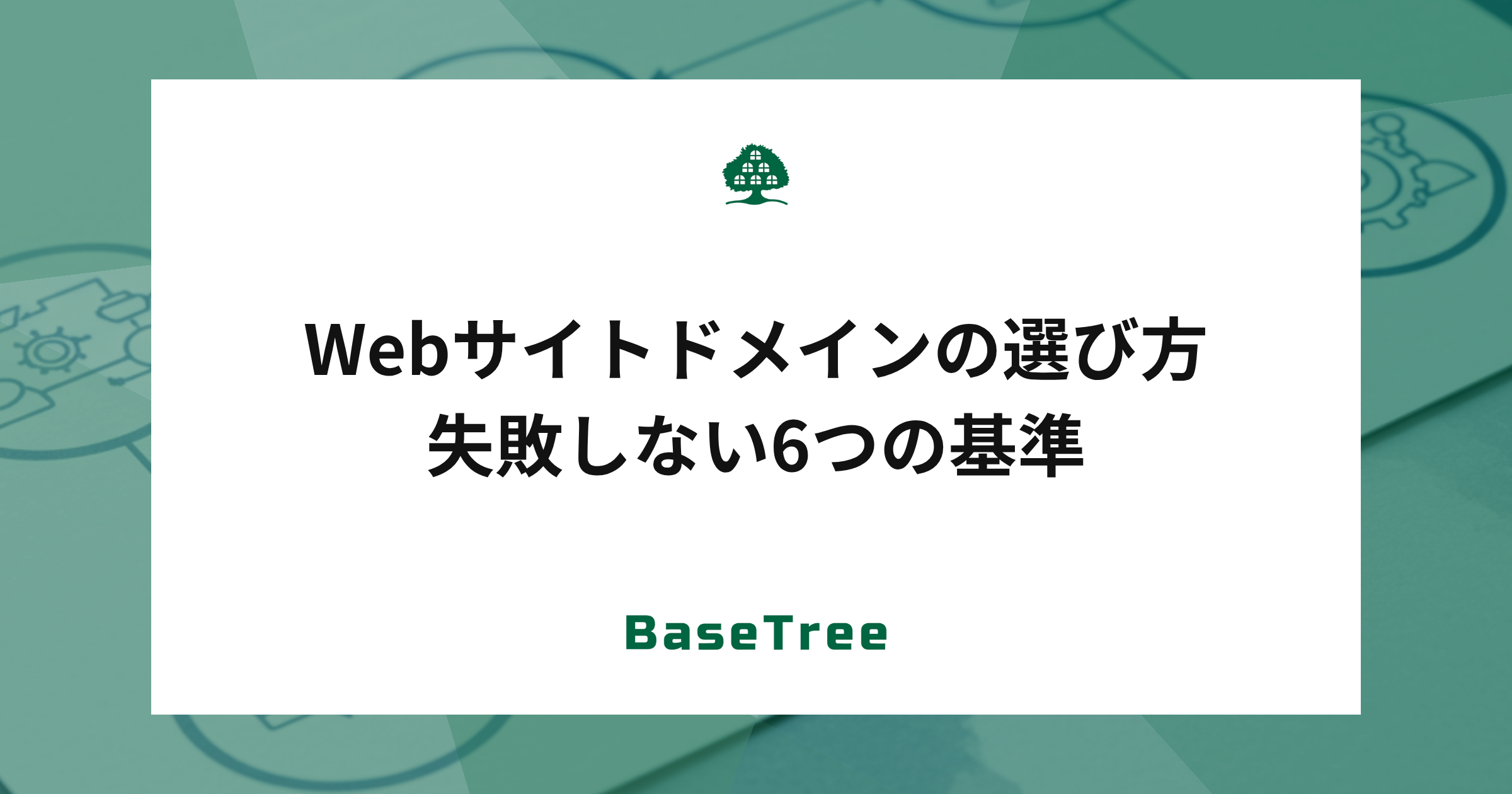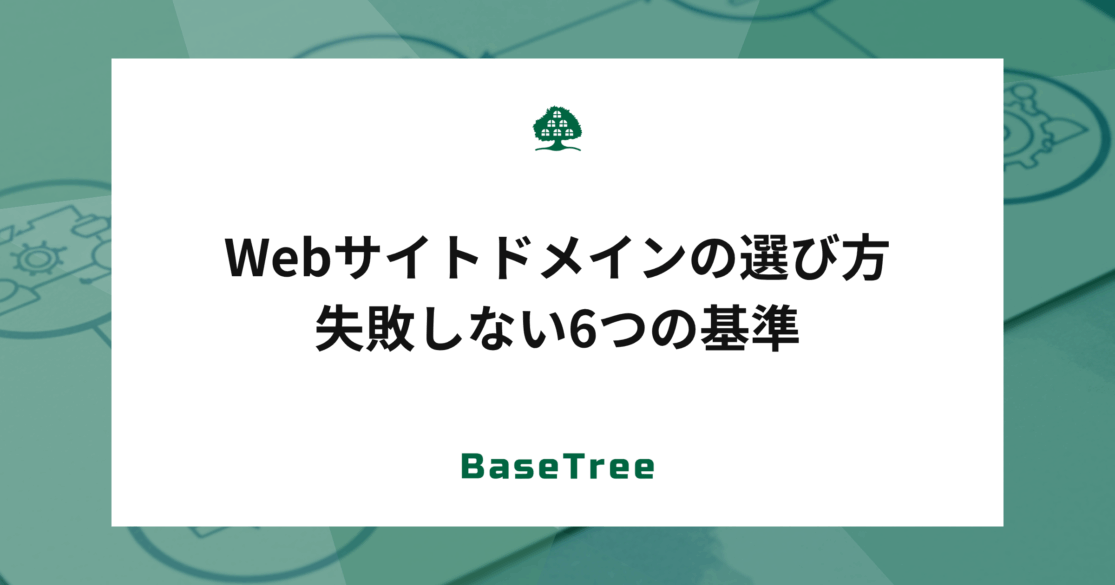
Webサイトのドメイン選びで失敗しないために知っておくべきこと
Webサイト制作で最初に決めなければならないのがドメイン名。ドメインはインターネット上の「住所」となり、一度決めたら簡単に変更できません。
「どんなドメインを選べばいいの?」「失敗しない選び方はあるの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
10年間WEBディレクターとして様々なクライアントのサイト制作に携わってきた経験からドメイン選びは見た目以上に重要です。選び方一つで印象や検索エンジンでの評価まで変わってきます。
この記事では、Webサイト制作のプロが失敗しないドメイン選びの6つの基準と、ドメインの基礎知識から実践的な選び方まで解説します。
これから新たにWebサイトや独自ドメインをお考えの方、きっとぴったりなドメインを選べるようになりますよ。
ドメインとは?インターネット上の「住所」の基本を理解しよう
まずはドメインの基本から。ドメインとはインターネット上のWebサイトやメールアドレスを識別するための「住所」のようなものです。
例えば「https://example.com」というURLの場合、「example.com」の部分がドメイン名にあたります。メールアドレスでは「info@example.com」の「@」以降の部分がドメインです。
ドメインがあることで、数字の羅列であるIPアドレス(例:192.168.0.1)を覚える必要がなく、人間にとって分かりやすい文字列でWebサイトにアクセスできるようになっています。
ドメインの構成要素を理解する
ドメインは複数の要素から構成されています。「example.co.jp」というドメインを例に説明すると
- 「jp」:トップレベルドメイン(TLD)- 国や用途を表す
- 「co」:セカンドレベルドメイン – 組織の種類を表す
- 「example」:サードレベルドメイン – 組織や個人が自由に決められる部分
トップレベルドメインは、ドメインの種類を決める重要な要素。「.com」や「.jp」など、選ぶ種類によって印象や信頼性が変わってきます。
独自ドメインと無料ドメインの違い
ドメインには大きく分けて「独自ドメイン」と「無料ドメイン」があります。
独自ドメインは自分で取得したオリジナルのドメインで、「example.com」のように自由に文字列を設定できます。一方、無料ドメインは、レンタルサーバや無料ブログサービスから提供されるもので、「example.●●●.com」のような形式になります。
本格的にビジネスでWebサイトを運用するなら独自ドメインを取得してください。独自ドメインには以下のようなメリットがあります。
- ブランド価値と信頼性の向上
- SEO(検索エンジン最適化)で有利になる
- サービスに依存せず長期的に同じURLを維持できる
- 独自のメールアドレスが作れる(例:info@独自ドメイン)
無料ドメインは初期費用がかからない点が魅力ですが、ブランド構築や長期的な運用を考えると最初から独自ドメインを取得する方が賢明です。
無料ドメインから独自ドメインに切り替えると、Webサイトの転送設定をしたり、名刺を刷り直したり、届出のホームページ欄を修正したりと「変更処理」が後々必要です。
失敗しないドメイン選びの6つの基準
では、具体的にどのようにドメインを選べばいいのでしょうか?10年間のWEB制作経験から「失敗しないドメイン選びの6つの基準」をご紹介します。
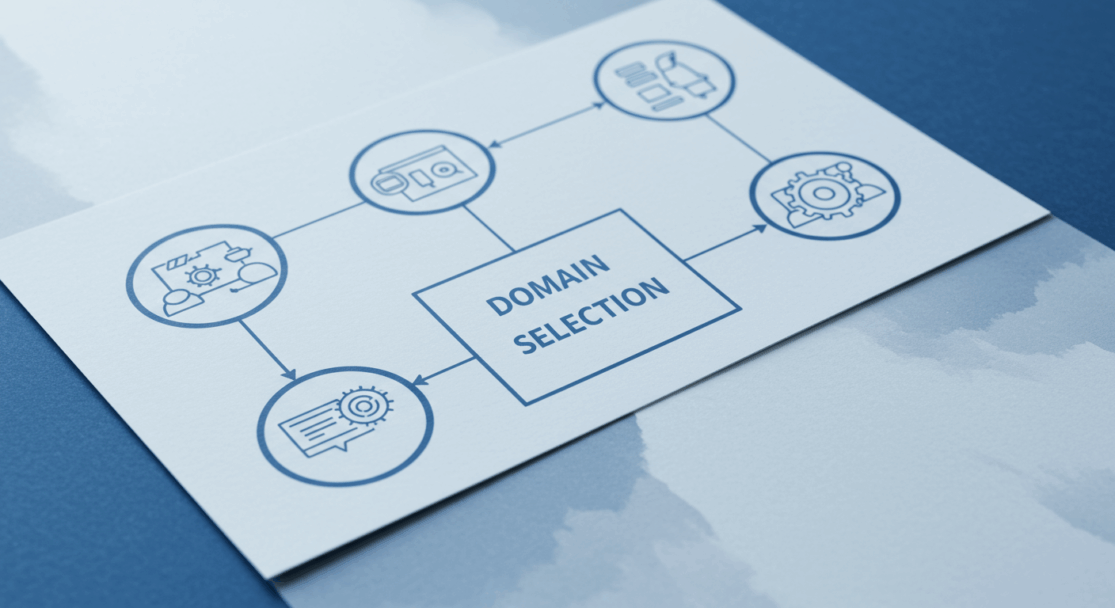
1. 短くて覚えやすいドメイン名を選ぶ
ドメイン名は短くシンプルで覚えやすいものを選びましょう。長すぎるドメイン名は打ち間違いの原因になりますし、覚えてもらいにくくなります。
理想的なのは、10〜15文字程度のドメイン名です。例えば「amazon.com」や「google.com」のように、短くて印象に残りやすいドメイン名が理想的です。
2. ビジネスやブランドを反映したドメイン名にする
ドメイン名は、あなたのビジネスやブランドを反映したものにしましょう。会社名やサービス名をそのまま使うのが一般的ですが、それが難しい場合は、ビジネスの特徴や提供する価値を表す言葉を選びましょう。
例えば、花屋なら「flower-○○.com」、IT企業なら「○○tech.com」のように、一目でどんなビジネスかわかるドメイン名が理想的です。
3. 適切なトップレベルドメイン(TLD)を選ぶ
トップレベルドメインの選択も重要です。主なトップレベルドメインには以下のようなものがあります。
- .com:商業組織向け(最も一般的)
- .net:ネットワーク関連組織向け
- .org:非営利組織向け
- .jp:日本国内向け
- .co.jp:日本の企業向け
- .or.jp:日本の非営利組織向け
- .shop:ショップ・小売業向け
- .info:情報提供サイト向け
日本国内でビジネスを展開するなら「.jp」や「.co.jp」の信頼性が高いです。特に法人の場合は「.co.jp」がおすすめです。国内外問わずビジネスを展開するなら「.com」が無難な選択肢です。
業種や目的に合わせて最適なトップレベルドメインを選びましょう。
4. 将来性を考慮したドメイン名にする
ビジネスは成長し変化していくものです。現在の事業内容だけでなく、将来の展開も考慮したドメイン名を選びましょう。
例えば現在は特定の商品だけを販売していても将来的に取扱商品を増やす可能性があるなら、特定の商品名をドメインに使うのは避けた方が無難です。
同様に地域限定のビジネスでも将来的に展開エリアを広げる可能性があるなら、特定の地名をドメインに含めるのは再考した方がいいかもしれません。
5. 商標権や著作権に配慮する
他社の商標や著作物に類似するドメイン名は避けましょう。知らずに他社の商標に似たドメインを取得してしまうと、後々トラブルになる可能性があります。
ドメインを決める前に類似の商標がないか特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)などで確認してください。
また有名企業や商品名を含むドメインを取得すると、商標権侵害で訴えられるリスクもあります。自社の正当なビジネスを表すオリジナルのドメイン名を考えましょう。
6. 数字やハイフンの使用は最小限に
数字やハイフンを使ったドメイン名は、口頭で伝える際に誤解を招く場合があります。例えば「2」と「to」、「4」と「for」など、発音が似ている場合は注意が必要です。
ハイフンも多用すると覚えにくくなりますし打ち間違いの原因にもなります。できるだけシンプルなドメイン名を心がけましょう。
どうしても数字やハイフンを使いたい場合は、最小限にとどめることをおすすめします。
ドメインの種類と特徴を徹底比較
ドメインにはさまざまな種類があり、それぞれ特徴や用途が異なります。ここでは主要なドメインの種類と特徴を比較してみましょう。
分野別トップレベルドメイン(gTLD)の特徴
分野別トップレベルドメイン(gTLD)は用途別に分かれており、世界のだれでも登録が可能なドメインです。主なgTLDとその特徴は以下の通りです。
- .com:最も一般的で認知度が高い。商業サイトに最適
- .net:ネットワーク関連のサイトに適しているが、現在は用途を問わず広く使われている
- .org:非営利組織向けだが、制限はなく誰でも取得可能
- .info:情報提供サイト向け。比較的取得しやすい
- .biz:ビジネス用途向け
2012年以降は「.shop」「.app」「.blog」などより具体的な用途を表す新gTLDも多数登場しています。これらは特定の業種やサービスに特化したドメインとして活用できます。
国コードトップレベルドメイン(ccTLD)の特徴
国コードトップレベルドメイン(ccTLD)は国や地域を表すドメインです。日本のccTLDである「.jp」には以下のような種類があります。
汎用型JPドメイン
- 汎用JPドメイン(.jp):日本に住所を持つ個人・法人・組織なら誰でも取得可能
属性型JPドメイン
- .co.jp:日本の会社向け(法人格が必要)
- .or.jp:日本の非営利組織向け
- .ne.jp:日本のネットワークサービス提供者向け
- .ac.jp:日本の教育機関向け
- .go.jp:日本の政府機関向け
- 地域型JPドメイン(.tokyo.jp、.osaka.jp など):各都道府県に関連する組織・個人向け
特に「.co.jp」は日本の法人のみが取得できるため信頼性が高く、ビジネス目的のサイトとして最適です。
新gTLDの登場と活用法
近年では従来の「.com」や「.net」以外にも、様々な新しいトップレベルドメイン(新gTLD)が登場しています。
- .shop:ショップ・小売業向け
- .blog:ブログサイト向け
- .app:アプリケーション関連向け
- .tech:テクノロジー関連向け
- .design:デザイン関連向け
- .online:オンラインビジネス向け
- .tokyo:東京関連向け
新gTLDはビジネスの内容や特徴をより明確に表現できるメリットがあります。例えばECサイトなら「.shop」、テクノロジー企業なら「.tech」というように、業種や提供するサービスに合わせてドメインを選ぶとURLだけでサイトの内容を伝えることができます。
ただし新gTLDは「.com」などの従来のドメインに比べて認知度がまだ低いため、ユーザーに馴染みがなく覚えづらい可能性があります。新gTLDドメインを選択する際は、ターゲットとなる顧客層や業界の傾向も考慮しましょう。
ドメイン取得の手順と注意点
ドメインの種類と特徴を理解したところで、実際のドメイン取得手順と注意点を見ていきましょう。

ドメイン取得の基本的な流れ
ドメインを取得する基本的な流れは以下です。
- 希望するドメイン名を決める
- ドメイン取得サービスで空き状況を確認する
- 利用規約に同意し、必要情報を入力する
- 料金を支払い、申し込みを完了する
- 取得完了後、ネームサーバーの設定を行う
特に「.co.jp」などの属性型JPドメインを取得する場合は、法人格の証明書(登記簿謄本など)が必要になるので注意してください。新規事業や新サイト立ち上げなど他のプロモーションとの兼ね合いで厳密な公開日の指定がある場合は、前もってドメイン取得を進めましょう。
ドメイン取得サービスの選び方
ドメインを取得するにはドメイン取得サービス(レジストラ)を利用します。主なドメイン取得サービスには以下のようなものがあります。
主なドメイン取得サービス(レジストラ)
- お名前.com
- ムームードメイン
- エックスドメイン
- さくらインターネット
ドメイン取得サービス(レジストラ)選びのポイント
- 料金(初期費用と更新料)
- 管理画面の使いやすさ
- カスタマーサポートの充実度
- Whois情報公開代行サービスの有無
- 自動更新機能の有無
レンタルサーバー(Webサイトやメールの器)と同じ会社でドメインを取得すると、Webサイトの設置や公開、メールアドレスの発行や受送信詳細設定などが容易になる場合が多いです。基本的にはレンタルサーバーとドメインは同じ会社をご案内します。
ドメイン取得時の注意点
- Whois情報公開
ドメイン所有者の情報は原則公開されます。個人情報を守るためにWhois情報公開代行サービスの利用を検討しましょう。 - 更新忘れに注意
ドメインは定期的に更新が必要です。更新を忘れるとドメインが失効し他者に取得される可能性があります。 - 複数のTLDを取得する
主要なドメイン(example.com)だけでなく、類似ドメイン(example.net、example.jpなど)も可能であれば取得しておくとブランド保護になります。 - ドメイン移管の手続き
ドメイン管理サービスを変更する場合(お名前.com → エックスサーバーなど)、ドメイン移管の手続きが必要になります。手続きには時間がかかるため計画的に行いましょう。
特に更新忘れには注意が必要です。多くのサービスでは期日が来ると指定のクレジットカード・銀行口座から自動で引き落とされる「自動更新設定」が可能なので、重要なドメインは自動更新を有効にしておくことをおすすめします。
中小企業におけるドメイン選びのポイント
- 地域性を活かす
地域密着型のビジネスなら地域名を含めたドメインも効果的
(saitama-xxx、gunma-xxxなど) - 信頼性を重視する
法人なら「.co.jp」の取得・運用がWebの世界では信頼性に影響します - シンプルさを優先
難しい言葉や造語は避け覚えやすさ(入力のしやすさ)を重視 - 競合と差別化
同業他社のドメインと酷似しないように注意 - 将来の拡大を考慮
現在の事業だけでなく将来の展望も視野に入れる
私が見てきた限りでは、「最初はどんなドメインでもいい」と考えていた企業も、後になって「もっと慎重に選べばよかった」と後悔するケースが少なくありません。
ドメインは一度決めたら簡単に変更しづらい重要な要素。じっくり検討して長期的な視点で選ぶことをおすすめします。
SEOを考慮したドメイン選びのテクニック
ドメイン選びはSEO(検索エンジン最適化)にも影響します。ここではSEOを考慮したドメイン選びのテクニックを紹介します。
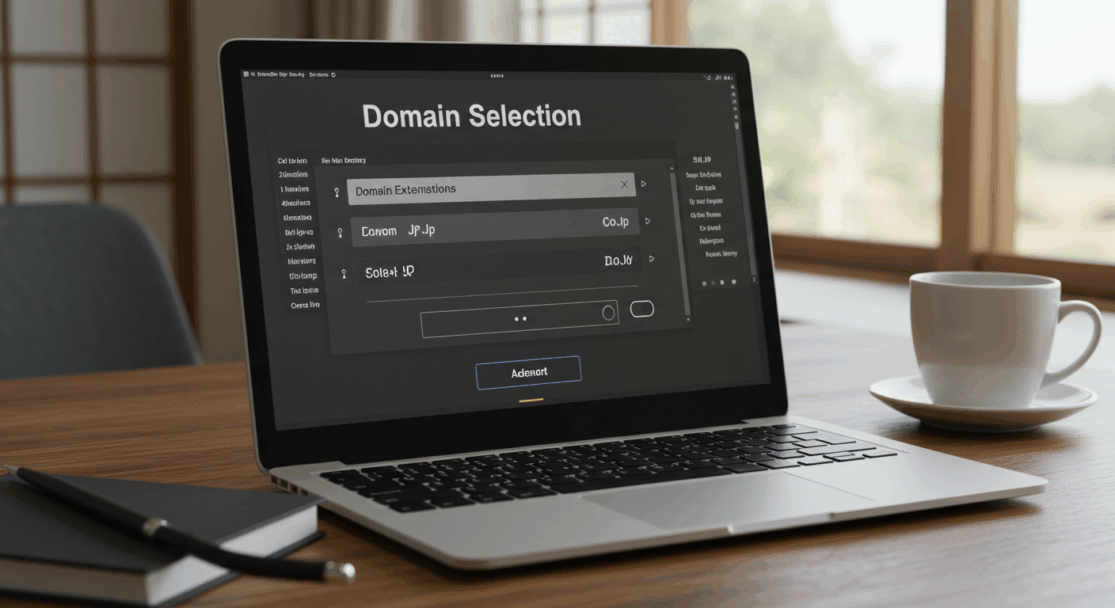
キーワードを含めたドメイン名の効果
かつては、ドメイン名にキーワードを含めることがSEOに大きく影響すると言われていました。例えば、「tokyo-seo-service.com」のようなキーワード入りドメインです。
現在のGoogleのアルゴリズムではドメイン名に含まれるキーワードの重要性は以前ほど高くありません。それでも適切に使用するとメリットがあります。
- ユーザーにサイトの内容が伝わりやすい
- アンカーテキスト(リンクテキスト)として自然に使われやすい
- ブランド認知とキーワード認知を同時に高められる
キーワードを詰め込みすぎるとスパム的な印象を与えてしまう可能性があるので注意が必要です。
ドメインの歴史と評価の関係
ドメインの運用歴はSEOに影響します。長年運用されているドメインは新規ドメインよりも信頼性が高いと評価される傾向があります。
可能であれば「すでに運用歴のあるドメインを取得する」のも一つの戦略です。ただし、そのドメインが過去にスパム行為などで評価を落としていないか確認することが重要です。
ドメインの過去の評価を確認するには、以下のような方法があります。
- Wayback Machineでドメインの過去のコンテンツを確認する
- バックリンク分析ツールで被リンクの質を確認する
- Google Search Consoleの過去データがあれば確認する
地域名を考慮したドメイン選び
地域に根ざしたビジネスを展開している場合、地域名を含めたドメインや地域別のトップレベルドメインを選ぶことで、ローカルSEOに有利になる可能性があります。
例えば
- 「tokyo-○○.com」のように地域名を含める
- 「○○.tokyo.jp」のような地域型JPドメインを使用する
特にGoogleマイビジネスと連携させることで、地域検索での表示順位向上が期待できます。
ただし、将来的に事業エリアを拡大する可能性がある場合は、特定の地域名をドメインに含めることで制約になる可能性もあるので慎重に検討しましょう。
Webサイトのドメインは、事業やWebサイトの目的に合わせて選ぼう
ドメイン選びはWeb上の住所となる重要な決断です。この記事でご紹介した6つの基準とチェックポイントを参考にあなたのビジネスやブランドにぴったりのドメインを選んでください。
最後に「失敗しないドメイン選びの6つの基準」をおさらいしておきましょう。
- 短くて覚えやすいドメイン名を選ぶ
- ビジネスやブランドを反映したドメイン名にする
- 適切なトップレベルドメイン(TLD)を選ぶ
- 将来性を考慮したドメイン名にする
- 商標権や著作権に配慮する
- 数字やハイフンの使用は最小限に
ドメインは一度決めたら簡単には変更しづらいもの。時間をかけて検討し長期的な視点で選ぶことをおすすめします。
また重要なドメインは複数のTLDで取得しておくとブランド保護になります。例えばメインで「example.com」を使うなら、「example.jp」や「example.net」も合わせて取得しておくと良いでしょう。
あなたのWebサイトが成果に繋がるか否かは、最適なドメイン選びからすでに始まっています。
Webサイト制作やドメイン選びでお悩みの方はぜひBaseTreeにご相談ください。
あなたのビジネスに最適なドメイン選びから、Webサイト制作、運用まで一貫してサポートします。
詳細はBaseTreeのWebサイト制作ページをご覧ください。