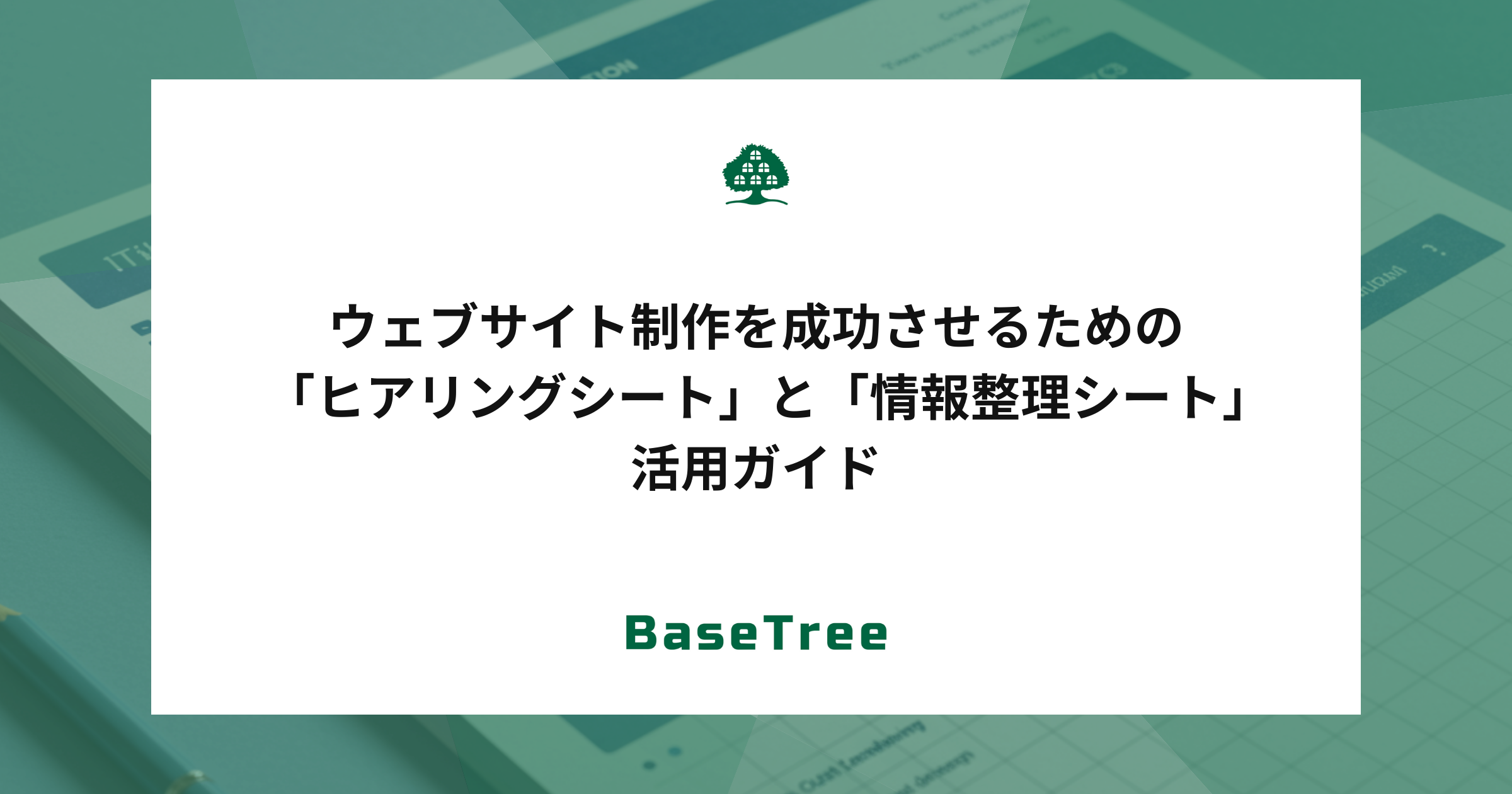ウェブサイト制作の成功はクライアントの要望を正確に把握し、情報を戦略的に整理することから始まります。しかし、多くの制作現場ではこの最初のステップが疎かになりがちです。
- 結局何をしている会社かわからない
- 営業トークとWebサイトの内容が噛み合わない
- ユーザーが欲しい情報にたどり着けない
このような「見られているけど伝わらない」Webサイトが生まれる根本原因は、戦略と理解の欠如、つまり質の高いヒアリングと情報整理ができていないことにあります。
この記事では、10年間WEBディレクターとして様々な案件に携わった経験から、すぐに使えるヒアリングシートと、成果を生むサイトに不可欠な情報整理シートのテンプレートと活用法を徹底解説します。
これからWeb制作を依頼する方も、受注する方も、ぜひ参考にしてみてください。
なぜウェブサイト制作に「ヒアリング」と「情報整理」が不可欠なのか?
Webサイト制作でいきなりデザインや原稿作成に着手するのは失敗への近道です。なぜなら、情報が整理されていないWebサイトは、ほぼ確実に成果が出ないからです。ユーザーは欲しい情報にたどり着けず、運営側は更新の方向性を見失い、結果として「ただ作っただけのWebサイト」になってしまいます。
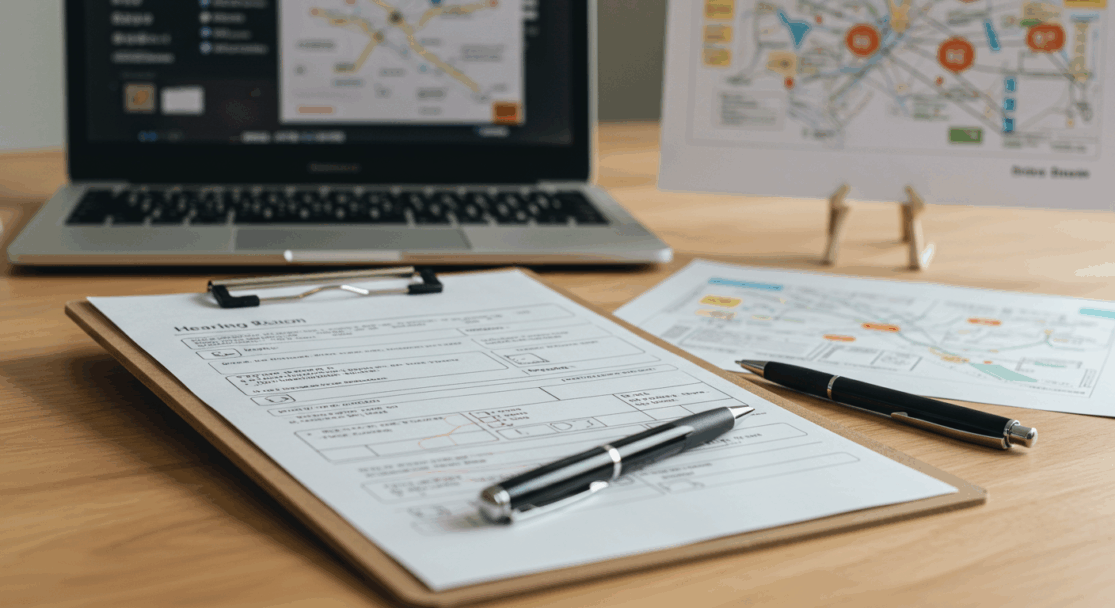
ウェブサイト制作の成功率を高める「ヒアリングシート」の重要性
ヒアリングシートはご要望や目的、ご予算、納期などを事前に整理し、制作要件を明確にするためのアンケートです。その重要性は、主に3つあります。
1. 認識のズレを防止する
クライアントと制作者の間で認識のズレが生じると、後々大きなトラブルになりかねません。「こんなはずじゃなかった」「言った・言わない」というトラブルを防ぐためにも、要件を文書化することが重要です。
口頭だけのヒアリングでは約7割のプロジェクトで認識のズレが発生しますが、詳細なヒアリングシートを使えば、そのリスクを2割以下に抑えることができます。
2. 効率的に必要な情報収集ができる
Web制作に必要な情報は多岐にわたります。デザイン、機能、コンテンツ、予算、納期など、聞くべき項目を事前に整理しておくことで、漏れのない効率的な情報収集が可能になります。
特に初めてWebサイトを制作するクライアントの場合、何を伝えればよいのかわからないことも多いものです。ヒアリングシートがあれば、必要な情報を順序立てて提供してもらえます。
3. プロジェクトの成功確率を高める

詳細なヒアリングを行うことでクライアントの本当のニーズや課題が見えてきます。
表面的な要望だけでなく、その奥にあるクライアント自身も気づいていない本質的な課題を明らかにし理解することで、当初の想定以上の成果を上げるより効果的なWebサイトが提案できます。
成果を引き出す!ウェブサイト制作に必須のヒアリング7項目
具体的にどのような質問を準備すればよいのでしょうか?
数多くのサイト制作経験から、プロジェクトの方向性を決める特に重要な7つのヒアリング項目をご紹介します。
1. 事業の本質を理解するための質問
ウェブサイト制作の土台となる、企業の強みや独自性を浮き彫りにします。
- 「今までで一番印象に残っている取引(成功事例)は何ですか?」
- 「その取引が始まったきっかけは何でしたか?」
- 「お客様は御社のことを何屋さんだと思っていますか?」
- 「創業のきっかけや理念について教えてください」
特に「印象に残っている取引」についての質問は、企業の強みや独自性を浮き彫りにする上で非常に効果的です。成功事例の背景には、その企業ならではの価値提供の形があるからです。

2. 顧客理解のための質問
理想的な顧客像(ペルソナ)を具体化し、その課題や購買行動を理解します。
- 「理想的なお客様はどのような方ですか?(年齢、性別、職業、悩みなど)」
- 「お客様が御社を選ぶ決め手は何だと思いますか?」
- 「お客様からいただく質問や問い合わせで多いものは何ですか?」
- 「お客様が抱えている課題や悩みは何だと思いますか?」
Webサイトの最終的な目的は顧客とのコミュニケーションです。
「顧客理解」の質問を通じて、ペルソナ(理想的な顧客像)を具体化し、そのペルソナが抱える課題や購買行動を理解することが重要です。
ペルソナを具体的に想定することはデザインやコンテンツを決める上でも有用です。年齢層、性別、職業、興味関心、インターネットリテラシーなど、できるだけ詳細に把握しましょう。例えば、高齢者向けのサービスであれば、文字サイズを大きくしたり、ナビゲーションをシンプルにしたりする配慮が必要です。ペルソナも業界知識に長けた専門家であれば(プロ向けであれば)、専門用語を使っても問題ないでしょう。
3. 競合理解のための質問
競合との差別化を図り、業界での立ち位置を明確にします。
- 「主な競合他社はどこだと考えていますか?」
- 「競合と比較した時の御社の強みは何ですか?」
- 「競合のWebサイトで参考になる点や、逆に改善すべき点はありますか?」
競合分析は感情的な評価ではなく、事実に基づく客観的な分析を心がけましょう。
競合他社サイトを分析することで、業界の標準やトレンドを把握できます。また、競合サイトの良い点を取り入れつつ、改善点を克服することで、差別化を図ることができます。
ただし、単に「競合サイトを教えてください」と聞くだけでは不十分です。「どの点が良いと思うか」「どの点に不満を感じるか」まで具体的に聞き出すことで、クライアントの好みや価値観も理解できます。
4. ウェブサイトの目的と期待する成果
制作の方向性を定めるため、ウェブサイトのゴールを具体的に設定します。
- 「Webサイトで最も達成したい目標は何ですか?(認知度向上、問い合わせ増、採用強化など)」
- 「目標を達成したと言える具体的な数値目標はありますか?(例:月間問い合わせ数2倍、採用応募30%増など)」
- 「現在のWebサイト(もしあれば)の課題は何ですか?」
目標が「問い合わせ増加」なのか「採用強化」なのか「ブランディング」なのかによって、サイト設計は大きく変わってきます。
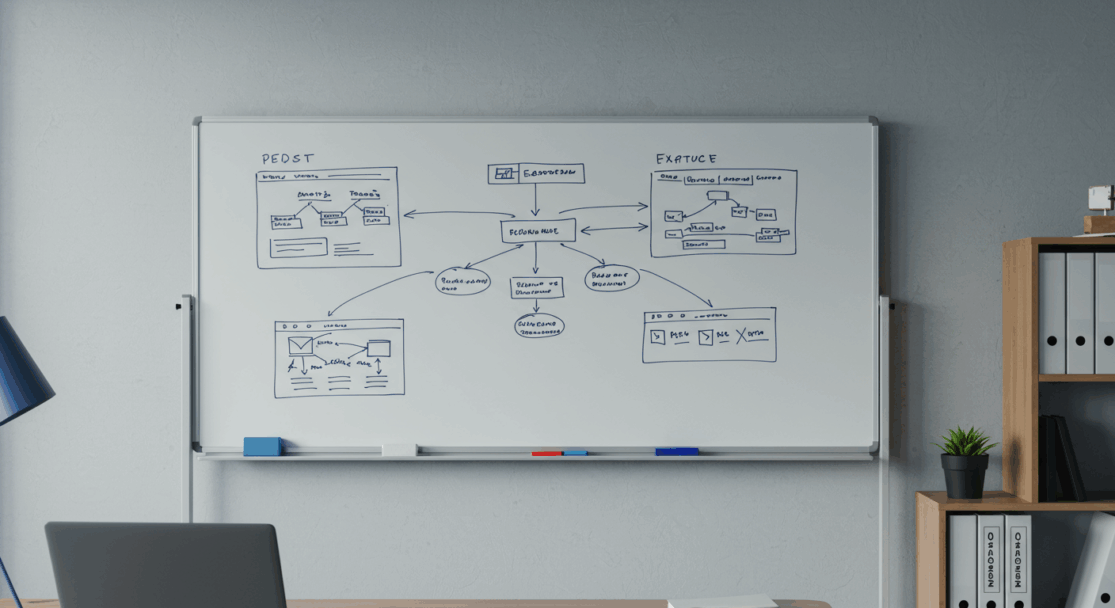
「月間問い合わせ数を現状の2倍にしたい」「サイト経由の採用応募を30%増やしたい」など、目的を達成したと言うことができる具体的な数値、すなわち「目標数値」を設定しましょう。アクセス数、問い合わせ数、コンバージョン率など、具体的な指標を設定しておくことで、サイト公開後の評価がしやすくなります。定期的な打ち合わせの実施や改善提案の機会なども事前に取り決めておくと、長期的な関係構築につながります。
Webサイトの効果を測定するためのアクセス解析や、検索エンジンからの流入を増やすためのSEO対策についても確認しておきましょう。
Google Analytics(GA4)などのアクセス解析ツールの導入や、キーワード選定、メタタグの最適化、コンテンツSEOなど、どこまでの対策を行うかを明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
5. コンテンツと情報発信に関する質問
「企業が伝えたいこと」と「ユーザーが知りたいこと」のバランスが取れたコンテンツを企画します。
- 「どのような情報を優先的に伝えたいですか?」
- 「お客様が最も知りたいと思う情報は何だと思いますか?」
- 「お問い合わせフォームやブログ機能など、必要な機能はありますか?」
お問い合わせフォーム、会員登録機能、ECサイト機能、ブログ、SNS連携など、必要な機能をヒアリングし洗い出しましょう。
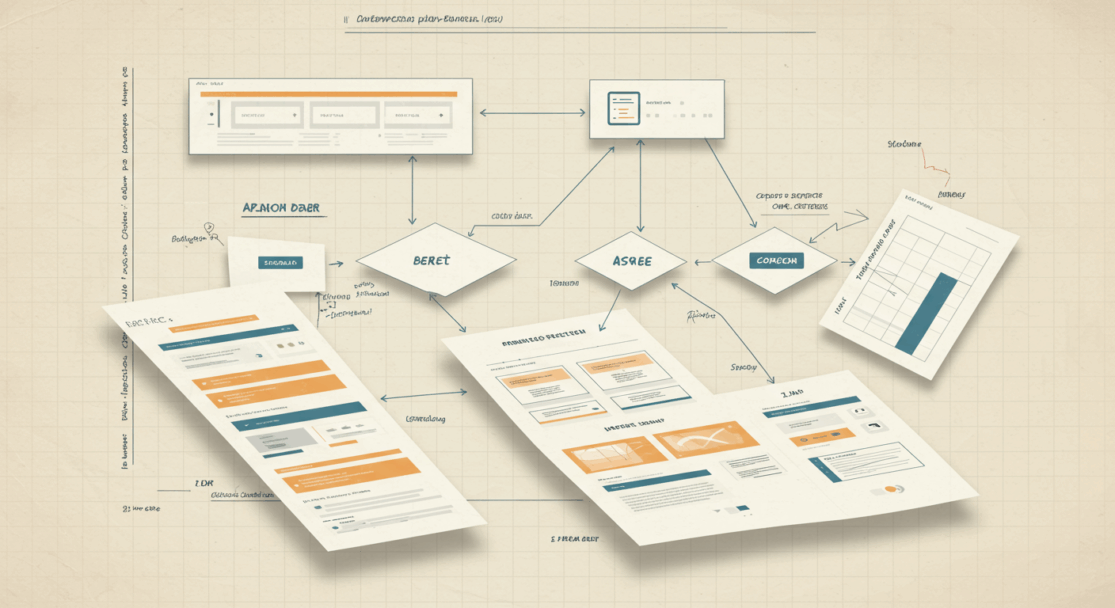
また、既存コンテンツ(会社案内、製品情報など)の取扱も確認しましょう。全てを移行するのか一部なのか、新規コンテンツはクライアント提供か制作会社による代行かなど、コンテンツの作成責任者や承認フローも確認しておきましょう。
6. デザインの方向性に関する質問
クライアントの好みやブランドイメージを視覚的に理解します。
- 「好きなWebサイトのデザインや、参考にしたいサイトはありますか?」
- 「御社のブランドイメージを表す言葉や色はありますか?(例:モダン、親しみやすい、青など)」
- 「避けたいデザインのテイストはありますか?」
デザインの好みは主観的なものですが、「好きなWebサイトの例」「参考にしたいサイト」など具体的な参考サイトを挙げてもらうことで、クライアントが抱いているイメージを視覚的に共有・理解することができます。
7. 運用体制と予算に関する質問
公開後の継続的な運用を見据え、現実的な計画を立てます。
- 「サイト公開後の更新はどなたが、どのくらいの頻度で担当されますか?」
- 「Webサイトの制作と、その後の運用にかけるご予算感を教えてください」
- 「希望する公開時期はいつ頃ですか?」
Webサイトは公開して終わりではありません。公開後の更新頻度や更新方法、セキュリティ対策、バックアップ体制なども事前に確認しておくことが重要です。
- 「サイト公開後の更新はどなたが担当される予定ですか?」
- 「更新頻度はどの程度を想定していますか?」
- 「Webサイト制作と運用にかける予算感を教えてください」
特に中小企業では運用体制が十分に整っていないケースが多く、「本業の合間に時間があったらやる」という不確かな体制になりがちです。誰が、どれくらいの頻度で更新するか、現実的な運用計画がサイトの長期的な成功につながります。

クライアント側で更新する場合はCMS(コンテンツ管理システム)の導入を要件定義に必ず盛り込み、制作会社へ更新代行を依頼する場合は保守サービスを検討する必要があります。
また、予算と納期は品質を決定する重要な要素です。
クライアントの期待と現実のギャップを埋めるためにも、早い段階で率直な話し合いが必要です。
予算については、「〇〇万円程度」という具体的な金額を聞き出せるとベストですが、答えにくい場合は「〜50万円」「50〜100万円」などの範囲で確認するのも一つの方法です。
納期については、公開希望日だけでなく、中間成果物(ワイヤーフレーム、デザインカンプなど)の確認スケジュールも含めて検討しましょう。
すぐに使える!実用的なヒアリングシートテンプレート
実際に使えるヒアリングシートのテンプレートをご紹介します。このテンプレートは、私が実際のプロジェクトで使っているものをベースにした、汎用的なテンプレートです。
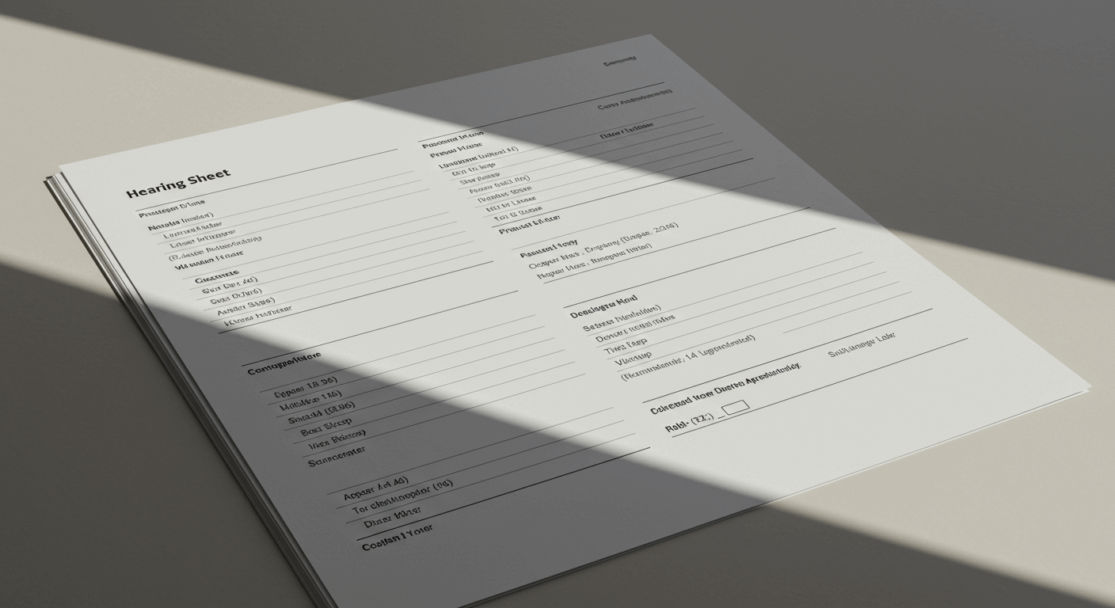
基本情報
- 会社名/ご担当者名
- 連絡先(電話番号/メールアドレス)
- 現在のWebサイトURL(リニューアルの場合)
- ヒアリング日/担当者
プロジェクト概要
Webサイト制作の目的(複数選択可)
- 会社・サービスの認知度向上(ブランディング)
- 問い合わせ・資料請求の増加
- 商品・サービスの販売
- 採用活動の強化
- 具体的な数値目標(可能であれば):
- その他
予算感・納期
- 50万円
- 50〜100万円
- 100〜200万円
- 200万円〜
- 希望納期/公開予定日
ターゲットユーザー
- 主なターゲット層(年齢/性別/職業など)
- ターゲットが抱える課題や悩み
- ターゲットの特徴や行動パターン
- ターゲットがWebサイトに求めていること
競合分析
- 主な競合サイト(URL)
- 競合サイトの良い点・改善点
- 自社の強み・差別化ポイント
サイト構成・機能
必要なページ(複数選択可)
- トップページ
- 会社案内/企業情報
- サービス/商品紹介
- 実績/事例紹介
- ブログ/コラム
- 採用情報
- お問い合わせ
- その他
必要な機能(複数選択可)
- ブログ機能
- SNS連携
- お問い合わせフォーム
- 資料請求フォーム
- 多言語対応
- 会員登録/ログイン機能
- ECサイト機能
- 予約システム
- その他
デザイン要件
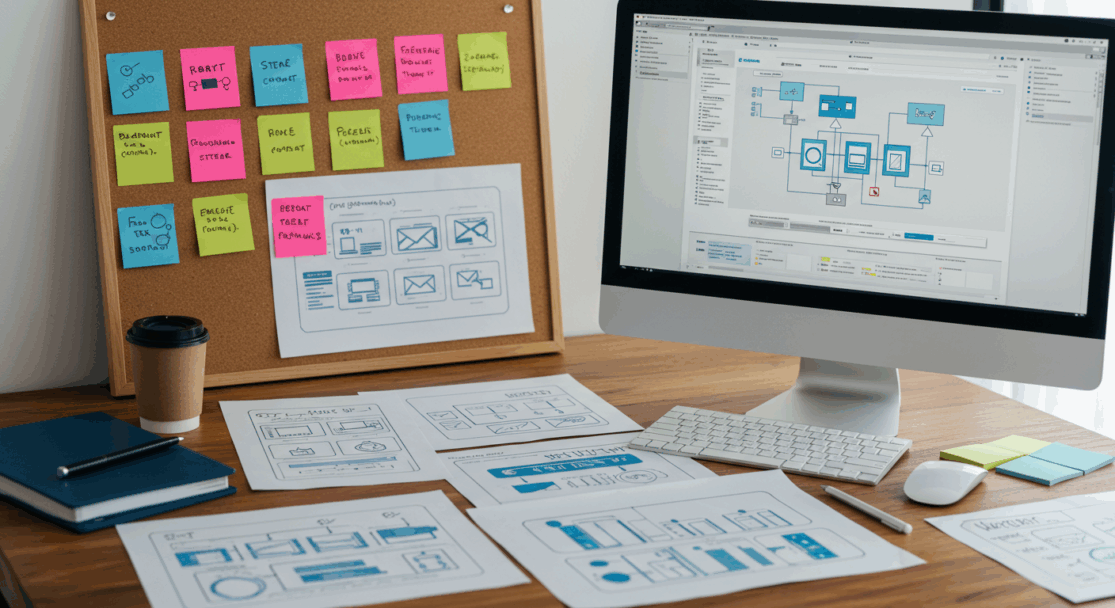
デザインの方向性(複数選択可)
- モダン/スタイリッシュ
- シンプル/ミニマル
- 親しみやすい/カジュアル
- 高級感/格式高い
- その他
デザインの具体的イメージ
- 参考にしたいWebサイト(URL)
- 希望する色のイメージ
- 使用したい写真/イラスト
- 避けたいデザイン要素
原稿・素材(文章や画像)
- コンテンツ準備の担当(クライアント/制作会社)
- 既存コンテンツの有無と形式
- 写真/画像素材の準備状況
- コンテンツ承認フロー(〇〇様)
運用・保守
- 更新頻度の想定
- 更新作業の担当(更新対象コンテンツ/クライアント/制作会社)
- CMS(コンテンツ管理システム)の必要性(必要/不要)
- 保守契約の希望(希望する/希望しない)
SEO・マーケティングセクション
- 主要な対策キーワード
- アクセス解析の必要性(必要/不要)
- SNSとの連携
- リスティング広告出稿の予定
その他・備考セクション
- その他の要望や質問
- 懸念事項
ヒアリングシートの活用ポイントと実践
ヒアリングシートを効果的に活用するためのポイントをご紹介します。単にテンプレートを使うだけでなく、以下のポイントを押さえることで、より質の高いヒアリングが可能になります。
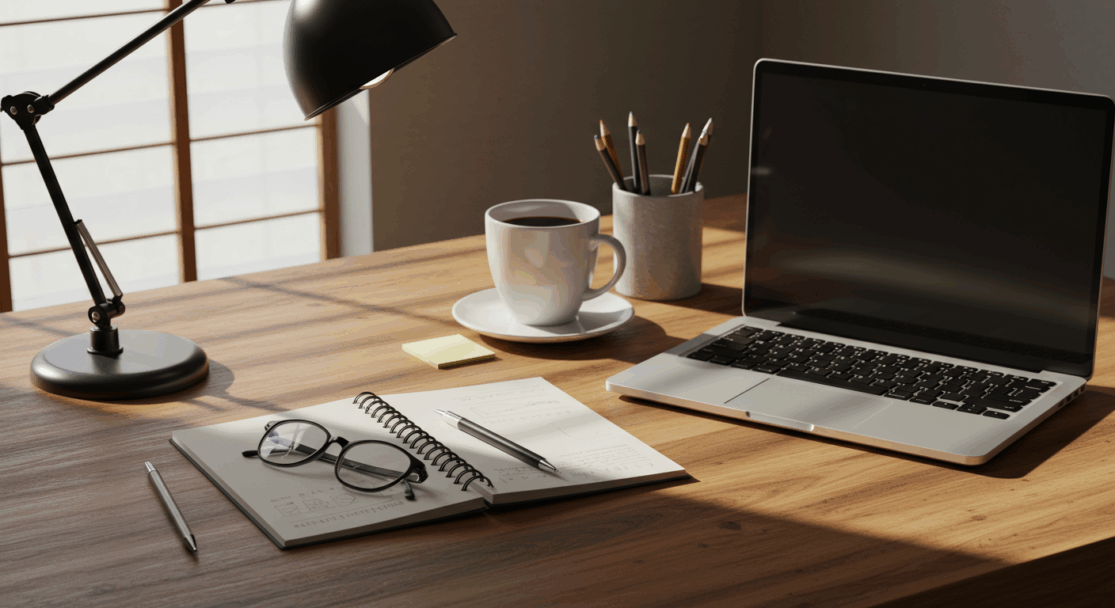
1. ヒアリング前の準備が重要
ヒアリングシートを送付する前に、クライアントの業界や事業内容について基本的な調査を行っておきましょう。業界特有の課題や最新トレンドを理解しておくことで、より的確な質問や提案ができるようになります。
また、クライアントの現在のWebサイト(リニューアルの場合)や競合サイトを事前にチェックしておくことも大切です。「このページは参考になりますね」「こういった改善ができそうです」など、具体的な話ができると信頼感が高まります。
2. 質問の意図を説明する
ヒアリングシートの質問項目が多いと、クライアントは「なぜこんなことを聞くのか」と疑問に思うかもしれません。各セクションの冒頭に質問の意図や重要性を簡潔に説明することで、クライアントの協力を得やすくなります。
例えば、「ターゲットユーザーに関する質問は、デザインやコンテンツをユーザーにとって最適なものにするために重要です」といった説明を加えると、クライアントも真剣に考えて回答してくれるでしょう。
当日いきなり質問するのではなく、事前に「こういう目的で質問します」と伝えておくと、クライアント側もお会いするまでに考える時間が生まれ、より深い回答を引き出せることが多いです。
3. 対面・オンラインでのヒアリングを併用する
ヒアリングシートはあくまでも情報収集のツールです。シートだけでなく、対面やオンラインでの打ち合わせを併用することで、より深い理解が得られます。
特に、クライアントの表情や反応を見ながら質問することで、文書だけでは伝わらないニュアンスや優先順位を把握することができます。また、その場で追加質問をすることで、より具体的な情報を引き出すことも可能です。
4. 優先順位を明確にする
クライアントの要望は多岐にわたることが多く、すべてを同時に実現することは難しい場合があります。そのため、要望の優先順位を明確にしておくことが重要です。
「最も重要な目的は何ですか?」「予算や納期を考慮した場合、どの機能を優先しますか?」といった質問を加えることで、プロジェクトの方向性がより明確になります。
5. 定期的に見直し・改善する
ヒアリングシートは一度作ったら終わりではありません。プロジェクトの経験を積むごとに、「この質問は役に立った」「この質問は不要だった」といった気づきが得られるはずです。
そうした気づきをもとに、定期的にヒアリングシートを見直し、改善していくことで、より効果的なツールへと進化させることができます。私自身、10年間で何度もヒアリングシートを改訂してきました。
ヒアリングシート活用の注意点
ヒアリングシートを活用する際の注意点についても触れておきましょう。これらのポイントに気をつけることで、より効果的なヒアリングが可能になります。
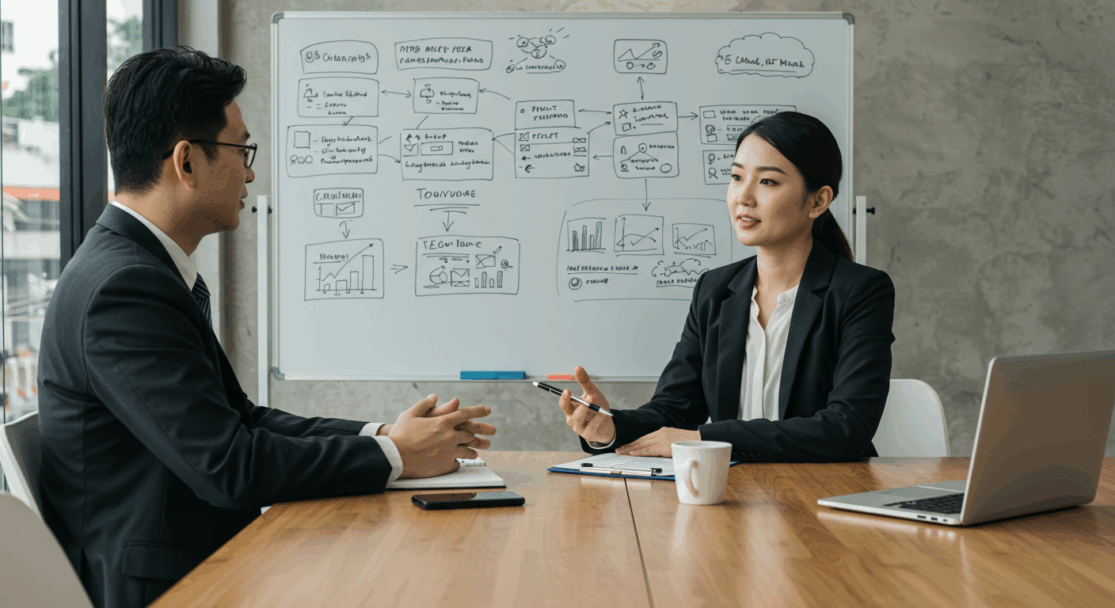
1. 専門用語を多用しない
Web制作の専門家にとっては当たり前の用語でも、クライアントにとっては難解な専門用語が多くあります。「レスポンシブデザイン」「CMS」「SEO」などの用語を使う場合は、簡単な説明を添えるか、平易な言葉に置き換えるようにしましょう。
例えば、「レスポンシブデザイン」ではなく「スマートフォンやタブレットでも見やすく表示される設計」、「CMS」ではなく「Webサイトを簡単に更新できるシステム」といった言い換えが効果的です。
2. 質問数のバランスを考える
詳細な情報を得たいからといって、質問数が多すぎるとクライアントの負担になります。特に初回のヒアリングでは、必要最低限の質問に絞り、詳細は段階的に聞いていくアプローチが効果的です。
私の経験では、初回のヒアリングシートは30分程度で回答できる量(20〜30問程度)が適切です。それ以上の詳細は、初回ヒアリング後の追加質問として整理するとよいでしょう。
3. クライアントの言葉をそのまま記録する
ヒアリング中にクライアントが使った言葉や表現は、できるだけそのまま記録しておくことが重要です。専門家の言葉に言い換えてしまうと、ニュアンスが変わってしまう可能性があります。
特に「使いやすい」「かっこいい」「親しみやすい」といった主観的な表現は、クライアントによって意味が異なります。「具体的にはどのようなイメージですか?」と掘り下げて確認することが大切です。
4. 要望と予算のギャップに注意する
クライアントの要望と予算にギャップがある場合は、早い段階で率直に伝えることが重要です。後になって「予算オーバーなので機能を削減します」と言うよりも、初期段階で「この予算ではここまでの機能が実現可能です」と明確にしておく方が、信頼関係を築けます。
予算に合わせた段階的な開発計画を提案するなど、クライアントの期待と現実のバランスを取るための工夫も必要です。
成果の基盤を作る「情報整理シート」とは?
ヒアリングで得た情報を整理し、ウェブサイトの骨格を設計するのが情報整理シートです。多くのWebサイトが失敗する原因は「企業が伝えたいこと」と「顧客が知りたいこと」のギャップにあります。情報整理シートはこのギャップを解消し、サイトの成功確率を飛躍的に高めます。
多くの企業がWebサイトを持っていますが、その多くは「企業が伝えたいこと」と「顧客が知りたいこと」のギャップが解消されていません。自社都合の情報設計になっていたり、強みや特徴など自社の価値が伝えきれていなかったり、情報がバラバラでサイトが構造的に設計されていなかったりと様々な問題を抱えています。

情報整理は時間をかけるほど、後工程が加速する
初期の情報整理にしっかり時間をかけることで、デザインや実装段階での手戻りが減り、プロジェクト全体の効率が向上します。
Webサイト制作において「デザイン」や「技術力」が重視されがちですが、「情報整理と構造設計」がその後の成否を大きく分けます。特に運用を重ねれば重ねるほどこの傾向は顕著です。
情報整理シートを活用するメリットと効果
- 企業の理念・体制・事業内容・選ばれる理由を顧客視点で可視化できる
- 社内で共通理解が生まれ、営業や採用など誰が説明しても「ズレない」情報発信が可能になる
- 営業・採用・教育・承継など、ウェブサイトだけでなく様々な場面で活用できる情報資産となる
「Webサイトを上手く使っていきたいけど、何を伝えればいいのかわからない」と悩んでいませんか?実はあなただけでなく多くの企業が直面する課題です。
Webサイトは「作って終わり」ではなく継続的に育てていくもの。その基盤となる情報整理をしっかりと行うことで、長期的に成果を生み出すウェブサイトが構築できます。
情報整理シートを活かすためのポイント
情報整理シートを最大限に活かすためのポイントを紹介します。
- 経営者・現場担当者など、複数の視点から情報を収集する
- 「当たり前」と思っている情報こそ、明文化・可視化する
- 情報の優先順位を明確にする(すべてが重要ではない)
- ユーザー視点で情報を整理する(自社視点に偏らない)
- 定期的に情報を更新・見直す(情報は常に変化する)
社内では「当たり前」でも外部の人には伝わっていないことが多くあります。そうした「暗黙知」を「形式知」に変換することが情報整理の本質です。
情報整理シート作成3つのステップ
情報整理シートを作成するための3つのステップをご紹介します。基本的な構成要素を記入することで、ウェブサイトの目的を明確にし、ウェブサイト制作の土台となる情報を体系的に整理できます。
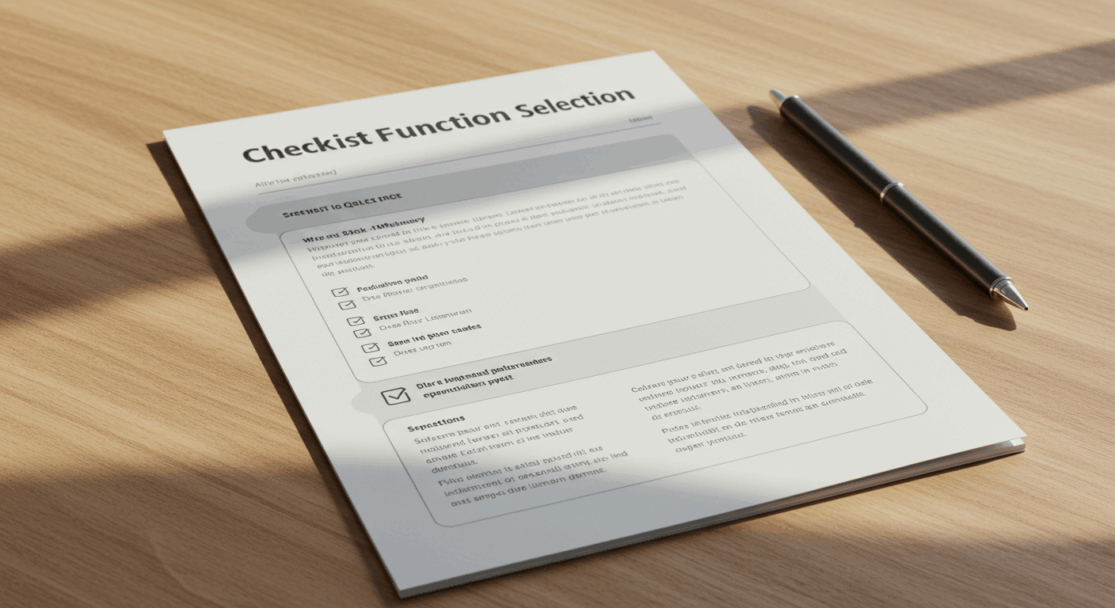
STEP1: 事業理解のための情報収集
事業の背景や価値観まで掘り下げ、現状を棚卸しします。
- 経営者へのヒアリング
「なぜこの事業を始めたのか」「どんな価値を提供したいか」など根本的な想いを聞き出す - 事業責任者・担当者へのヒアリング
営業や採用担当者から、顧客や求職者のリアルな声を集める。 - 既存のWeb・広告データの分析(任意)
STEP2: 顧客理解のための情報整理
ターゲットとなる顧客の具体的な人物像(ペルソナ)と、その行動・心理を理解します。
- ペルソナの再定義と意思決定プロセスの明文化
「35歳男性、IT企業勤務」だけでなく「どんな課題を持ち、どんな価値観を重視するか」まで掘り下げる - カスタマージャーニーの構築
顧客が自社を知り問い合わせや購入に至るまでの道筋を可視化する - 失注・成功ケースの分解分析(任意)
STEP3: 競合分析と差別化ポイントの明確化
客観的な視点で競合を分析し、「自社ならではの価値」を明らかにします。
- 競合サイトの調査
情報構造や使われている言葉を分析する - 差別化要素の抽出と可視化
「競合にはない独自のサービス」「他社より手厚いサポート」など、勝っているポイントを言語化する - 競合にないコンテンツ設計の立案
競合が提供していない独自のサービスや、他社にはない専門的な知識、迅速なカスタマーサポートなど「ターゲットが求めているが競合は提供できず自社が提供できること」が差別化です。
情報整理シートのテンプレートと活用法
実際に使える情報整理シートのテンプレートと、その効果的な活用法を紹介します。
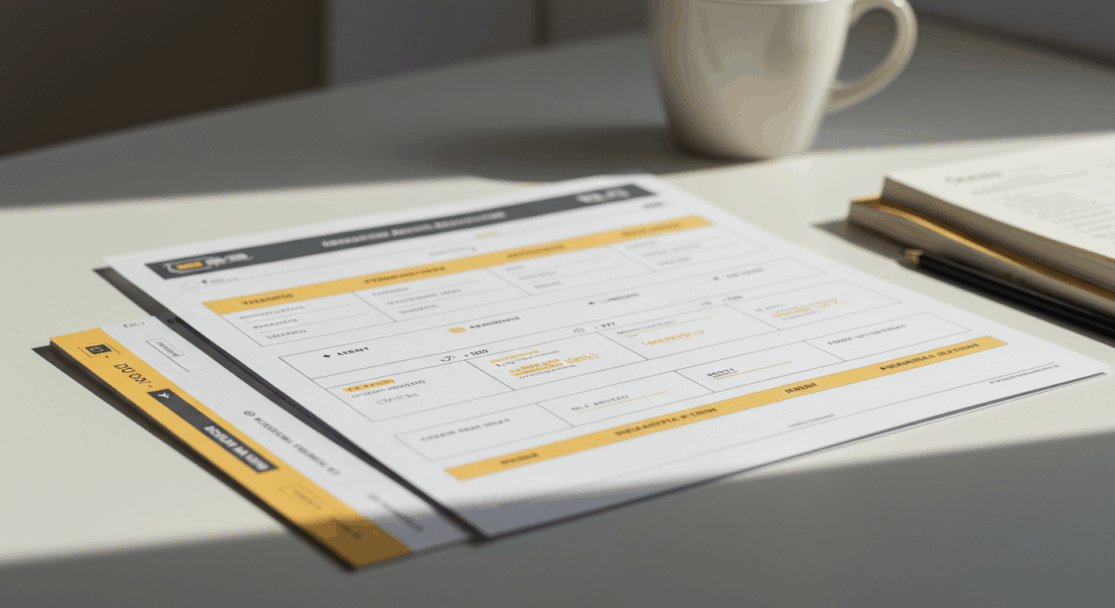
自社・競合情報テンプレート
ウェブサイト制作の基本情報を収集するためのテンプレートです。プロジェクトの方向性を決める重要な情報を整理します。
- プロジェクト概要(目的、目標、期間、予算など)
- 企業情報(理念、ビジョン、強み、特徴など)
- ターゲット情報(ペルソナ、課題、ニーズなど)
- 競合情報(競合サイト、差別化ポイントなど)
- コンテンツ要件(必要なページ、機能など)
ペルソナ設定シート
ターゲットとなるユーザーを具体的に設定するためのシートです。表面的な属性だけでなく、心理や行動パターンまで掘り下げます。
- 基本属性(年齢、性別、職業、役職など)
- ライフスタイル(趣味、価値観、日常生活など)
- 課題・悩み(業務上の課題、個人的な悩みなど)
- 情報収集行動(よく利用するメディア、情報源など)
- 意思決定プロセス(検討から決定までの流れ)
「誰に向けて」「何を伝えるか」を可視化し、サイト構造や必要なコンテンツを設計します。
情報構造設計シート
Webサイトの情報構造を設計するためのシートです。情報の階層や関連性を視覚化します。
- サイトマップ(ページ構成と階層)
- ページごとの目的と対象
- コンテンツの優先順位
- ユーザーの導線設計
- CTAの配置計画
情報構造を可視化し共通理解を持つことで、クライアント・制作会社が一体となったチーム全体でサイト制作に臨みます。
ヒアリングシートと情報整理シートから戦略的なサイト構造を設計する
整理した情報を基に、ユーザーが迷わず目的を達成できるサイト構造を設計します。
SWOT分析で全体像を把握する
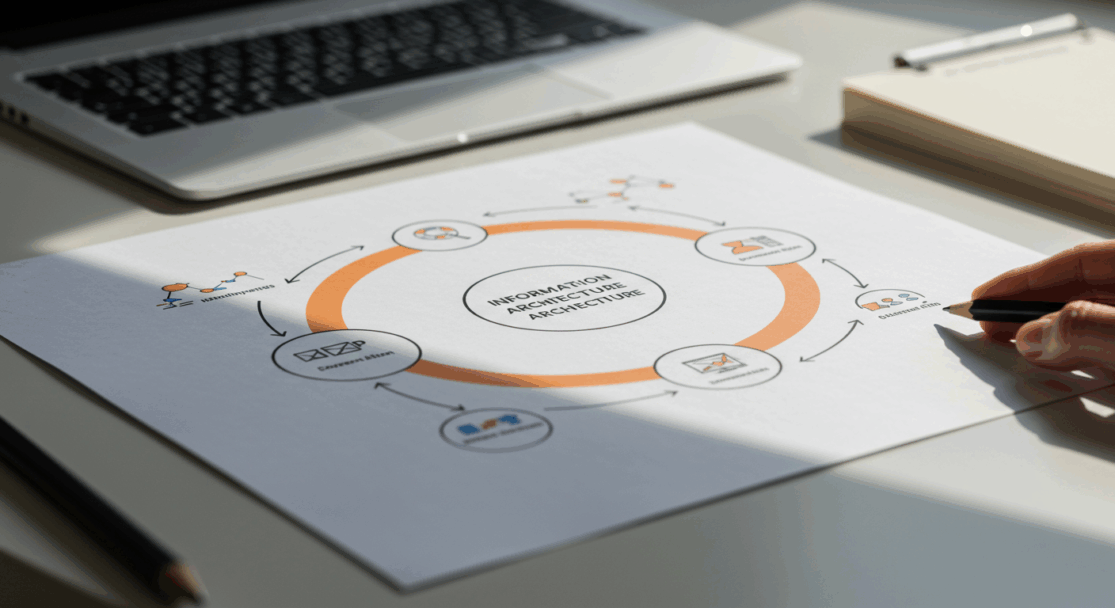
SWOT分析は、企業の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を整理するフレームワークです。ヒアリングで得た情報をこの4つに分類することで、Webサイトで強調すべき点や対応すべき課題が明確になります。
例えば、ある製造業のクライアントでは、「技術力の高さ」と「少量多品種生産への対応力」が強みとして浮かび上がりました。これらをWebサイトの中心的なメッセージとして位置づけることで、差別化された訴求ポイントを構築できました。
ペルソナ設定で顧客を具体化する
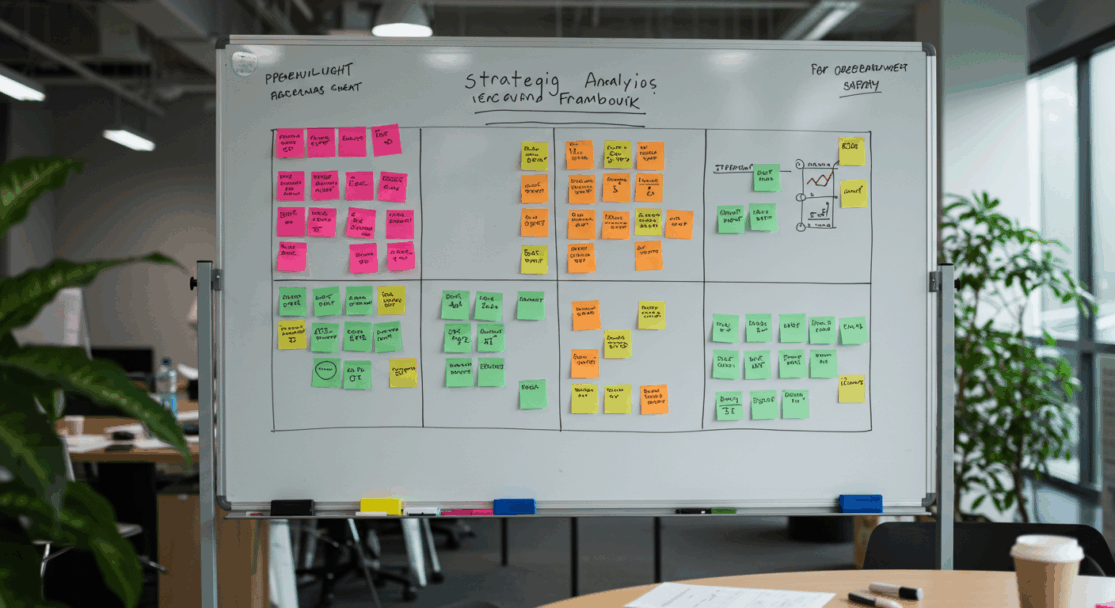
ペルソナとは、理想的な顧客像を具体的に描いたものです。ヒアリングで得た顧客情報をもとに、以下の要素を含むペルソナを作成します。
- 基本属性(年齢、性別、職業、役職など)
- 業務上の課題や悩み
- 情報収集の方法
- 意思決定のプロセスと判断基準
- 価値観や優先事項
ペルソナを設定することで、「誰に向けて、何を、どのように伝えるか」が明確になり、Webサイトの情報設計がしやすくなります。
カスタマージャーニーマップで導線を設計する

カスタマージャーニーマップとは、顧客がWebサイトとの接点を持ってから目標達成(問い合わせや購入など)に至るまでの道筋を可視化したものです。
具体的には、以下のステップごとに顧客の行動、感情、接点、課題を整理します。
- 認知段階:どのように自社サイトを知るか
- 検討段階:どのような情報を求めているか
- 比較段階:何を基準に判断するか
- 決定段階:最終的な決め手は何か
- 行動段階:どのようにアクションを起こすか
このマップを作成することで、各段階で必要なコンテンツや導線が明確になり、ユーザーの自然な行動に沿ったサイト設計が可能になります。
サイトマップで情報の階層を整理する
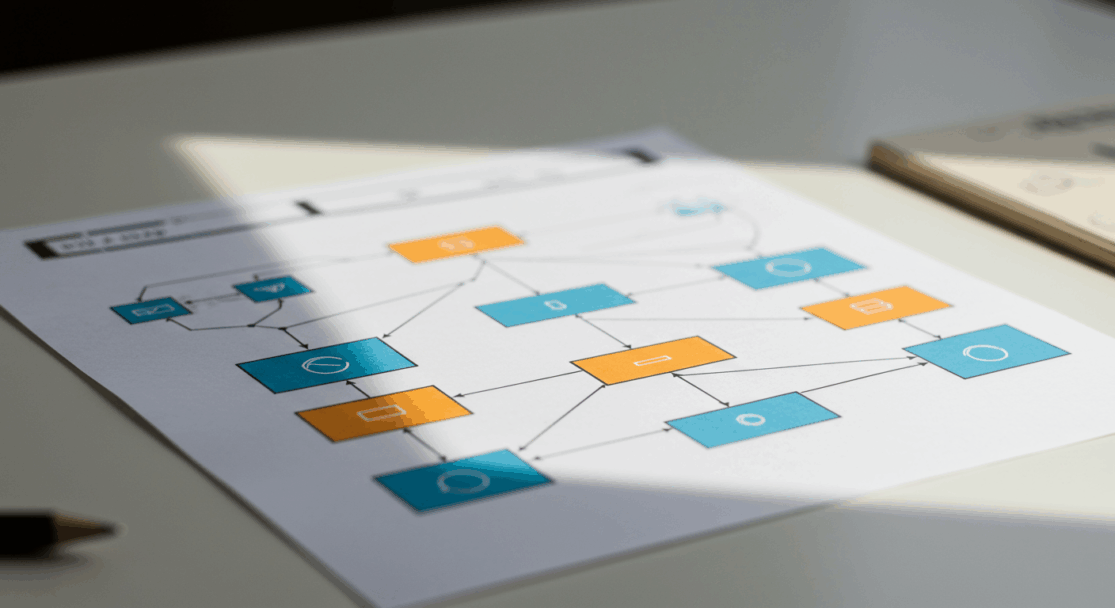
ウェブサイトの全体像を設計図(サイトマップ)に落とし込みます。
- 情報の階層を3段階以内に抑える: 3クリック以内で目的ページへの到達を目標
- 情報のグルーピング: 関連性の高い情報をまとめる
- 直感的なラベリング: メニュー名などを分かりやすい言葉にする
- コンテンツの優先順位付け:重要度に基づく配置の決定
サイトマップは単なるページ一覧ではなく、情報の関連性や優先順位を視覚化したものです。ユーザーの行動パターンを考慮した設計が求められます。
ページごとの情報設計方針の策定

各ページの目的と対象を明確にし、どのような情報をどの順序で配置するかを決定します。
- ページの目的と主要ターゲットの設定
- 伝えるべき主要メッセージの決定
- コンテンツの優先順位付け
- ユーザーの次のアクションの設定
各ページには明確な目的が必要です。「このページを見た人に何をしてほしいのか」を明確にすることで、効果的なコンテンツ設計が可能になります。
導線設計と行動誘導
ユーザーをどのように誘導し、最終的なコンバージョン(問い合わせ、資料請求など)につなげるかを設計します。
- 各ページからの遷移先の設定
- CTA(Call To Action)の配置計画
- ユーザーの回遊性を高める関連コンテンツの設計
CTAはコンバージョン率に直結する重要な要素。ユーザーに「ただ情報を見せる」だけでなく、「次のアクションに誘導する」ための設計をします。
成功するWeb制作は「ヒアリング」と「情報整理」が重要
Webサイト制作の成功は、高度なデザインや最新技術だけで決まるものではありません。
その土台となるクライアントへの深い理解(ヒアリング)と、戦略的な情報の構造化(情報整理)こそがプロジェクトの成否を分けます。
- ヒアリングシートは、プロジェクトの方向性を決める羅針盤。
- 情報整理シートは、成果を生み出すWebサイトの設計図。
この2つのツールを活用することで、クライアントとの認識のズレを防ぎ、ユーザーに価値が伝わるWebサイトを構築することができます。この記事が、あなたのWeb制作プロジェクトを成功に導く一助となれば幸いです。
BaseTreeでは埼玉県・群馬県に特化したウェブサイト制作を提供しています。
「ウェブサイトをリニューアルしたい」「新たにウェブサイトを立ち上げたい」という事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。