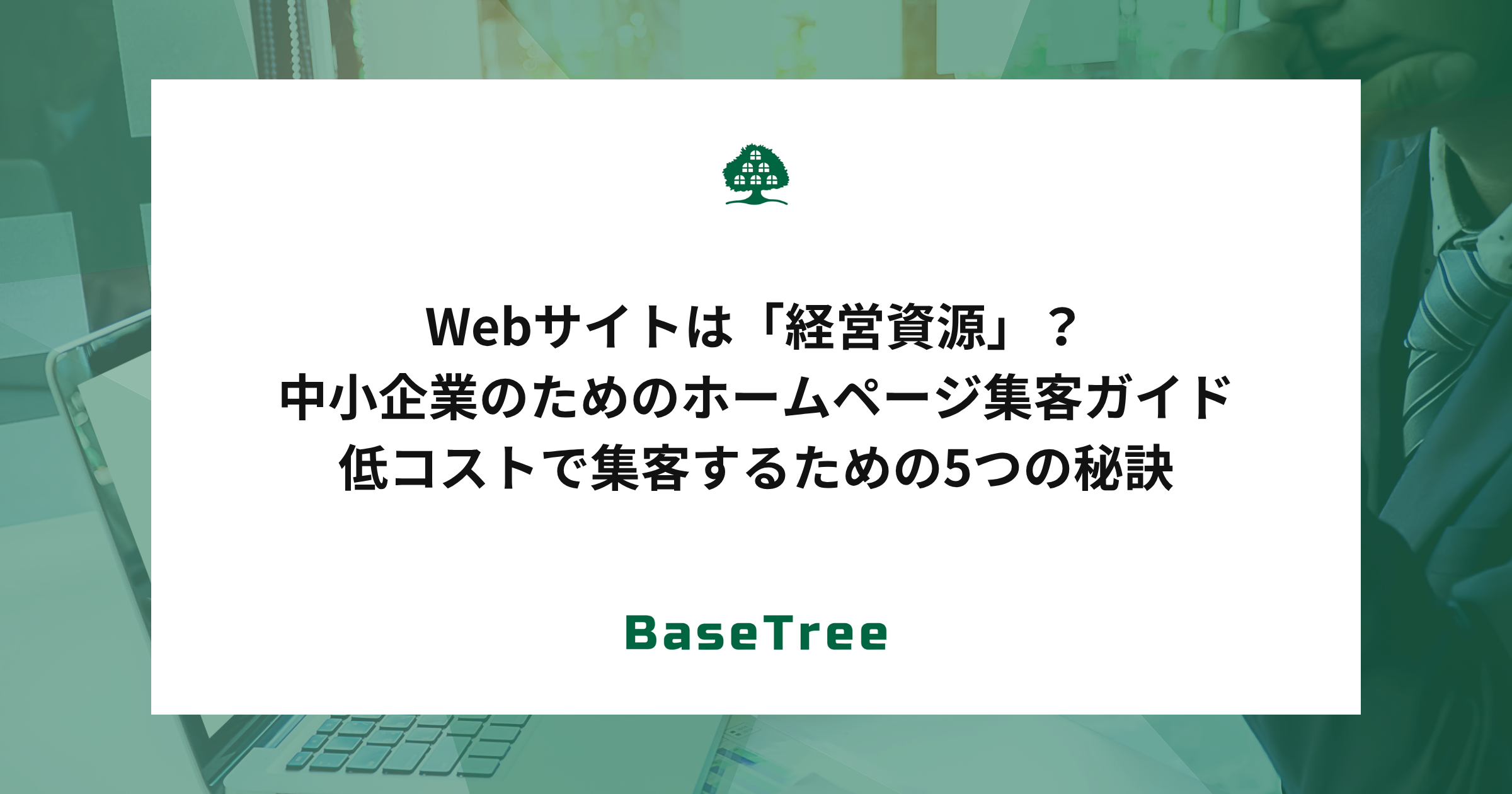Webサイトが「経営資源」?
Webサイトだけであらゆる経営課題を解決できるハズはなく、ウェブサイトが至上というわけでもありません。
しかし、「Webサイトでも」解決できることもあります。「Webサイト」で解決の一端を担うこともできます。
ヒト(人材)
「理想の働き方の実践と発信」
ウェブサイトで社員の実際の働き方や成長過程を詳しく紹介することが会社の理念と現実が一致していることを示し、同じ価値観を持つ優秀な人材を惹きつけ、社員の成長意欲も高める
モノ(商品・サービス)
「製品の使用現場の可視化」
ウェブサイトで顧客の製品使用事例や声を具体的に掲載することが潜在顧客の「うちの会社でも使えそう」という実感を生み、問い合わせから購入決定までの時間を短縮する
カネ(資金)
「経営の健全性と成長性の見える化」
ウェブサイトで実績数、市場シェア、顧客継続率、従業員構成、事業承継計画、決算書を公開することが公的機関や金融機関から見た経営の安定性と将来性を明確に示し、融資条件の改善や新規投資の獲得など、資金調達の幅を大きく広げる
情報
「24時間稼働の営業・サポート拠点」
ウェブサイトで製品情報、FAQ、活用事例、業界動向を公開することが、営業訪問やアフターフォローを自動化・補完し、顧客接点を最大化すると同時に市場の反応をリアルタイムで収集し、製品改良や新サービス開発のヒントを得る
Webサイトに企業活動を掲載・発信することで、「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」の経営資源を底上げする、もしくは経営資源をより効率的に増やせる。
Webサイトが経営資源を強化し、しかも代表者が変わっても企業に残り続け継承できるのなら、それは「Webサイトは企業にとって経営資源」と言えるのではないでしょうか。
Webサイトが解決に貢献する経営課題の例
営業力強化
「商談の質を上げる」
ウェブサイトで製品情報や導入事例を公開することが営業担当の基本的な説明作業を減らし、顧客ニーズに合わせた提案や交渉に時間を使えるようになる
業務効率化
「仕事の無駄をなくす」
ウェブサイトで業務マニュアルや規定を一か所にまとめることが社員の作業時間を短縮し、ミスも減らし人件費や経費の削減につながる
事業承継
「会社の歴史をつなぐ」
ウェブサイトで創業からの物語や成功体験を記録することが、会社の大切にしてきた価値観を形にし、次の世代へスムーズに引き継ぐ手助けとなる
商品開発・改良
「新しいアイデアを育てる」
ウェブサイトでお客様の声や社員の気づきを集めることが製品改良や新サービスのヒントを生み出し、他社にない独自の強みを作り出す
人材育成
「全員で学び合う」
ウェブサイトで研修内容や成長事例を共有することで社員同士が互いに刺激し合い、学ぶ雰囲気を作り、会社全体の能力アップと人材の定着につながる
ブランド構築
「会社の良さを伝える」
ウェブサイトで理念や社会貢献活動を分かりやすく示すことが、会社の存在意義を社会に広く知ってもらい、顧客や優秀な人材から選ばれる会社になる
今持っているもの・やれていることを1つ1つ丁寧に言語化し、Webサイトという媒体に載せ、これを顧客に届けたり、自社自ら活用する。
Webサイトでもやれることはたくさんあります。
思っているだけでは届かないし、あなたが素晴らしくてもそれを知る術がなければわからない。
高額な設備やツールやコンサルを入れる前に、まずは「自分たちの今」をアウトプットすることが経営課題解決策の初手ではないでしょうか。
中小企業だからこそホームページを持つべき理由
インターネットが日常生活に欠かせないものとなった現代、企業のホームページは「あれば便利」ではなく「ないと困る」存在へと変化しています。
特に中小企業にとって、ホームページは大企業と対等に戦うための強力な武器です。
でも、「本当にうちの会社にホームページは必要なの?」と疑問に思う経営者の方も多いでしょう。
10年間WEBディレクターとして様々なクライアントのウェブサイト制作に携わってきた経験から言えることは、適切に作られたホームページは中小企業の成長に大きく貢献するということです。
ホームページがあることで潜在顧客はあなたの会社を24時間365日発見できるようになります。
スマートフォンやSNSの普及により検索するユーザーが急増している今、オンライン上に存在しないことは、ビジネスチャンスを逃し続けているのと同じです。
検索ですぐにはヒットしなくても、すぐに問い合わせに繋がらなくても、毎日毎日オンライン上に向かって「プレスリリース」を打つ。
「プレスリリース」の積み重ねがあって、初めて集客になり、接客になり、問い合わせにつながるのです。
特に埼玉県深谷市や熊谷市、本庄市などの地域密着型ビジネスにとって、地域のユーザーに見つけてもらえるホームページは、新規顧客獲得の重要な入り口です。
そして、そのために「どんなホームページを有するか」が重要です。
「コストを抑えながら集客できるホームページ」5つの秘訣

「ホームページを作りたいけど、費用が心配…」
多くの中小企業経営者から聞く悩みです。
確かに制作会社に依頼すると数十万円から数百万円かかります。
でも、実は初期費用を抑えながらも効果的なホームページを作る方法があります。
私がBaseTreeを創業する前、多くのクライアントが「予算内で最大の効果を出せるホームページ」を求めていました。
その経験から、コストを抑えながらも集客できるホームページを作るための5つの秘訣をご紹介します。
1. ホームページの目的と目標を明確にする
ホームページ制作で最も重要なのは、「なぜ作るのか」という目的を明確にすることです。「みんなが持っているから」では、カネという資源を無駄にしてしまいます。
問い合わせを増やしたいのか、商品を販売したいのか、採用を強化したいのか。
目的によって、必要な機能やページ構成は変わってきます。
目的が明確なほど、無駄な機能を省けるため、制作コストを削減できます。
例えばブログ機能を減らす、サービスを絞る、高度な自動化や連携の仕組みを見送って運用でカバーするなど、必要最小限の機能やページ構成に絞ることで、コストダウンが図れます。
Webサイトを公開したりリニューアルしてすぐ、ましてや1〜2ページだけで、今まで問い合わせがなかったところからいきなり問い合わせが来る、というのは困難です。
よく、Webサイトは「公開して終わりではなく継続的な更新が大事」と言いますが、実際の運用面でも機能やサービスを絞って小さく始めるやり方が現実的です。
小さく生み、大きく育てるです。
大きく育つ過程で、必要なページや機能は追加できます。
まず、何のために、何を目標にして、そのためにユーザーに何を提供できるのか?実際に提供できているのか?を反芻しながら「使えるホームページ」を手にすることが、5つの秘訣の中でも最重要です。
2. テンプレートを活用する
ゼロからオリジナルデザインを作ると費用が高くなりますが、WordPressなどのCMSには、高品質なテンプレート(テーマ)が数多く用意されています。
テンプレートを活用すれば、デザイン費用を大幅に抑えられます。
また、要素が決まっているので「何を書けばいいかわからない」という企業や経営者にとっては、まず「穴埋め」することで体裁が整うというメリットもあります。
テンプレートは「使い古されている」「他所と同じようなデザイン」と敬遠される方もいますが、カスタマイズ次第でオリジナリティを出すことは十分可能です。
業種別に最適化されたテンプレートも多数あります。
貴社の事業やブランドに合ったテンプレートを選び、それを叩きに自社の事業理解、そして訴求内容を検討してみてください。
テンプレートを選ぶ際、必ずチェックしていただきたいのが、テンプレートが「モバイル対応(レスポンシブデザイン)」か否かです。
現在、Webサイトへのアクセスの約7割はスマートフォンです。(業種にもよりますが)
スマホで見やすいサイトでなければ、せっかくの訪問者を逃してしまいます。
3. 必要な機能に絞る
「あれもこれも」と欲張りすぎると制作費用が膨らむだけでなく、サイトの使いやすさも損なわれます。
特に初期段階では本当に必要な機能に絞ることが重要です。
例えばお問い合わせフォームは必須ですが、会員登録機能やオンライン予約システムは本当に必要か検討し見送るなど。
機能は後から追加することもできます。
まずは最小限の機能でスタートし、反応を見ながら徐々に拡張していきましょう。
私が支援したクライアントでは当初予定していた予約システムの導入を見送り、シンプルなお問い合わせフォーム&LINE登録からスタート。
運用しながらニーズを確認した後で予約システムを追加し、初期費用を抑えながら問い合わせ後の対応まで含めて効率的なサイト運営ができました。
4. コンテンツは自分で用意する
ホームページ制作費用の中で、意外と大きな割合を占めるのがコンテンツ制作費です。
テキストの作成や写真撮影を制作会社に依頼すると追加費用が発生します。
できる限り会社紹介文や商品説明などのテキスト、商品や店舗の写真を自分で用意するとコストが抑えられます。
スマートフォンのカメラでも、明るい自然光の下で撮影すれば、十分使える写真が撮れます。
ただし、自社の魅力を伝えるコンテンツ作りは簡単ではありません。
「何を書けばいいかわからない」という場合は、まずは競合他社のサイトを参考にしたり、お客様からよく聞かれる質問をもとにコンテンツを考えたりするのがおすすめです。
写真も同様に、やはりプロが撮った写真の方がキレイで、一目で分かります。
あくまで「初期段階」であり、なおかつ「コストがかけられない」場合の対応策です。
5. 運用のしやすさを重視する
ホームページは作って終わりではありません。
定期的な更新が、検索エンジンからの評価を高め、集客力を維持するために重要です。
WordPressなどの自社で簡単に更新できるCMS(ホームページ構築システム)を導入すれば、専門知識がなくてもブログ記事の投稿や基本的な情報更新が可能で、長期的なコスト削減につながります。
更新作業をすべて制作会社に依頼すると、その都度費用が発生します。
小さな変更でも数千円から数万円の費用がかかります。
自社で更新できる環境を整えることで、運用コストを大幅に削減できるのです。
集客できるホームページの基本構成とは?
ただ安ければいいわけではありません。
肝心なのは「集客できるホームページ」「自社でコントロールできる」「実態に即している」を満たすこと。
では、どんな構成にすれば効果的に集客できるのでしょうか?
10年間のWEBディレクション経験から、「中小企業の集客できるホームページ」に共通する最低限必要な構成をご紹介します。
トップページ(ファーストビュー)
訪問者が最初に目にする部分です。
3秒以内に「何の会社か」「何ができるのか」を伝えます。
長い文章や複雑なアニメーションではなく、簡潔な見出しと魅力的な画像で、あなたのビジネスの価値を一目で伝えましょう。
例えば「埼玉県深谷市の工務店なら○○」といった地域性と業種がわかるタイトルや、「断熱性能で選ばれる注文住宅」といった強みを示すキャッチコピーが効果的です。
ファーストビューには必ず「お問い合わせ」などの行動喚起ボタン(CTA)を配置しましょう。
興味を持った訪問者やリピーターがすぐにアクションを起こせる環境を整えます。
会社情報・サービス紹介
信頼を築くための重要なページです。
会社の沿革や理念だけでなく、「なぜこのビジネスを始めたのか」「どんな想いで仕事をしているのか」といった背景や裏側を含めると、共感を抱いてもらいやすくなります。
サービス紹介では単なる機能や仕様の羅列ではなく、「顧客のどんな問題を解決できるのか」という視点で内容を構成し、顧客が得られるメリットを具体的に示しましょう。
事例・実績・お客様の声
「本当に信頼できる会社なのか?」という不安を解消するために、実績やお客様の声は非常に効果的です。
特に地域密着型のビジネスでは、同じ地域の顧客の声があると安心感につながります。
実名や顔写真の掲載が難しい場合でも、「埼玉県熊谷市 A様」といった形で地域性を示したり、具体的なエピソードを含めたりすることで、リアリティと信頼性を高められます。
また、事業・商品・サービスの理論、プロセスの正当性を証明する要素にもなり得ます。
お問い合わせページ
集客の最終目標である「問い合わせ」を促すページです。
フォームは必要最小限の項目にとどめ、入力の手間を減らすことが重要です。
名前、連絡先、問い合わせ内容の3項目程度でも十分です。
フォームだけでなく、電話番号やメールアドレスなど、複数の連絡手段を用意しておくと、お客様の好みに合わせた応対ができます。
さらに「お問い合わせいただいてから24時間以内に返信します」といった対応方針も明記します。
ブログ・コラム
定期的な更新が可能なブログやコラムは、SEO(検索エンジン最適化)の観点からも非常に重要です。専門知識や役立つ情報を発信することで、検索エンジンからの評価が高まり、アクセス数の増加につながります。
例えば、工務店であれば「家づくりの基礎知識」「リフォームのポイント」など、お客様が知りたい情報をテーマにした記事を定期的に投稿しましょう。1記事あたり800字程度でも十分効果があります。
集客できるホームページ制作の7STEP

では、実際にホームページを作る際の手順を見ていきましょう。私がBaseTreeで実践している7ステップの制作プロセスをもとに、中小企業が自社でも取り組める形にアレンジしてご紹介します。
STEP1:目標と予算の設定
まずは、ホームページを通じて達成したい目標を明確にしましょう。「月に10件の問い合わせを獲得したい」「地域での認知度を高めたい」など、具体的な数値目標があると良いでしょう。
同時に、投資できる予算も決めておきます。初期費用だけでなく、ドメイン・サーバー代などのランニングコストも考慮に入れてください。予算に応じて、自作するか制作会社に依頼するかも検討しましょう。
予算の目安としては、自作の場合は初期費用5万円程度+月額維持費3,000円程度から、制作会社に依頼する場合は30万円程度からが相場です。ただし、機能や規模によって大きく変動します。
STEP2:競合分析とコンテンツ計画
同業他社のホームページを5〜10サイト程度調査し、良い点・改善点をメモしておきましょう。「このサイトのここが使いやすい」「あのサイトのここが分かりにくい」といった具体的な観点で分析すると、自社サイトの方向性が見えてきます。
また、どんなページ・コンテンツが必要かを洗い出し、サイトマップを作成します。最低限、トップページ、会社案内、サービス紹介、お問い合わせページは必要です。その他、実績紹介やブログなど、自社の強みを活かせるコンテンツを検討しましょう。
STEP3:制作方法の選択
ホームページ制作方法には、主に以下の3つがあります。
- ホームページ作成サービスを利用する
Wix、Jimdo、Amebaオウンドホームページなど、専門知識がなくても直感的に作成できるサービスがあります。月額1,000円〜5,000円程度で利用できるものが多いです。 - WordPressでテンプレートを活用する
柔軟性が高く、後々の拡張も容易です。テンプレート(テーマ)を購入すれば、デザインの土台ができた状態からカスタマイズできます。 - 制作会社に依頼する
予算に余裕があれば、プロに任せるのが確実です。ただし、相見積もりを取るなど、適正価格で依頼することが重要です。
技術的な知識や時間的余裕がない場合は、1か3の選択肢が現実的です。
将来的に本格的なサイトに育てたい場合は、拡張性の高い2の選択肢がおすすめです。
STEP4:デザインとコンテンツ制作
サイトの見た目を決める段階です。
内部で制作する場合はテンプレートの中から業種や雰囲気に合ったものを選びましょう。
制作会社に依頼する場合は参考にしたいサイトや好みのデザインテイストを伝えると、イメージが共有しやすくなります。
同時に各ページに掲載するテキストや画像を準備します。
- 専門用語を避け、誰にでも分かりやすい言葉で説明する
- 自社の強みや特徴を具体的に伝える
- お客様目線で、「何が解決できるのか」を明確に示す
- 写真は明るく鮮明なものを使用する
STEP5:サイト構築と動作確認
デザインとコンテンツが揃ったら実際にサイトを構築します。
内製化する場合は選んだサービスやCMSの手順に従って作業を進めましょう。
- スマートフォンでの表示が適切か
- リンクが正しく機能しているか
- お問い合わせフォームが正常に動作するか
- 文字の誤字脱字がないか
- 画像が適切に表示されているか
特にスマートフォン表示は重要です。
現在、ウェブサイトへのアクセスの約7割はスマートフォンからと言われています。
PC画面では問題なくても、スマホでは見づらいということがよくあるので、必ず確認しましょう。
STEP6:公開と初期プロモーション
すべての確認が終わったらサイト公開です。
公開直後は、Googleなどの検索エンジンにまだ認識されていないため、以下の方法で初期プロモーションを行うことをおすすめします。
- Googleビジネスプロフィールに登録する(地域密着型ビジネスには特に重要)
- 名刺やチラシにURLを記載する
- 既存顧客にメールでサイト公開を知らせる
- FacebookやInstagramなどのSNSでシェアする
特にGoogleビジネスプロフィールは無料で登録でき、地図検索で表示されるようになるため、地域顧客に表示される可能性が高まります。
必ず登録しておきましょう。
STEP7:分析と改善
ホームページは公開して終わりではありません。
定期的にアクセス解析を確認し改善を続けることが重要です。
Google Analyticsなどの無料ツールを導入しておくと、訪問者数や行動パターンを把握できます。
- どのページが最も見られているか
- 訪問者がサイト内でどのように移動しているか
- どこから訪問者が来ているか(検索・SNS・他サイトなど)
- スマートフォンとPCの利用割合
分析結果をもとにコンテンツの追加や改善を行いましょう。
例えば特定のページの滞在時間が短い場合は、コンテンツを拡充したり抜本的に見直す必要があるかもしれません。
低コスト&自分でできるSEO対策

せっかくホームページを作っても、検索エンジンで上位表示されなければ、訪問者は増えません。
ここでは、お金をかけずにできる効果的なSEO対策をご紹介します。
※SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)とは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで上位表示されるようにホームページを最適化することです。
地域名+業種のキーワードを意識する
中小企業、特に地域密着型のビジネスにとって「埼玉県深谷市 ホームページ制作」「熊谷市 リフォーム」といった地域名と業種を組み合わせたキーワードが重要です。
これらのキーワードは競合が比較的少なく、上位表示を狙いやすいのが特徴です。
これらのキーワードをタイトルや見出し、本文中に自然な形で盛り込みましょう。
ただし、不自然に詰め込むと逆効果になるので注意が必要です。
読んでみて、声に出してみて違和感がないかをチェックしてください。
ユーザーが知りたい情報を提供する
現在のSEOで最も重要なのは「ユーザーにとって価値のある情報」を提供すること。
例えばよくある質問とその回答、業界の基礎知識、選び方のポイントなど、ユーザーが知りたい情報をブログやコラムで発信しましょう。
「〇〇の選び方」「〇〇のメリット・デメリット」といった情報は、検索されやすく、かつ購入検討者の目に留まりやすいコンテンツです。
DX化推進も担当してきた経験から言えることですが、社内に眠っている知識や経験を「見える化」しWebサイトで共有することが、SEO対策の観点でも価値があります。
画像の最適化を忘れない
画像ファイルには、適切なファイル名とalt属性(代替テキスト)を設定しましょう。
例えば「img001.jpg」ではなく「saitama-fukaya-reform-kitchen.jpg」のように、内容を表すファイル名にします。
alt属性には画像の内容を簡潔に説明するテキストを入れます。
altにテキストを入れることで画像検索からの流入も期待できます。
さらに画像ファイルサイズは小さく圧縮しておくことも重要です。
サイト表示速度はSEOの評価要素の一つであり、大きな画像ファイルはページの読み込みを遅くしてしまいます。
一方で圧縮したことにより「粗い」「汚い」「見えない」など、ユーザーが情報を取得する上で価値がなくなってしまったり、Webサイト全体のイメージから剥離したり一貫性を損なうようであれば、高解像度の画像の方が良いケースもあります。
モバイルフレンドリーを徹底する
Googleは「モバイルファースト」の考え方を採用しており、スマートフォンでの表示が適切でないサイトは検索順位が下がる傾向があります。
- 文字サイズが読みやすいか
- タップ要素(ボタンやリンク)が指で押しやすい大きさか
- 横スクロールが発生していないか
- コンテンツが画面内に適切に収まっているか
Googleの「モバイルフレンドリーテスト」というツールを使えば、自社サイトのモバイル対応状況を無料でチェックできます。
Googleビジネスプロフィールを活用する
地域密着型ビジネスにとって、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の活用は必須です。
無料で登録でき、Googleマップや検索結果の店舗情報を追加・修正できます。
- 営業時間や定休日を正確に設定する
- 店舗や商品の写真を複数アップロードする
- お客様からの口コミを増やす(満足いただいたお客様に口コミ投稿をお願いする)
- 投稿機能を活用して、新商品情報やイベント情報を定期的に発信する
特に口コミは検索順位だけでなく、ユーザーの訪問・購入意欲にも大きく影響します。
積極的に集めるようにしましょう。
中小企業こそホームページで差をつける時代
ここまで中小企業が低コストで効果的なホームページを作るための方法を紹介してきました。
最後に重要なポイントをおさらいしましょう。
- 目的を明確に:なぜホームページを作るのか、何を達成したいのかを明確にする
- コストを抑える工夫:テンプレート活用、必要機能の絞り込み、自分でできることは自分でやる
- 基本構成を押さえる:トップページ、会社情報、サービス紹介、実績・お客様の声、お問い合わせ、ブログ
- 制作プロセスを理解する:目標設定から分析・改善までの7ステップ
- SEO対策を怠らない:地域名+業種のキーワード活用、価値ある情報提供、画像最適化、モバイル対応
デジタル化が加速する現代において、中小企業にとってホームページは「あれば便利」ではなく「ビジネス成長のための必須ツール」です。
大手企業に比べて予算や人員が限られていても、工夫次第で効果的なホームページを作り、集客につなげることは十分可能です。
私がBaseTreeを創業した理由も、多くの中小企業がウェブサイトを単なる情報発信ツールではなく、営業・採用・教育・承継に活用できる「情報資産」として活用できるよう支援したいと考えたからです。
そのために「つくって終わりではなく運用が大事」を体現する事業者を目指しています。
この記事を参考に、ぜひ事業を成長させるホームページ作りに取り組んでみてください。そして、もしサポートが必要であれば、BaseTreeにお気軽にご相談ください。
ホームページ制作サービスの具体的な提供内容については、BaseTreeのWebサイト制作をご覧ください。