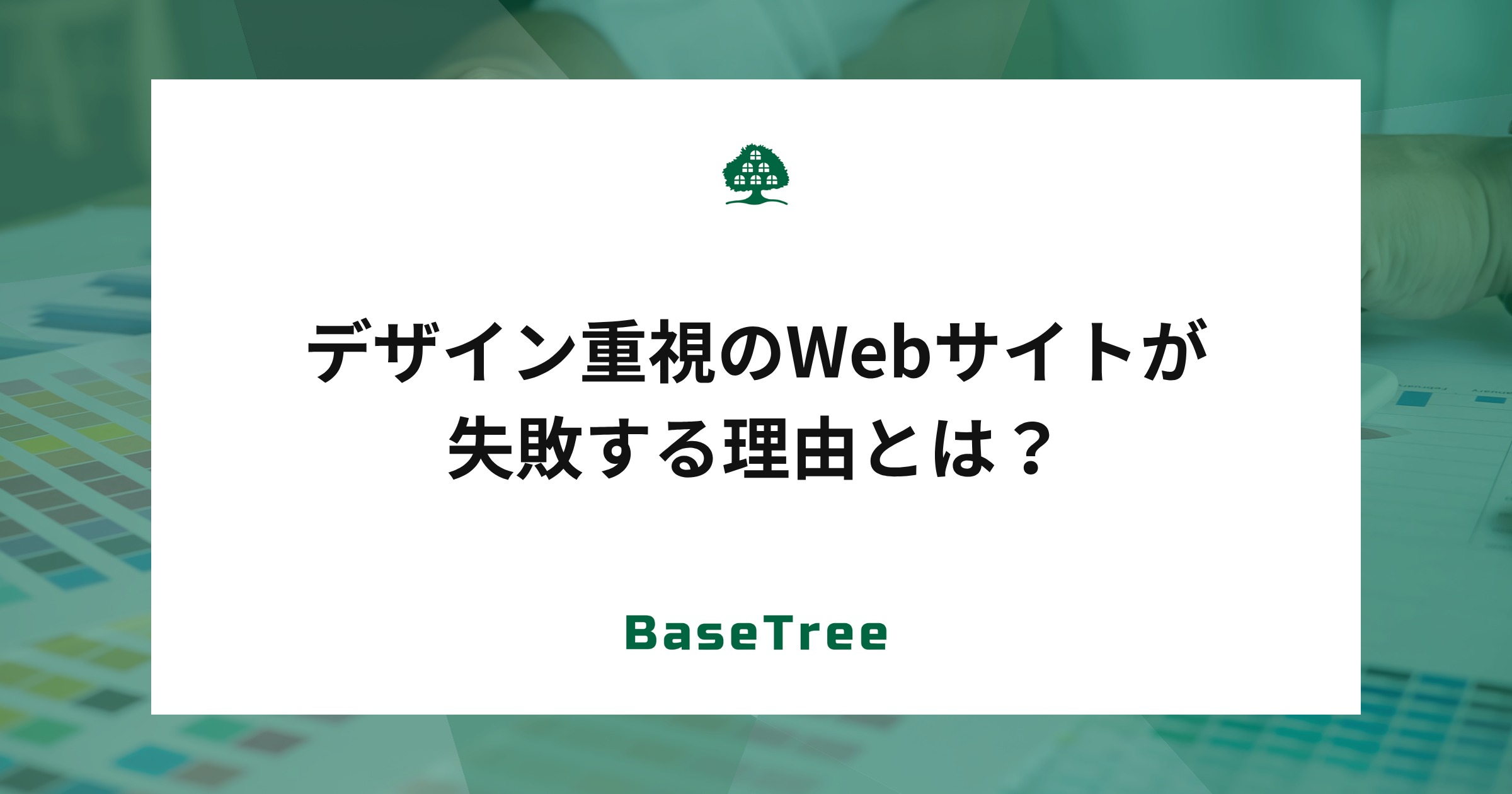「見た目の良いWebサイトを作れば成果が出る」
多くの企業がこの思い込みに囚われています。美しいデザインや最新のアニメーション効果を詰め込んだサイトは確かに目を引きますが、それだけで企業の成長につながるわけではありません。むしろ、デザインに過度に注力することで、本来のビジネス目標達成を妨げてしまうケースが少なくないのです。
10年間WEBディレクターとして様々なクライアントのサイト制作に携わってきた経験から言えることは、「見た目」だけを重視したWebサイトは、長期的な企業成長の足かせになりかねないということです。
今回は、デザインばかりに気を取られたWebサイトが企業の成長を妨げる理由と、本当に成果を生み出すサイトの条件について解説します。
なぜデザイン偏重のWebサイトは失敗するのか
デザイン偏重のWebサイトが失敗する理由は、見た目の美しさと実用性のバランスが崩れているからです。
私がこれまで関わってきた多くの企業サイトリニューアルプロジェクトでは、「競合他社よりもかっこいいサイトにしたい」という要望がよく聞かれました。しかし、そうした見栄えだけを追求したサイトの多くは、公開後に期待した成果が得られないという結果に終わっています。デザインに凝りすぎるあまり、本来のビジネス目標や顧客ニーズが二の次になってしまうのです。

デザイン重視のサイトが抱える問題点を具体的に見ていきましょう。
1. ユーザビリティの低下
過度に装飾的なデザイン要素は、サイト訪問者の操作性を損なうことがあります。
例えば、凝ったアニメーションやスクロール効果は確かに目を引きますが、情報を探している訪問者にとっては障害になりかねません。私が以前関わった美容クリニックのサイトでは、スタイリッシュなパララックス効果を全面に採用したものの、実際の予約数は旧サイトより減少してしまいました。
調査の結果、多くの訪問者が料金表や診療時間といった基本情報にたどり着けずに離脱していたことが判明したのです。
デザインが優先されると、ユーザーが求める情報への到達が難しくなり、結果としてコンバージョン率の低下につながるのです。
2. 表示速度の低下
高解像度の画像や複雑なアニメーション、重いJavaScriptファイルを多用したサイトは、読み込み時間が長くなりがちです。
サイトの表示速度は、ユーザー体験だけでなくSEO評価にも直結する重要な要素です。Googleの調査によれば、ページの読み込み時間が3秒から5秒に増えるだけで、直帰率は90%も増加するとされています。
ある製造業のクライアントサイトでは、豪華な画像ギャラリーと動画背景を採用した結果、モバイルでの表示速度が大幅に低下。アクセス解析の結果、スマートフォンユーザーの約70%がトップページの読み込み完了前に離脱していたことが分かりました。
3. 情報設計の不備
見た目のデザインに注力するあまり、情報の構造化や整理が疎かになることがあります。
美しいデザインを優先するあまり、「顧客が何を知りたいか」という視点が欠如してしまうのです。例えば、企業の歴史や理念を華やかに表現したトップページが印象的でも、訪問者が本当に求めている商品情報や問い合わせ方法が見つけにくければ、サイトとしての価値は低下します。
情報設計の不備は、単に使いにくいというだけでなく、顧客からの信頼低下にもつながります。「必要な情報が見つけられないサイト」は、その企業のサービスそのものに対する不信感を生み出してしまうのです。
どう思いますか?あなたの会社のサイトは、見た目と情報設計のバランスが取れていますか?
デザイン偏重が引き起こす具体的な問題事例
デザイン偏重のWebサイトがどのように企業の成長を妨げるのか、実際の事例を交えて詳しく見ていきましょう。
私がコンサルティングを行った中小製造業のA社では、創業50周年を機にWebサイトを全面リニューアルしました。デザイン性を重視した結果、確かに見栄えの良いサイトが完成しましたが、公開後3ヶ月経っても問い合わせ数は旧サイトの半分以下に留まっていたのです。
何が問題だったのでしょうか。詳細な分析を行った結果、以下のような問題点が浮かび上がりました。
1. 検索エンジン最適化(SEO)の軽視
デザイン重視のサイトでは、SEO対策が二の次になりがちです。
A社のケースでは、美しいビジュアルを優先するあまり、テキストコンテンツが極端に少なくなっていました。また、画像内にテキストを埋め込む手法を多用していたため、Googleのクローラーが情報を適切に認識できず、検索順位が大幅に下落していたのです。
さらに、JavaScriptを多用した動的コンテンツは、検索エンジンによる適切なインデックスを妨げることがあります。A社のサイトでは、主要な製品情報がJavaScriptで動的に生成される仕様だったため、検索エンジンからの評価が得られにくい状態になっていました。
SEO対策を軽視すると、どれだけ美しいサイトでも、そもそも顧客の目に触れる機会が失われてしまうのです。
2. コンバージョン導線の不明確さ
デザイン偏重のサイトでは、訪問者に何をしてほしいのかという「導線設計」が不明確になりがちです。
A社のサイトでは、確かに美しいアニメーションと写真で製品の魅力は伝わるものの、「問い合わせボタン」や「資料請求フォーム」へのアクセスが分かりにくく、多くの訪問者が行動に移せないまま離脱していました。
あるページでは、スクロールするとコンテンツが横方向に展開する斬新なデザインを採用していましたが、ユーザーテストの結果、多くの訪問者がこの操作方法に戸惑い、重要な情報にたどり着けていないことが判明したのです。
3. モバイル対応の不備
デザイン重視のサイトでは、PCでの見栄えを優先するあまり、スマートフォンでの表示が犠牲になることがあります。
日本のインターネットトラフィックの約70%はモバイル端末からのアクセスです。A社のサイトは確かにレスポンシブデザインを採用していましたが、複雑なアニメーションや大きな画像がモバイル環境では正常に機能せず、表示が崩れたり、操作しづらい状態になっていました。
アクセス解析の結果、PCユーザーの平均滞在時間が3分程度だったのに対し、モバイルユーザーは1分未満と大きな開きがあることが判明。モバイルユーザーの多くが、使いづらさからすぐに離脱していたのです。
あなたのサイトは、スマートフォンでも快適に閲覧・操作できますか?
本当に成果を生み出すWebサイトの条件
では、企業の成長に貢献する真に効果的なWebサイトとは、どのようなものでしょうか。
デザインを軽視せよと言っているわけではありません。重要なのは、「デザインと機能性のバランス」です。見た目の美しさと使いやすさ、そして事業目標達成のための機能が調和したサイトこそが、企業の成長を支える資産となります。
私がBaseTreeを創業した理由の一つは、「見た目だけが優先されたWebサイト」の限界を感じたからです。本当に成果を生み出すサイトには、以下の要素が不可欠です。
1. 顧客視点の情報設計
成功するWebサイトの第一条件は、顧客が求める情報を顧客が理解しやすい形で提供することです。
これは単に「どんな情報を載せるか」という問題ではなく、「どのような順序で」「どのような表現で」情報を整理するかという点が重要です。顧客の知りたいことを顧客の言葉で、顧客の思考の流れに沿って提示できているサイトは、自然とコンバージョン率が高くなります。
例えば、製造業のクライアントサイトをリニューアルした際、従来の「会社の歴史→事業内容→製品紹介」という企業視点の構成から、「どんな課題を解決できるか→具体的な解決事例→製品詳細→会社情報」という顧客視点の構成に変更したところ、問い合わせ数が3倍に増加した事例があります。
顧客視点の情報設計は、訪問者の「知りたい」「理解したい」「行動したい」というニーズに応えることで、自然とコンバージョンへと導くのです。
2. 明確な導線設計
効果的なWebサイトは、訪問者を迷わせることなく、目的の行動へと導きます。
サイトの各ページには明確な目的があり、訪問者にとって次に何をすべきかが分かりやすく示されていることが重要です。例えば、製品紹介ページであれば「詳細を見る」「お問い合わせ」「資料をダウンロード」など、具体的な次のステップが明示されているべきです。
あるBtoB企業のサイトリニューアルでは、各ページに「このページでできること」を明示し、関連する行動ボタンを目立つ位置に配置する設計に変更しました。その結果、サイト内の回遊率が40%向上し、資料ダウンロード数が2倍に増加したのです。
3. 適切なテクノロジー選択
Webサイトの構築には様々な技術が使われますが、最新技術を採用することが必ずしも最適解ではありません。
重要なのは、サイトの目的と予算、運用体制に合わせた適切な技術選択です。例えば、頻繁に更新が必要なコンテンツが多いサイトであれば、社内スタッフでも更新しやすいCMSの導入が不可欠です。また、将来的な拡張性を考慮したシステム設計も重要な要素となります。
ある中小企業では、最新のヘッドレスCMSを採用したものの、運用担当者が使いこなせず更新が滞ってしまったケースがありました。結局、より直感的に操作できるWordPressに移行し、情報更新の頻度が大幅に向上したという事例もあります。
最新技術の採用自体が目的化してしまうと、かえって運用の負担となり、サイトの価値を低下させることがあります。
4. 計測と改善の仕組み
成果を生み出すWebサイトは、公開して終わりではなく、継続的な計測と改善が行われています。
アクセス解析ツールを活用し、訪問者の行動データを収集・分析することで、サイトの問題点や改善点を特定できます。例えば、特定のページでの離脱率が高い場合、そのページのコンテンツや導線に問題がある可能性が高いと言えます。
私がサポートしている企業では、月次でアクセス解析レポートを確認し、データに基づいた改善を継続的に行っています。あるECサイトでは、カート離脱率の高さに着目し、購入プロセスを簡略化する改修を行った結果、コンバージョン率が1.5倍に向上した事例もあります。
最高のWebサイトとは、完璧な状態で公開されるものではなく、継続的な改善によって進化し続けるものです。
情報構造設計を重視したWebサイト制作アプローチ
では、デザイン偏重の罠に陥らず、真に成果を生み出すWebサイトを構築するには、どのようなアプローチが有効でしょうか。

BaseTreeでは、「情報構造設計」を最重視したWebサイト制作を行っています。これは単なるデザインや技術の問題ではなく、企業が持つ価値を顧客視点で整理・構造化し、効果的に伝えるための体系的なアプローチです。
具体的には、以下のようなプロセスで進めています。
1. 徹底したヒアリングと情報収集
Webサイト制作の第一歩は、クライアント企業の事業内容や強み、課題を深く理解することです。
私たちは初回のミーティングで「なぜWebサイトが必要なのか」「どんな成果を期待しているのか」といった本質的な質問から始めます。表面的なデザインの好みではなく、ビジネスゴールを明確にすることで、真に効果的なサイト設計の土台を築きます。
例えば、ある建設会社のサイト制作では、「施工事例をカッコよく見せたい」という当初の要望から、詳細なヒアリングを通じて「地元の住宅オーナーからのリフォーム依頼を増やしたい」という本質的なゴールを特定。それに基づいて、地域密着型の安心感を伝える構成と、リフォーム事例を中心としたコンテンツ設計に変更しました。
あなたは自社のWebサイトに何を期待していますか?見た目の良さだけでなく、具体的なビジネス成果を考えてみてください。
2. サイトマップとワイヤーフレームの作成
情報設計の核心は、サイトマップとワイヤーフレームの作成にあります。
サイトマップでは、サイト全体の構造と階層を設計します。ここで重要なのは、訪問者の思考プロセスに沿った情報の配置です。「この情報を知りたい人は、次に何を知りたいと思うか」という視点で情報を整理することで、自然な導線が生まれます。
ワイヤーフレームは、各ページのレイアウトと要素の配置を示す設計図です。この段階では装飾的なデザイン要素は排除し、情報の優先順位と導線に集中します。「このページで最も伝えたいことは何か」「訪問者にどんな行動を促したいか」という視点で要素を配置していきます。
あるメーカーのサイト制作では、従来の「製品カテゴリ別」の構成から、「顧客の課題別」の構成に変更。製品スペックよりも、その製品がどんな問題を解決できるかを中心に情報を再構築しました。その結果、技術に詳しくない新規顧客からの問い合わせが増加したという事例もあります。
3. 目的に合わせたデザイン制作
情報構造が固まった後に、ようやくビジュアルデザインの段階に進みます。
この順序が極めて重要です。デザインは情報構造を視覚的に表現し、強化するものであり、その逆ではありません。「見た目が良い」だけでなく、「情報が伝わりやすい」「目的の行動に結びつきやすい」デザインを追求します。
例えば、重要な情報ほど視線を集めやすい位置や大きさで表示する、関連情報は視覚的にグルーピングする、行動を促したいボタンは目立つ色や形状にするなど、情報の重要度や関連性を視覚的に表現することがデザインの本質的な役割です。
ある医療機関のサイトでは、診療内容よりも「初診の予約方法」と「アクセス情報」を最も目立つ位置に配置するデザインに変更。実際の患者さんの行動パターンに合わせたデザインにすることで、電話での問い合わせが減少し、Webからの予約率が向上した例もあります。
成果を生み出すWebサイト制作のためのチェックリスト
最後に、あなたの会社のWebサイトが真に成果を生み出す「経営資源」となっているかを確認するためのチェックリストをご紹介します。
以下の項目を確認してみてください。「いいえ」の項目が多いほど、サイトの見直しが必要かもしれません。
1. 目的と戦略の明確さ
□ Webサイトの具体的な目的(問い合わせ増加、認知度向上など)が明確に定義されている
□ ターゲットとなる顧客層が明確に特定されている
□ 競合他社との差別化ポイントがサイト上で明確に伝わる
□ サイトの各ページに明確な目的がある
これらの項目は、サイト制作の前提となる戦略の明確さを問うものです。目的やターゲットが曖昧なまま制作されたサイトは、見た目が良くても成果につながりにくいでしょう。
2. 情報設計の質
□ 訪問者が求める情報に3クリック以内でたどり着ける
□ 情報が顧客視点で整理されている(企業視点ではなく)
□ 各ページの主要メッセージが明確で、一目で理解できる
□ 専門用語や業界用語が適切に説明されている
情報設計の質は、訪問者の使いやすさと情報の伝わりやすさを左右します。特に、自社の常識や業界用語をそのまま使用していないかという点は要注意です。
3. ユーザビリティとアクセシビリティ
□ スマートフォンでも快適に閲覧・操作できる
□ ページの読み込み速度が十分に速い(3秒以内が理想)
□ ナビゲーションが直感的で使いやすい
□ 色覚多様性に配慮した配色になっている
使いやすさは、訪問者の滞在時間とコンバージョン率に直結します。特にモバイル対応と表示速度は、近年ますます重要性が高まっている要素です。
4. コンテンツの質と量
□ 顧客の疑問や課題に答える有益なコンテンツが充実している
□ 文章が読みやすく、専門知識がなくても理解できる
□ 画像や動画が適切に使用され、内容を補強している
□ コンテンツが定期的に更新されている
コンテンツは、訪問者の信頼を獲得し、専門性を示すための重要な要素です。特に、「自分たちの製品・サービスについての説明」だけでなく、「顧客の課題解決に役立つ情報」を提供できているかがポイントです。
5. 計測と改善の体制
□ アクセス解析ツールが適切に設定されている
□ 定期的にデータを確認し、改善点を特定している
□ コンバージョン率や主要指標の目標値が設定されている
□ A/Bテストなど、データに基づく改善を行っている
Webサイトは公開して終わりではなく、継続的な改善が重要です。特に、「何となく良さそう」ではなく、データに基づいた客観的な評価と改善が成果につながります。
いかがでしょうか?チェック項目に「いいえ」が多い場合は、デザインだけでなく、サイト全体の戦略や構造を見直す必要があるかもしれません。
デザインと情報設計のバランスが成功の鍵
Webサイトは、単なる「会社の看板」ではなく、成果を生み出す「経営資源」です。
デザイン偏重のWebサイトが企業の成長を妨げる理由は、見た目の美しさだけを追求するあまり、本来の目的である「情報伝達」や「行動促進」が二の次になってしまうからです。真に効果的なサイトとは、デザインと情報設計のバランスが取れたものであり、顧客視点で構築された情報発信基盤なのです。
私たちBaseTreeは、「情報構造設計の精度」「段階的な拡張」「SEO知見に基づく構築技術」「健全なインフラ管理体制」を特徴とするWebサイト制作を通じて、クライアント企業の成長を支援しています。
Webサイトを真の経営資源として活用するためには、まず「何のためのサイトか」「誰に何を伝えたいのか」という本質的な問いから始める必要があります。その上で、顧客視点の情報設計、明確な導線設計、適切なテクノロジー選択、そして継続的な計測と改善が重要です。
デザインは決して軽視すべきものではありません。しかし、デザインはあくまで「目的を達成するための手段」であり、それ自体が目的化してはならないのです。
あなたの会社のWebサイトは、見た目の美しさと実用性のバランスが取れていますか?真に成果を生み出す「経営資源」となっているでしょうか?
Webサイトの見直しや改善をお考えの際は、ぜひ情報構造設計を重視したアプローチを検討してみてください。
埼玉県深谷市を拠点に、熊谷市や本庄市など埼玉県北部と群馬県の中小企業向けにWebサイト制作サービスを提供するBaseTreeでは、企業価値を顧客視点で翻訳・整理し、「成果を生み出す経営資源」として機能する情報発信基盤の構築をサポートしています。詳しくはwebサイト制作のページをご覧ください。