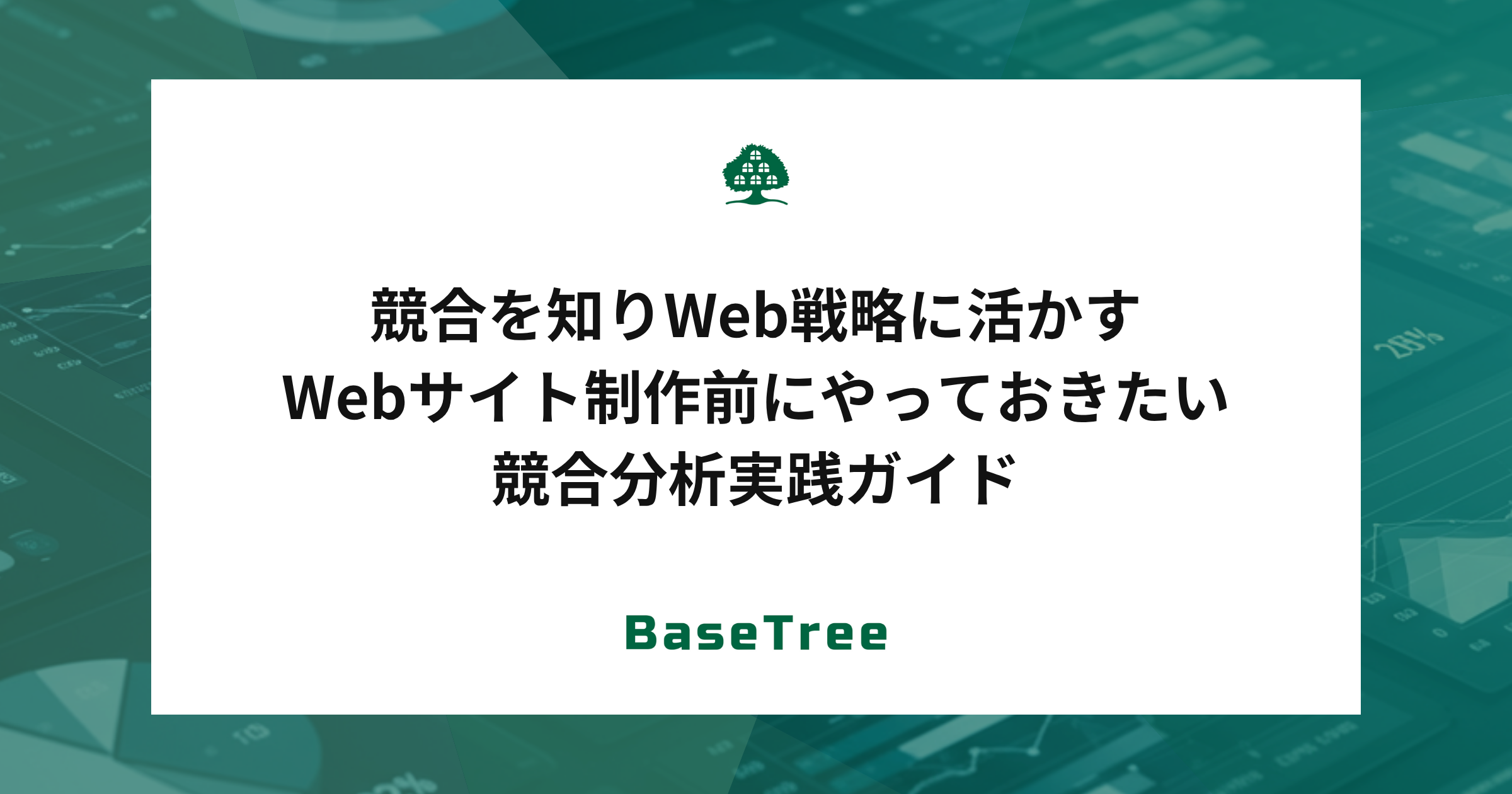なぜWebサイト制作前の競合分析が不可欠なのか?
Webマーケティングを成功させるには、競合サイトの分析が欠かせません。
なぜWebサイト制作前の競合分析が重要なのでしょうか?
それは「どうすれば競合に勝てるのか」という問いに答えるために、まず競合が何をしているのか知る必要があるからです。
多くの企業が「とりあえずホームページを作ろう」と自社の情報を詰め込んだWebサイトを制作します。
しかし、そのようなサイトは成果につながらないケースが非常に多いのです。
この記事では、Webマーケティングにおける競合サイト分析の重要性から具体的な分析手法、そして分析結果をどのように活用すべきかを解説します。
7つの必須チェック項目を中心に、貴社のWebマーケティング戦略を一段階上のレベルへと引き上げる参考になれば幸いです。
競合サイト分析とは?Webマーケティングにおける重要性
競合サイト分析とは?
競合サイト分析は、単に「ライバルの真似をする」ためではありません。
同じ市場で戦っている企業のWebサイトを調査・分析し、競合の強みと弱み、情報設計の特徴、ユーザー体験の設計方法、そして何より「顧客に対してどのような価値提案をしているか」を理解することです。
この分析なしにWebサイトを作ることは、地図なしで未知の土地を歩くようなもの。
市場の動向を把握し、ユーザーのニーズを理解し、そして自社の強みを最大限に活かすための重要なステップです。
競合サイト分析の重要性
Webマーケティングにおいて競合サイト分析が重要な理由は、市場における自社の立ち位置を客観的に把握し、差別化戦略を立てるためです。
競合が何をしているか知らなければ、自社の強みを最大限に活かすことはできません。
特に近年のデジタルマーケティング環境において、ユーザーは複数のサイトを比較検討してから購入や問い合わせに至るケースが一般的です。
つまり競合との違いを明確に打ち出せるかどうかが成果を左右します。
競合分析を行うことで得られるメリット
- 市場における自社の立ち位置を客観的に把握できる
- 競合が見落としている顧客ニーズを発見できる
- 効果的な差別化戦略を立てられる
- 業界標準のUX/UIを理解した上で改善点を見出せる
- コンバージョン率向上につながる要素を特定できる
中小企業が限られたリソースを最大限に活かすためには、競合分析に基づいた戦略的なWebサイト設計が不可欠です。
では、具体的に何を分析すればよいのでしょうか?
次に競合サイト分析の基本的なステップと、7つのチェック項目について記載します。
競合サイト分析の基本ステップ
競合サイト分析を効果的に行うには体系的なアプローチが必要です。
以下の3つの基本ステップを押さえておきましょう。

1. 競合を特定する
まず最初に行うのは、本当の意味での「競合」を特定すること、分析すべき競合サイトを正確に特定すること。
多くの企業が「同じ地域・業種の企業」を競合と考えがちですが、実際には「顧客から見て同じ課題を解決する選択肢となる企業」が真の競合です。
対面やリアルな場での競合と、デジタル上の競合が必ずしも一致するとは限りません。
例えば、地域密着型の税理士事務所の場合、同じエリアで営業している他の税理士事務所だけでなく、オンライン完結型の税務サービスや、大手の税理士法人の地方支店なども競合です。
競合を特定するポイント
- 直接競合:同じ商品・サービスを提供している企業
- 間接競合:異なる方法で同じ顧客ニーズを満たしている企業
- 潜在競合:現在は競合ではないが、将来的に市場に参入する可能性がある企業
注目すべき3〜5社程度の競合を選定します。
全ての競合を分析しようとすると時間がかかりすぎるため、市場シェアの大きい企業や、特に自社と似た価値提案をしている企業に絞ることをおすすめします。
競合サイトの特定方法
- 自社の主要キーワードでGoogle検索を行い、上位表示されているサイトをリストアップする
- 自社と同じ市場・同じ顧客層をターゲットにしている企業のサイトを確認する
- 業界内で知名度の高い企業のサイトをチェックする
SEO観点では同じキーワードで上位表示を争うサイトが「デジタル上の競合」です。
同業種や同規模でなくとも、同じ検索クエリで上位表示されるサイトは重要な分析対象です。
2. 競合サイトを調査する
競合を特定したら、次は具体的な調査です。
後述する7つのチェック項目を中心に、競合サイトの特徴や戦略を詳細に分析します。
調査の際は単に「見た目」だけでなく、サイト構造やコンテンツ戦略、SEO施策、ユーザー体験など、多角的な視点で分析することが重要です。
複数の競合サイトを比較することで、業界全体のトレンドや標準的な施策も把握できます。
競合サイト分析を通じて、競合がどのような顧客層をターゲットにしているのか、どのような価値提案を重視しているのかが見えてきます。
例えば「業界内のほとんどの企業が技術的な特徴を前面に出している一方で、導入後のサポート体制についての情報が不足している」という発見があったとします。
これを踏まえると、「導入から定着までのサポート体制を差別化ポイントにする」という価値提案や訴求を試す価値がありますよね。
3. 調査結果を分析・活用する
収集した情報を整理し自社サイトとの比較分析を行います。
競合サイトの長所・短所を客観的に評価し、自社サイトに取り入れるべき要素や差別化すべきポイントを明確にします。
分析結果は、SWOT分析やSTPなどのフレームワークを活用して整理するとより立体的・多面的に理解が深まります。
エクセルなどで単純な比較表を作成するのも実用的な方法です。
重要なのは、分析結果を自社のWebマーケティング戦略に具体的にどう活かすかを明確にすること。
チームが理解でき、いつでも誰でも競合調査結果を参照できる状態がベストです。
競合サイト分析の7つの必須チェック項目
競合サイト分析を行う時は「7つのチェック項目」を重点的に評価してみてください。
競合サイトの強みと弱み、そして自社サイトの改善点が明確になります。

1. サイト構造とユーザー体験
競合サイトのサイト構造とユーザー体験(UX)は、最も基本的かつ重要なチェック項目です。
- ナビゲーション構造:メニュー項目の配置や階層構造
- 情報アーキテクチャ:コンテンツの分類や配置の論理性
- ユーザーフロー:訪問者がどのような導線で情報を得て、コンバージョンに至るか
- モバイル対応:レスポンシブデザインの実装状況や使いやすさ
- ページ読み込み速度:画像やコードの圧縮、タイムライン、視覚効果など
- フォームの使いやすさ:設問項目、入力補助、入力完了ページなど
競合サイトがユーザーをどのように重要なページへ誘導しているかを調査します。
トップページで最も目立つ位置に何を配置しているか?
メインナビゲーションの項目と順序は?
サービス紹介ページの構成やどこまで詳細に記載している?
CTA(お問い合わせ、電話など)の配置位置と表現方法は?
など、ホームページから商品・サービスページ、そして問い合わせや購入ページへの導線が明確になっているサイトは、コンバージョン率も高い傾向にあります。
また、ページの読み込み速度もユーザー体験に大きく影響します。
Google PageSpeed Insightsなどのチェックツールを使って、競合サイトのパフォーマンスをチェックしてみましょう。
2. デザインとブランディング
競合サイトのデザインとブランディング要素は、そのブランドの個性や市場でのポジショニングを反映しています。
- カラースキーム:使用している主要カラーとアクセントカラー
- タイポグラフィ:フォントの種類、サイズ、行間、階層など
- ビジュアル要素:画像、動画、図解、アイコン、イラストの使い方
- 全体的なトーンと雰囲気:フォーマル、カジュアル、革新的、伝統的などブランドイメージの一貫性
これらの要素を分析することで、業界内でのデザイントレンドや、競合がどのようなブランドイメージを構築しようとしているかが見えてきます。
自社サイトのデザインリニューアルを検討する際の参考になるでしょう。
ただし、単に「見た目がいい」デザインを真似るのではなく、ターゲットユーザーにとって使いやすく、自社のブランド価値を効果的に伝えるデザインを目指すことが重要です。
競合サイトを実際にスマートフォンで閲覧し、ユーザーとして体験してみることをおすすめします。
現在、Webサイトへのアクセスの約80%はスマートフォンからと言われており、スマートフォンでの使いやすさは非常に重要です。
3. コンテンツ戦略
競合サイトのコンテンツ戦略は事業・商品の強みや、ターゲットユーザーのニーズへの対応方法を示しています。
- コンテンツの種類:ブログ記事、ケーススタディ、ホワイトペーパー、動画など
- コンテンツのトピック:どのような話題に焦点を当てているか
- コンテンツの質と深さ:表面的な情報か、詳細で専門的な内容か
- 更新頻度:どのくらいの頻度で新しいコンテンツを公開しているか
- コンテンツの配置:重要なコンテンツをどこに配置しているか
- 専門性とわかりやすさ:専門用語と平易な言葉のバランス
- 事例・実績の見せ方:件数、カテゴリやタグ、ページ構成
- よくある質問の内容と回答方法:数、回答の粒度、内部リンクの有無、まとめページの有無
競合のコンテンツ戦略を分析することで、業界内で注目されているトピックや、ユーザーが求めている情報の種類が見えてきます。
競合がカバーしていない領域(コンテンツギャップ)を発見できれば、それは自社が差別化できる絶好の機会です。
特に注目すべきは、競合サイトの「顧客の声」や「事例紹介」と、「お役立ち情報」などの人気コンテンツ。
「顧客の声」や「事例紹介」は顧客がどのような課題を抱えていて、それをどのように解決したのかを示す貴重な情報源です。
「お役立ち情報」はSEO対策語句の類推や、内部リンクの貼り方、サイドメニューに何を置いているのか、どのページに収斂されていくのかなど、自社のコンテンツ企画やリンクビルディング(自サイトの重要ページに到達しやすくすること)の参考にできます。
競合サイトの中で最もシェアされているコンテンツと、そのコンテンツが人気を集めている理由を分析し、自社のコンテンツ戦略に活かしましょう。
多くの企業が「自社の製品・サービスの機能や特徴」を中心にコンテンツを構成しがちですが、実際に成果を上げているサイトは「顧客の課題とその解決方法」を中心に据えています。
一度、自分が顧客の立場になって考えてみてください。
あなたは「この会社のサービスの機能一覧」と「この会社がどのように私の問題を解決してくれるのか」のどちらに興味がありますか?
答えは明らかですよね。
実績があるのならば、まずは顧客にアンケートを行って「実績」や「事例」から拡充していきましょう。
4. SEO戦略とキーワード戦略
競合サイトのSEO戦略を分析することで、検索エンジンでの露出や上位表示の可能性を高めるためのヒントが得られます。
- ターゲットキーワード:タイトルタグ、見出し、URLなどで使用されているキーワード
- メタデータ:タイトルタグとメタディスクリプションの書き方
- 内部リンク構造:重要ページへの内部リンクの配置方法
- コンテンツの構成:見出し(H1、H2など)の使い方や文章の構成
- 被リンク(外部からのリンク):どのようなサイトからリンクを獲得しているか
特に重要なのは、競合サイトがどのキーワードで上位表示されているかを把握すること。
顧客はどのようなキーワードで検索し、競合サイトに辿り着いているのかを知る術です。
業界や商材に精通するほど専門用語や業界用語を使って検索してくるだろうと想像しがちですが、顧客は異なる言葉で検索していることが多いのです。
例えばBaseTreeでは「Webサイト制作」で基本的に統一していますが、顧客は「ホームページ作成」と検索するかもしれません。
このギャップを理解し、顧客の言葉でコンテンツを作ることが重要です。
SEO分析ツールを使えば、競合サイトの上位キーワードや、そのキーワードでの検索ボリュームを確認できます。
どのようなコンテンツが最も多くのトラフィックを集めているか類推も可能です。
競合サイトの被リンク分析をすることで、効果的なリンク獲得戦略のヒントも得られます。
どのようなサイトからリンクを獲得しているか、どのようなコンテンツが多くリンクされているか調査してみましょう。
5. トラフィックと流入経路
競合サイトのトラフィック量や流入経路を分析することで、効果的なマーケティングチャネル(集客経路、アクセス経路)や集客戦略のヒントが得られます。
- トラフィック量:月間訪問者数や閲覧ページ数
- トラフィックソース:オーガニック検索、直接訪問、ソーシャルメディア、参照元サイトなど
- 地域分布:どの国や地域からのアクセスが多いか
- デバイス分布:デスクトップとモバイルの割合
競合サイト分析ツールを使うと、競合サイトのトラフィック推定値や流入経路の内訳を確認できます。
特に注目すべきは競合サイトの「トラフィックソース」です。
例えばソーシャルメディアからの流入が多い競合サイトがあれば、そのソーシャルメディア戦略を詳しく調査する価値があります。
参照元サイトからの流入(外部サイトからのリンク)が多い場合は、どのようなサイトとパートナーシップを結んでいるかチェックしましょう。
6. マーケティング施策とCTA(行動喚起)
競合サイトのマーケティング施策やCTA(Call To Action)の設計は、コンバージョン戦略を類推する上で重要です。
- リード獲得方法:資料ダウンロード、メルマガ登録、無料トライアルなど
- CTAの配置と表現:ボタンのデザイン、テキスト、配置場所
- ランディングページの構成:見出し、メリット説明、社会的証明など
- 特典や限定オファー:どのような特典を提供しているか
競合サイトのCTA分析は、効果的なコンバージョン導線の設計方法や、ユーザーの行動を促す表現方法のヒントが得られます。
特に注目すべきは、競合サイトがどのような特典や保証を提供してリード(問い合わせ)を獲得しているのか。
無料eBook、ウェビナー、チェックリストなど、様々な形式のリードマグネット(顧客情報取得のための特典)が使われていますが、それぞれにターゲットとする顧客層や購買段階が異なります。
1ユーザーになって競合サイトを閲覧し、どんな特典がもらえるから問い合わせをしてみようと思ったか、この特典を得る対価としてユーザーは何を提供するのか?購買段階に応じて特典をどのように使い分けているのか?など顧客目線での検証をおすすめします。
7. 差別化ポイントと価値提案
競合サイトがどのように自社の強みや独自の価値を伝えているかを分析しましょう。
- USP(Unique Selling Proposition):独自の強みや特徴をどう表現しているか
- 価値提案:顧客にどのような価値や解決策を提供すると約束しているか
- ターゲット顧客:どのような顧客層をメインターゲットとしているか
- ブランドストーリー:どのようなストーリーでブランドの魅力を伝えているか
競合サイトの差別化ポイントを分析することで、市場内での各社のポジショニングが見えてきます。
同時に、自社が強調すべき独自の強みや、まだ満たされていない市場ニーズを特定できます。
特に重要なのは、競合サイトが「なぜ自社を選ぶべきか」をどのように説明しているか。
価格、品質、専門性、サービス、実績など、どの角度からどんな切口で差別化を図り、「自社を選ぶべきだ」と主張しているのかを整理します。
この「差別化ポイント」について、次章で詳しく見ていきます。
競合分析から差別化ポイントを見つける方法
競合分析を行っただけで終わりにせず、得た情報を自社サイトに活かす上で最も重要なのは「自社の差別化ポイント」を明確にすること。
単に「他社と違うこと」を探すのではなく、「顧客にとって価値があり、かつ自社が提供できる独自の強み」を特定することです。

ギャップ分析で市場の隙間を見つける
競合分析の結果を元に、市場における「ギャップ」を特定します。
競合が対応していないニーズや、不十分にしか対応できていない領域のことです。
- 顧客の主要なニーズをリストアップする
- 各競合がそれぞれのニーズにどの程度対応しているか評価する
- 対応が不十分な領域を特定する
- 自社がそのギャップを埋められるか検討する
顧客の悩みに寄り添い、それを解決する方法を明確に示すことで、競合との「価値ある差別化」が可能に。
「顧客が求めることで、誰も満たせていないこと」
「顧客の求めに対応はしているが、不満や不安が解消されていないこと」
「自社が今持っている資源を組み替えや入れ替えすると提供できること」
「解消の仕方が、自社の理念や社会通念上反しないこと」
リソースが限られる中小企業にとって、これらを念頭にギャップを見つめていただくと、現実的で成功確率の高いギャップの埋め方が見つかるはずです。
自社の強みを客観的に評価する
差別化ポイントを見つけるためには、自社の強みを客観的に評価することが重要です。
- 顧客にとっての価値:この強みは顧客にとってどれだけ重要か
- 競合との比較:この強みは競合と比べてどれだけ優れているか
- 持続可能性:この強みは長期的に維持できるか
例えば「迅速な対応」を強みとして挙げる企業は多いですが、それが本当に競合と比べて優れているのか、顧客にとって決定的な価値があるのかを客観的に評価する必要があります。
同じ工数で同じ納期で提供できる競合がいれば「迅速だけが強み」だと、途端に強みを失います。競合よりも高品質だったり、性能が高いのに同じ価格帯だったり、専任性だったり、オンラインではなく訪問による膝を突き合わせた提供方法だったり…。これらとかけ合わせで「迅速な対応」までできる競合がいなければ、そこで初めて強みと言えるかもしれません。
1週間ぐらいの納期を見込んでいて、それを遅延するようであると困るが、大幅な短縮は求めていない。短縮することで特急料金がかかったり、工程がカットされたり、品質が落ちる方が問題だと多くの顧客が考えるのであれば、顧客にとって「迅速な対応」はメリットではなく、すなわち「選ぶ理由」にはならないということです。
自社の強みを過大評価せず、現実的な視点で評価することが重要です。
時には社外の視点を取り入れることも有効です。
顧客視点での価値提案を構築する
競合分析と自社の強みの評価を踏まえて、顧客視点での価値提案(バリュープロポジション)を構築します。
「なぜ顧客が自社を選ぶべきなのか」を明確に説明するものです。
- 顧客の課題や悩みへの理解を示す
- その課題をどのように解決するかを具体的に説明する
- 解決によってもたらされる具体的なメリットを示す
- なぜ自社がその解決に最適なのかの理由を提示する
BaseTreeで大切にしているのは、「Webサイトは経営資源」という価値提案です。
これは多くの企業が抱える営業・採用・承継という課題に対する解決策であり、他のWeb制作会社とは異なる独自の価値提案です。
あなたの会社ならではの価値提案は何でしょうか?
それを明確にしWebサイトの中心に据えることで、競合との差別化が図れます。
競合サイト分析結果の活用方法
競合サイト分析で得た情報は、適切に活用することで大きな価値を生み出します。
ここでは分析結果を効果的に活用するための具体的な方法を紹介します。

自社サイトの改善点を特定する
競合サイトとの比較を通じて、自社サイトの改善すべき点が明確になります。
- ユーザー体験:ナビゲーション、情報の見つけやすさ、モバイル対応など
- コンテンツの質と量:競合と比較して不足している情報や、深掘りすべきトピック
- デザインとブランディング:時代遅れになっている要素や、ブランドイメージを強化すべき部分
- 技術的な側面:ページ速度、SEO最適化、セキュリティなど
競合サイトの優れた点を参考にしつつも、単なる模倣ではなく自社の強みや独自性を活かした改善を心がけましょう。
差別化戦略を構築する
競合サイト分析の最も重要な成果の一つは、効果的な差別化戦略の構築です。
- 競合サイトの共通点を特定する(業界標準となっている要素)
- 競合サイト間の違いを分析する(各社の差別化ポイント)
- 競合がカバーしていない市場ニーズや領域を特定する(ブルーオーシャン)
- 自社の強みと、特定した市場機会を組み合わせて独自の価値提案を構築する
差別化戦略は、単に「違う」だけでなく、ターゲット顧客にとって意味のある違いを生み出すことが重要です。
競合が提供していない価値や、競合よりも優れた方法で提供できる価値に焦点を当てましょう。
コンテンツ戦略の最適化
競合サイト分析から得た洞察を基に、効果的なコンテンツ戦略を構築できます。
- 競合がカバーしていないキーワードやトピックを特定し、コンテンツギャップを埋める
- 競合の人気コンテンツを参考に、より深く、より価値の高いコンテンツを作成する
- 競合のコンテンツ形式(ブログ、動画、インフォグラフィックなど)のバランスを分析し、不足している形式を強化する
- 競合のコンテンツ更新頻度を参考に、適切な公開スケジュールを設定する
コンテンツ戦略の最適化は単に量を増やすのではなく、質と関連性を伴ってコンテンツを拡充していくことが重要です。
ターゲットユーザーにとって本当に価値のあるコンテンツを提供することを目指しましょう。
マーケティング施策の優先順位付け
競合サイト分析の結果を基に、効果的なマーケティング施策の優先順位を決定できます。
- 競合と比較して最も差が大きい領域に優先的にリソースを投入する
- 競合が成功を収めている施策を参考に、自社に適した形で導入を検討する
- 競合が活用していない新しいマーケティングチャネルや手法を特定し、先行者利益を得る
- 短期的な成果が見込める「低hanging fruit(手の届きやすい果実)」と、長期的な競争力強化のための施策のバランスを取る
マーケティング施策の優先順位付けでは、ROI(投資対効果)を重視することが重要です。限られたリソースを最も効果的に活用するために、期待される成果と必要なリソースのバランスを考慮しましょう。
競合分析に基づくWebサイト設計の実践ポイント
競合分析を行い差別化ポイントを特定したら、次はWebサイト設計に反映させる段階です。
ここでは、実践的なポイントをご紹介します。

情報構造に差別化要素を組み込む
Webサイトの情報構造(サイトマップ)に、差別化要素を効果的に組み込むことが重要です。
- トップページの最も目立つ位置に差別化ポイントを配置する
- メインナビゲーションに差別化要素を反映させる
- 競合が見落としている情報を積極的に取り入れる
- 顧客の意思決定プロセスに沿った情報の流れを設計する
例えば競合分析で「アフターサポート」が市場のギャップであると判明した場合、「サポート体制」をメインナビゲーションに追加し、トップページでも目立つ位置に配置する策が考えられます。
情報構造の設計では「顧客がどのような順序で情報を求めるか」を常に意識することが重要です。
競合と差別化されたビジュアル表現
Webサイトのデザインも競合との差別化を図る重要な要素です。
- 競合分析で把握した業界の標準的なデザインを理解した上で、差別化を図る
- 自社のブランドイメージに合ったカラースキームを選択する
- 写真やイラストの使い方で独自性を出す
- レイアウトやタイポグラフィで差別化を図る
ただし、あまりに業界標準から外れたデザインは、ユーザーの混乱を招く可能性があります。「認知しやすさ」と「差別化」のバランスを取ることが重要です。
見慣れない・感覚的に操作できない・次に何が展開されるか予想がつかないWebサイトは当然ながら見慣れるまでに時間を要するので、内容理解に欠けたり離脱されたり…競合と差別化するために独自のビジュアルを採用したからといって、閲覧されなければ本末転倒です。
例えば保険業界では青や緑を基調とした信頼感のあるデザインが多い中で、あえて温かみのあるオレンジや茶色を使うことで、「親しみやすさ」を差別化ポイントにすることができます。
コンテンツ戦略に競合分析の知見を活かす
Webサイトのコンテンツ戦略にも競合分析の知見を活かしましょう。
- 競合が取り上げていないトピックを積極的に取り入れる
- 顧客の言葉(業界用語ではなく)を使ったコンテンツを作成する
- 事例や実績の見せ方を工夫する
- FAQセクションで競合が答えていない質問に回答する
特に重要なのは、「顧客の言葉」を使ってコンテンツを作成することです。
競合分析を通じて把握した顧客の検索キーワードを活用し、顧客が理解しやすい言葉でコンテンツを作成しましょう。
競合サイトのコンテンツを分析する中で「これは説明が不十分だ」と感じたり、「そうじゃないんだよな」という点があれば、それが御社の価値観であり主張です。
自社サイトではその点を詳しく解説することで差別化を図ることができます。
競合分析を継続的に行うための体制づくり
競合分析は一度行って終わりではなく継続的に行うことが重要です。
貴社がWebサイトを見直そうとしているように、市場環境や競合の戦略は常に変化しており、それに合わせて自社の戦略も調整する必要があるからです。
定期的なモニタリングの仕組み
競合を定期的にモニタリングする1番の方法は、定期的にチェックする「仕組み」を作流こと。
- 四半期ごとに主要競合のWebサイトをチェックする
- 競合のSNSアカウントをフォローし、1日1回は投稿や動向を把握する
- 検索対策キーワードで1日1回は実際に検索し、競合と自社サイトの順位を確認する
- 業界のニュースレターや専門メディアをチェックする
情報を集約し定期的に分析することで、競合の動向や市場のトレンドを把握し続けることができます。
データに基づく継続的な改善
自社のWebサイトのパフォーマンスデータと競合サイトの分析結果を組み合わせて改善を行いましょう。
- Google Analyticsなどのツールで自社サイトのパフォーマンスを測定する
- ヒートマップツールを使ってユーザーの行動を分析する
- 競合サイトとのベンチマーキングを定期的に行う
- A/Bテストを実施し改善の効果を検証する
私がクライアントに提案している方法の一つは「競合ウォッチングシート」の作成です。
このシートに競合の動向、Webサイトの変更点、新しいコンテンツなどを記録し、自社のWebサイトと照らし合わせて戦略に活かします。
継続的な競合分析と改善のサイクルが長期的に競合優位性の維持に繋がります。
競合分析の落とし穴と対処法
競合分析は非常に有効なツールですが、いくつかの落とし穴があります。
よくある落とし穴とその対処法をご紹介します。
競合の真似に終始してしまう罠
競合分析の最大の落とし穴は、「競合の真似に終始してしまう」こと。
競合サイトの良い点を取り入れることは重要ですが、単なるコピーになってしまうと差別化できません。
- 競合分析は「何をすべきか」ではなく「何をすべきでないか」を学ぶためのものでもある
- 業界標準を理解した上で、自社ならではの独自性を追求する
- 競合が行っていないことにこそ、差別化のチャンスがある
競合分析は「業界の常識」を理解するためのものであり、その常識に従うためのものではありません。時には常識を破ることで、大きな差別化ができます。
過剰な競合意識による本質の見失い
もう一つの落とし穴は、「過剰な競合意識によって本質を見失う」こと。
競合との差別化に固執するあまり、顧客のニーズを見失ってしまうケースがあります。
- 常に顧客視点に立ち返る
- 「競合と違うこと」ではなく「顧客にとって価値があること」を優先する
- 競合分析と同じくらい顧客分析にも力を入れる
競合分析の目的は「競合との違い」ではなく「顧客にとっての価値ある差」を見つけること。
競合分析はあくまでその手段であり、目的ではありません。
「競合と違うこと」を目指すのではなく、「顧客にとって最高の価値を提供する」ことを目指しましょう。
結果として競合との差別化につながりますが、出発点は常に顧客のニーズであるべきです。
競合サイト分析に役立つツール紹介
競合サイト分析を効率的に行うには適切なツールの活用が欠かせません。
ここでは、無料と有料に分けて、特に役立つツールを紹介します。

無料ツール
予算に制約がある場合でも、以下の無料ツールを活用することで、基本的な競合分析ができます。
- Google Search Console:自社サイトのSEOパフォーマンスを確認し、競合と比較する基準にできます
- Google PageSpeed Insights:競合サイトのページ速度やパフォーマンスを分析できます
- Ubersuggest:基本的なキーワード分析や競合サイトの上位キーワードを無料で確認できます
- SimilarWeb(無料版):競合サイトのトラフィック推定値や流入元を確認できます
これらの無料ツールを組み合わせることで、競合サイトの基本的な特徴や戦略を把握できます。
UbersuggestやSimilarWebの無料版は、競合サイトの基本的なトラフィックデータやキーワード情報を提供してくれるため初期分析に役立ちます。
有料ツール
より詳細な分析や、大規模なプロジェクトには、以下の有料ツールをおすすめします。
- SEMrush:競合サイトのオーガニックキーワード、広告キーワード、バックリンクなどを包括的に分析できます
- Ahrefs:競合サイトのバックリンクプロファイルや上位コンテンツを詳細に分析できます
- Moz Pro:競合サイトのドメイン権威性やページ権威性、キーワードランキングなどを調査できます
これらの有料ツールはより詳細なデータと分析機能を備えています。
例えばSEMrushやAhrefsでは、競合サイトの全オーガニックキーワードや、そのキーワードでの検索ボリューム、現在の順位などを確認できます。
バックリンク分析機能も充実しており、競合サイトがどのようにリンクを獲得しているかを詳細に調査できます。
競合分析を活かしたWebサイト制作が「成果を生むWebサイト」につながる
Webサイト制作前の競合分析は、成功するWebサイトを作るための必須工程です。
本記事でご紹介した内容をあらためてまとめます。
- 競合分析は単なる表面的な観察ではなく、体系的なプロセスに従って行う
- 真の競合を特定し、情報構造、デザイン、コンテンツ、SEO戦略を分析する
- 分析結果から市場のギャップを見つけ、自社の強みと組み合わせて差別化ポイントを特定する
- 差別化ポイントをWebサイトの情報構造、デザイン、コンテンツに効果的に反映させる
- 競合分析は一度きりではなく、継続的に行い、常に改善を続ける
- 競合の真似に終始せず、顧客視点での価値提供を最優先する
この記事で紹介した必須チェック項目と分析手法の活用が、競合の強みと弱みを理解し、自社サイトの改善点や差別化のポイントを明確にします。
「作っただけのWebサイト」ではなく、「成果を生み出すWebサイト」を制作することができます。
競合分析はWebサイト制作工程の一部であり、Webマーケティング戦略全体の中に位置づけることが重要です。
競合サイト分析は目的ではなく手段であること。
分析の目的は自社のWebサイトとWebマーケティング戦略を改善し、事業目標を達成するためということを忘れないでください。
競合サイト分析を通じて、市場における自社の立ち位置を明確にし、ターゲットユーザーにとって真に価値のあるWebサイトを構築していきましょう。
Webサイトは単なる情報発信ツールではなく、営業・採用・教育・承継に活用できる「情報資産」として捉え、長期的な視点で設計・運用していくことが肝心です。
競合分析に基づいたWebサイト制作、Webマーケティングでお悩みの方は、ぜひBaseTreeにご相談ください。
競合分析から戦略立案、サイト設計まで一貫してサポートいたします。